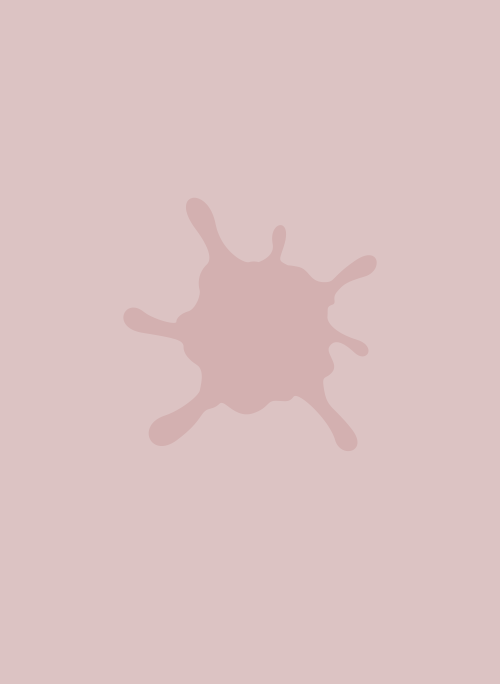こうなると、由理阿は目を開けたくても、怖くて開けられない。
このまま夜明けまで耐えるしかないのだろうか? 何事も起こらなければいいけれど------。
不安と恐怖が心の許容量を超えようとした瞬間、エアコンのお休みタイマーが切れ、音の出所が隣だということが判明した。
隣との間が薄い壁のみで、浅い眠りの中、距離感が鈍っていたのだろう。誰もいないはずの隣で深夜に音がするのは変だけれど、もしかすると、末広さんの家族か親戚の人が、遺品整理と部屋の片付けに来ているのかもしれない。明日、大家に確かめてみよう。少なくともこの部屋には何も異変はない。
由理阿は安堵の胸を撫で下ろした。
だが、それも束の間、今度は、キッチンでもみしみしと足音がし出した。
もう隣のこととは言っていられない。
そのうち、ベランダのサッシ戸を叩く音も聞こえ出した。
風の音ではないことはわかっていた。ぞくぞくっと身も凍るような戦慄が全身を駆け抜けた。
アイボリーのレースのカーテンの向こうに、人の気配を感じた時には、迫り来る恐怖に耐えきれず、沙羅を揺すり起こすしかなかった。
「------由理阿、どうかした?」
寝ぼけ眼に飛び込んできたのは、血の気の失せた由理阿の顔だった。
「あ、あの------」
怯え切った顔から絞るような声が漏れた。震える指はベランダの方を指していた。
何が何だかわからないまま、よろよろと立ち上がった沙羅がサッシ戸に駆け寄った時には、何ら異常は認められなかった。
部屋は深夜の静寂に包まれていた。
「------沙羅、あたし怖いよ」
暗闇に浮かぶ青白い顔から消え入りそうな声が漏れた。
「深夜番組でも見よっか。この時間って何やってたっけ?」
何を思ったのか、沙羅はためらうことなく部屋の隅に置かれたテレビのスイッチを入れた。
一瞬、ゲームソフトか何かのコマーシャルが映った後、誰も触っていないのに、あっという間にチャンネルが変わり、止まることなく次々と変わり続け、最後は砂嵐状態になった。沙羅が立ち上がり掛けたが、スイッチを切るまでもなく、パッとカメラのフラッシュのような閃光を放ちテレビは独りでに消えていた。
次の瞬間、テレビの前に女が立っていた。暗闇の中に、血の気のない顔と薄汚れた白い着物がぼんやりと浮かび上がっている。うつむいているので、表情をうかがい知ることはできない。
由理阿は、女の姿を見ただけで背筋がぞくぞくした。二人は、身動きもできず、恐怖に引きつったお互いの顔を見合わせた。
胸が締め付けられるような圧迫感に耐え切れなくなった由理阿は、思わずうめき声を上げた。すると、だらりと垂れた手首が目の前をすーっと通り過ぎた。
女の体は部屋の隅から隅へ移動していた。歩いたというよりも床の少し上を滑ったような感じだ。
「う------うう------うううう------」
悲しそうな女のすすり泣きは、耳から聞こえたのではなく、直接意識の中に入り込んできたような感じがした。
「------あなた、忘れてしまいましたか、私と交わした約束を? 気の遠くなるほどの長い間、この時を待っていました------」
初めて聞いたはずなのに、その声にはどこか懐かしい響きがあった。
女は話の途中で咳き込んだかと思うと、血を吐いた。
「永遠に光の差すことのない、漆黒の闇の中で、いつかこの日が来ることを願っていました------」
苦しい息の下で話し続けた。呼吸器系を病んでいるようだ。
消え入るような声で、不思議なくらい穏やかな口調なのに、どこかに威圧的な怖さを含んでいた。
「とうとう、こうしてあなたに会うことができました------」
「ました------」の「た」は、かろうじて聞き取れたが、そこまで言うと、女は消えていた。
不意に由理阿はソファに押し倒された。
何者かが物凄い力でのしかかってきていた。
戸締りはしっかりしてあるから、人が入ってくることなんてありえないのに------。
わけもわからないまま、押さえ込まれた時、甘酸っぱい汗の匂いに混じって、ほんのりと薔薇の香りがした。
この香水を付けているのは------?
暴行を働いているのが沙羅だと気づいた時には、声も出せなかった。
沙羅、何をするのよ! 正気を取り戻してよ!
そう叫びたくても、すでに沙羅の指が自分の首に食い込んでいた。
遠のいていく意識の中で、由理阿は不思議な感覚に囚われていた。自分の首を絞めている手が、子どもの手のように小さく感じられたのだ。
このまま夜明けまで耐えるしかないのだろうか? 何事も起こらなければいいけれど------。
不安と恐怖が心の許容量を超えようとした瞬間、エアコンのお休みタイマーが切れ、音の出所が隣だということが判明した。
隣との間が薄い壁のみで、浅い眠りの中、距離感が鈍っていたのだろう。誰もいないはずの隣で深夜に音がするのは変だけれど、もしかすると、末広さんの家族か親戚の人が、遺品整理と部屋の片付けに来ているのかもしれない。明日、大家に確かめてみよう。少なくともこの部屋には何も異変はない。
由理阿は安堵の胸を撫で下ろした。
だが、それも束の間、今度は、キッチンでもみしみしと足音がし出した。
もう隣のこととは言っていられない。
そのうち、ベランダのサッシ戸を叩く音も聞こえ出した。
風の音ではないことはわかっていた。ぞくぞくっと身も凍るような戦慄が全身を駆け抜けた。
アイボリーのレースのカーテンの向こうに、人の気配を感じた時には、迫り来る恐怖に耐えきれず、沙羅を揺すり起こすしかなかった。
「------由理阿、どうかした?」
寝ぼけ眼に飛び込んできたのは、血の気の失せた由理阿の顔だった。
「あ、あの------」
怯え切った顔から絞るような声が漏れた。震える指はベランダの方を指していた。
何が何だかわからないまま、よろよろと立ち上がった沙羅がサッシ戸に駆け寄った時には、何ら異常は認められなかった。
部屋は深夜の静寂に包まれていた。
「------沙羅、あたし怖いよ」
暗闇に浮かぶ青白い顔から消え入りそうな声が漏れた。
「深夜番組でも見よっか。この時間って何やってたっけ?」
何を思ったのか、沙羅はためらうことなく部屋の隅に置かれたテレビのスイッチを入れた。
一瞬、ゲームソフトか何かのコマーシャルが映った後、誰も触っていないのに、あっという間にチャンネルが変わり、止まることなく次々と変わり続け、最後は砂嵐状態になった。沙羅が立ち上がり掛けたが、スイッチを切るまでもなく、パッとカメラのフラッシュのような閃光を放ちテレビは独りでに消えていた。
次の瞬間、テレビの前に女が立っていた。暗闇の中に、血の気のない顔と薄汚れた白い着物がぼんやりと浮かび上がっている。うつむいているので、表情をうかがい知ることはできない。
由理阿は、女の姿を見ただけで背筋がぞくぞくした。二人は、身動きもできず、恐怖に引きつったお互いの顔を見合わせた。
胸が締め付けられるような圧迫感に耐え切れなくなった由理阿は、思わずうめき声を上げた。すると、だらりと垂れた手首が目の前をすーっと通り過ぎた。
女の体は部屋の隅から隅へ移動していた。歩いたというよりも床の少し上を滑ったような感じだ。
「う------うう------うううう------」
悲しそうな女のすすり泣きは、耳から聞こえたのではなく、直接意識の中に入り込んできたような感じがした。
「------あなた、忘れてしまいましたか、私と交わした約束を? 気の遠くなるほどの長い間、この時を待っていました------」
初めて聞いたはずなのに、その声にはどこか懐かしい響きがあった。
女は話の途中で咳き込んだかと思うと、血を吐いた。
「永遠に光の差すことのない、漆黒の闇の中で、いつかこの日が来ることを願っていました------」
苦しい息の下で話し続けた。呼吸器系を病んでいるようだ。
消え入るような声で、不思議なくらい穏やかな口調なのに、どこかに威圧的な怖さを含んでいた。
「とうとう、こうしてあなたに会うことができました------」
「ました------」の「た」は、かろうじて聞き取れたが、そこまで言うと、女は消えていた。
不意に由理阿はソファに押し倒された。
何者かが物凄い力でのしかかってきていた。
戸締りはしっかりしてあるから、人が入ってくることなんてありえないのに------。
わけもわからないまま、押さえ込まれた時、甘酸っぱい汗の匂いに混じって、ほんのりと薔薇の香りがした。
この香水を付けているのは------?
暴行を働いているのが沙羅だと気づいた時には、声も出せなかった。
沙羅、何をするのよ! 正気を取り戻してよ!
そう叫びたくても、すでに沙羅の指が自分の首に食い込んでいた。
遠のいていく意識の中で、由理阿は不思議な感覚に囚われていた。自分の首を絞めている手が、子どもの手のように小さく感じられたのだ。