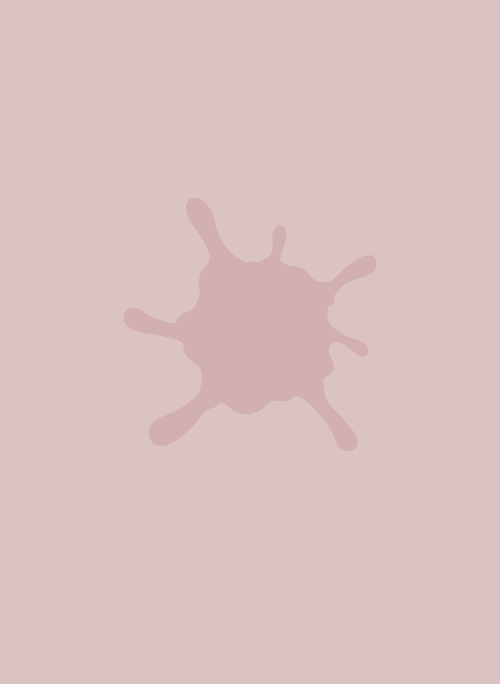一瞬あっけに取られて後姿を見送っていた。パジャマに見えたのは、マルチチェックのシャツで、男か女かわからないような、かつらのようにボリュームのある髪も、後ろから見れば、曲がりなりにもバンダナで束ねてあった。
その後、外出・帰宅時にアパート周辺で顔を合わせることがあったけれど、常にそんな格好だった。マルチチェックのシャツの裾をケミカルウオッシュのジーンズの中にわざと入れずに、白のTシャツの上に羽織っていることが多かったけれど、迷彩などのミリタリールックのジャケットの時もあった。ただし、どんな時にもペイズリー柄のバンダナで髪を束ね、銀縁眼鏡の向こう側から伏し目がちの軽い会釈を返してきた。
そんな時、決まって背筋にひやりとしたものを感じた。前にどこかで会っているという気がしてならなかった。だから、幾度か記憶の糸を懸命にたぐり寄せようと試みたのに、何も脳裏に浮かんではこなかった。
ただ、由理阿がどうしても理解しかねることは、巻き添えとなり一緒に連れて行かれそうになったというのに、末広に対してそれほど激しい憤りを感じないことだ。あれほど苦しい思いをしたというのに。頭痛・眩暈・吐き気に襲われ、由理阿は本当に死ぬかと思った。
不意にドアを叩く音が聞こえた。
こんな大変なことがあった日に一体誰かしら?
怖怖開けると、大家だった。
つい先ほど会ったばかりなのに、どうしたというのだろう?
不安が募る。
「------神垣さん、お邪魔します。もう休んでるかと思ったんだけれど、どうしても、できるだけ早く知らせておかなきゃならないことがあって------」
いかにもすまなさそうな表情で言う。
「はい」
由理阿は力なく答える。
「実は、つい今し方、末広さんのお父さんから明日の昼ごろ来るって電話があったんです。神主さんだから、そんなにちょくちょく神社を留守にするわけにもいかないし------、何しろ東北の田舎で、朝一番の新幹線に乗っても、ここに着くのは昼ごろになるっていうのに、日帰りしなきゃならないんですって。そういうわけで、あまりゆっくりもできないのに、皆さんに直接会って謝罪したいって言うのよ。そんな時間に来ても、皆さん学校、仕事に出払ってて、誰もいませんよって言ったんだけれど------」
由理阿に異変が起きていた。もう大家の顔も見えていなかったし、声も聞こえていなかった。
それに気づかず大家は続ける。
「まあ、会うっていったってねえ------、杓子定規なお詫びを聞くだけで、むしろ腹が立つだけかもしれないけれど------。かといって、死んでしまった息子が掛けた迷惑で残された親を責めるのも理不尽だし、会っても気まずいだけで、会わないほうがいいかもしれないわねえ------」
大家は、自分の言ったことを頭の中で反芻するかのようにしみじみ言う。
由理阿はうなずこうともしない。
その時、由理阿には夢の中で自分を刺し殺した神主の顔が見えていた。
見覚えのある顔だとは思ったけど、まさか、こんなことって------。
由理阿の脳裏には夢の中の神社のシーンがまざまざとフラッシュバックしていた。
小太刀が体に刺さってきた瞬間のひんやりした感触と、自分は死ぬんだという恐怖が甦り、心臓が破れそうなほど高鳴っていた。
「由理阿、嫌な予感するって言ってたよねえ。悪夢が現実になったんだ――。同じ週に立て続けに踏切飛込みで一人、硫化水素で一人死んじゃうなんてね。そんなことって、絶対普通じゃないよ――。二人には何のつながりもないんでしょう? 偶然というよりもこの辺の土地って呪われてるんじゃない? この辺りに不成仏霊とかうじゃうじゃ彷徨ってたりしてね------」
テレビで硫化水素自殺のニュースを見た沙羅が、心配して訪ねてきてくれた。
「ちょっと沙羅、他人事みたいに言わないでよ。女の切断された足首が飛んできたり、毒ガス吸わされたりで、もうまいってるんだから。あたしの身にもなってよ――」
由理阿は口を尖らせている。
「あっ、悪かった。でも、まあ大事に至らなくてよかったじゃない」
「まあ今までのところはそうだけど、本当にこれで終わったのかなあ?」
「そう言われてみれば、由理阿の夢の話と今回の事件は、あんまり関係があるように思えないもんね――」
「でしょう? 夢の中ではあたしが殺されるんだけど、現実には身近な所で人が死んでいる。そのうち、あたしが死ぬ番が回ってくるのかなあ? 沙羅、そもそも殺される夢にどんな意味があるのよ?」
救いを求めるような目で沙羅を見つめる。
「------そうねえ、あたしの知ってる限りでは、今の自分が死んで、新しい自分に生まれ変わるとか、問題が解決していくとかいう解釈が普通みたいだから------」
「ということは、意外と前向きな夢っていうか、心配しなくていいのかなあ?」
一瞬、由理阿の顔が緩む。
「------でもね、自分が殺される夢を見るってことは、自分自身を心理的に攻撃してるってことで、罪悪感の表れと考える向きもあるのよ。独断と偏見で言わせてもらえば、自分の思い出したくない体験を消し去ろうとする、気持ちの表れじゃないかなあと思うんだけど------」
「そ、そんなあ。もしそれが本当なら、消去してしまいたい体験って何なんだろう?」
失望の色が由理阿の顔を横切る。
「由理阿、虫も殺さないような顔してるけど、何かうしろめたいことしてるんじゃないの?何か思い当たる節ない?」
「そ、そんなこと言われても、あたし何もしてないから------」
由理阿は言葉に詰まる。
「------由理阿、不安をかき立てるようなこと言っときながら、こんなこと言うのも変だけど、あんまり心配しないほうがいいって。あんまり役に立たないかもしれないけど、困ったことがあれば、いつでもあたしを呼んで」
沙羅の温かい気持ちが由理阿に伝わってくる。
「ありがとう。じゃ、お言葉に甘えて、困ったときには遠慮なく呼ぶからね」
「ところでさ、由理阿。さっきからちょっと気になってたんだけど、お香か何か焚いた?」
「あっ、そうか。まだ香りが残ってたんだよね。色々あったから、心を落ち着かせるっていうか、リラックスするために何がいいのかなあって、ちょっとネットとかで調べて、アロマセラピーを見つけたってわけ」
「何だ。そういうことか。ところで、このお香って何なの?」
「これは白檀っていって、香木なのよ。リラックス効果があって、ストレスを和らげるんだって。香炉まで買ったんだから」
「ねえ、由理阿、ほんのり甘くっていい香りが漂ってるわ。もうちょっと焚いてくんないかなあ?」
「沙羅が気に入ってくれてうれしいよ。ちょっとこっち来て。」
二人はキッチンへ移動する。
「本当は、こんなやり方はよくないんだろうけどね」
そう言いながら由理阿はガス火の上に炭を置く。
「これ、香炉っていうの。素材も色々あるんだけど、あたしのは京焼」
「紅白梅か。かわいいね」
沙羅の声が弾んでいる。
由理阿は火が点いた炭を香炉の灰に埋め、その上に香木を載せる。
煙が香りとともにくゆっている。
「わあ――っ、すごい! あたしもはまりそう」
沙羅の目が輝いている。
「ところで、由理阿、お腹すいてない? もうすぐ7時よ。あたし、今日お昼にあんまり食べなかったから、もうペコペコ」
「もう沙羅ったら。これからしばらくお香の香りに包まれながらゆったりした時の流れに身を任せようとしてたのに――」
「残念だったね、由理阿。でも、料理はあたしに任せて。今日のような蒸し暑い日にぴったりの丼物の作り方を覚えたところなのよ。冷蔵庫の中の物、好きに使わせてくれるよね?」
「どうぞお好きなように。本当のこと言うと、もう一つ見せたい物があるんだけど、あたしもお腹すいちゃったから、後にするね」
「------覚えてるよ。由理阿が包丁使えないってこと。先の尖った物とか見るだけで怖くてたまんなくなるんだったよね。あたしが料理してる間、あっちに行ってていいよ。終わったら呼ぶから」
沙羅の声が妙に落ち着いていた。
「ありがとう」
沙羅の心遣いがうれしかった。
「ちょっと由理阿、最近自炊してないんじゃないの? 炊飯器ほこり被ってるよ」
「いやっ、その、自炊はしてるんだけど、あたしって、あんまし白いご飯って食べないほうだから------」
由理阿の歯切れの悪い返事を聞きながら、沙羅はさっそく料理に取り掛かる。
さっと洗った米を炊飯器に入れ、白米高速スイッチを押す。
小鍋にオリーブオイルを敷き、種を取った唐辛子とニンニクとねぎを細かく潰して弱火で炒め、焼き色が付いてきたところで醤油を加えてたれを作る。炊き立てのご飯の上に冷えた豆腐・きゅうり・トマトを切って載せ、たれをかけると出来上がりだ。夏ばて防止のぴりっと辛い豆腐丼ってところだ。
パスタを含め麺類好きの由理阿にとっては、久々の白ご飯の食事だ。
「へええ、短時間でも、こんなにふっくら炊き上がるんだ。白米高速ってほとんど使ったことなかったから、気がつかなかった」
沙羅の訪問が久々だったこともあり、夕食後も話が弾んだ。
大学ではしょっちゅう顔を合わすけれど、そんなにゆっくり話はできない。やっぱりうちは違う。
そんなことを思いながら、由理阿がカモミールティーを入れて戻ってくると、テレビを見ていた沙羅は、いつの間にかソファで眠ってしまっていた。
由理阿も食後の片付けの後すぐに床に就いたものの、夜になっても一向に気温が下がらない熱帯夜。いつになっても寝付かれない。
寝返りを打つ度に、すやすやと寝息を立てている沙羅がうらやましかった。
こんなに寝苦しい夜に眠れるなんて、よっぽど疲れていたのかな?
睡眠中に風邪をひかないように、由理阿は夜はできるだけエアコンの使用を控えているが、こうなってはやむを得ない。エアコンのスイッチを入れるついでに、沙羅の安らかな寝顔を見ながらそっとガーゼケットを掛けてやる。
ベッドに戻ってからは、人工の冷風を浴びながら、しばしうつらうつらと浅い眠りの中にいた。
どれくらい時間が経ったのだろう?
由理阿はエアコンの作動音に混じって声が聞こえたような気がした。そのうちみしみしと床がきしむ音もしてきた。空耳だと必死で自分に言い聞かせようにも、一向に足音は止まらない。外部から人が侵入してくることはありえないのに。ドアの鍵もチェーンも掛けてある。
由理阿は、目を閉じてじっとしていると、恐怖が静かにじわじわと体に染み込んでくるような感覚に襲われた。
恐怖が心を満たした瞬間、高校の時同級生から聞いた、怖い話が意識に浮上してきた。深夜ににベッドの回りをうろうろ歩き回る女の霊の目撃談だ。
古びた木造アパートに越して来た夜、床に就いてしばらくすると、机の周りをうろうろと歩き回る足音がする。気のせいだと思いたくても、やがてその足音は自分が寝ているベッドの周りに移ってきた。
怖くて目を閉じてじっとしているしかない。
足音がぴたりと止まった時、様子を覗おうと恐る恐る薄目を開けると、枕元に髪の長い青白い顔をした白い着物姿の女が立ち、自分の顔を上から覗き込んでいた。
全身の血が凍るような感覚に襲われた。
恐怖のあまり頭から布団を被り、ぎゅっと目をつぶる。すると、血がどろどろ流れる映像が瞼の裏に映し出された。はっと反射的に目を開けると、布団の中の闇があるだけ。再び目を閉じると、鮮烈な映像が流れ出す。何度かそんなことを繰り返すうちに、眠りに落ちた。
翌朝、部屋を片付けている時、箪笥の後ろに押入れがあることに気づく。何か秘密が隠されているようで気になり、すぐに箪笥を動かし、押入れを開けてみる。中は空っぽだったが、上段の床と壁に赤い絵の具を撒き散らしたような染みが広がっていた。それは、みるみるうちに光沢を帯びた粘液状に変化していく。
その後、外出・帰宅時にアパート周辺で顔を合わせることがあったけれど、常にそんな格好だった。マルチチェックのシャツの裾をケミカルウオッシュのジーンズの中にわざと入れずに、白のTシャツの上に羽織っていることが多かったけれど、迷彩などのミリタリールックのジャケットの時もあった。ただし、どんな時にもペイズリー柄のバンダナで髪を束ね、銀縁眼鏡の向こう側から伏し目がちの軽い会釈を返してきた。
そんな時、決まって背筋にひやりとしたものを感じた。前にどこかで会っているという気がしてならなかった。だから、幾度か記憶の糸を懸命にたぐり寄せようと試みたのに、何も脳裏に浮かんではこなかった。
ただ、由理阿がどうしても理解しかねることは、巻き添えとなり一緒に連れて行かれそうになったというのに、末広に対してそれほど激しい憤りを感じないことだ。あれほど苦しい思いをしたというのに。頭痛・眩暈・吐き気に襲われ、由理阿は本当に死ぬかと思った。
不意にドアを叩く音が聞こえた。
こんな大変なことがあった日に一体誰かしら?
怖怖開けると、大家だった。
つい先ほど会ったばかりなのに、どうしたというのだろう?
不安が募る。
「------神垣さん、お邪魔します。もう休んでるかと思ったんだけれど、どうしても、できるだけ早く知らせておかなきゃならないことがあって------」
いかにもすまなさそうな表情で言う。
「はい」
由理阿は力なく答える。
「実は、つい今し方、末広さんのお父さんから明日の昼ごろ来るって電話があったんです。神主さんだから、そんなにちょくちょく神社を留守にするわけにもいかないし------、何しろ東北の田舎で、朝一番の新幹線に乗っても、ここに着くのは昼ごろになるっていうのに、日帰りしなきゃならないんですって。そういうわけで、あまりゆっくりもできないのに、皆さんに直接会って謝罪したいって言うのよ。そんな時間に来ても、皆さん学校、仕事に出払ってて、誰もいませんよって言ったんだけれど------」
由理阿に異変が起きていた。もう大家の顔も見えていなかったし、声も聞こえていなかった。
それに気づかず大家は続ける。
「まあ、会うっていったってねえ------、杓子定規なお詫びを聞くだけで、むしろ腹が立つだけかもしれないけれど------。かといって、死んでしまった息子が掛けた迷惑で残された親を責めるのも理不尽だし、会っても気まずいだけで、会わないほうがいいかもしれないわねえ------」
大家は、自分の言ったことを頭の中で反芻するかのようにしみじみ言う。
由理阿はうなずこうともしない。
その時、由理阿には夢の中で自分を刺し殺した神主の顔が見えていた。
見覚えのある顔だとは思ったけど、まさか、こんなことって------。
由理阿の脳裏には夢の中の神社のシーンがまざまざとフラッシュバックしていた。
小太刀が体に刺さってきた瞬間のひんやりした感触と、自分は死ぬんだという恐怖が甦り、心臓が破れそうなほど高鳴っていた。
「由理阿、嫌な予感するって言ってたよねえ。悪夢が現実になったんだ――。同じ週に立て続けに踏切飛込みで一人、硫化水素で一人死んじゃうなんてね。そんなことって、絶対普通じゃないよ――。二人には何のつながりもないんでしょう? 偶然というよりもこの辺の土地って呪われてるんじゃない? この辺りに不成仏霊とかうじゃうじゃ彷徨ってたりしてね------」
テレビで硫化水素自殺のニュースを見た沙羅が、心配して訪ねてきてくれた。
「ちょっと沙羅、他人事みたいに言わないでよ。女の切断された足首が飛んできたり、毒ガス吸わされたりで、もうまいってるんだから。あたしの身にもなってよ――」
由理阿は口を尖らせている。
「あっ、悪かった。でも、まあ大事に至らなくてよかったじゃない」
「まあ今までのところはそうだけど、本当にこれで終わったのかなあ?」
「そう言われてみれば、由理阿の夢の話と今回の事件は、あんまり関係があるように思えないもんね――」
「でしょう? 夢の中ではあたしが殺されるんだけど、現実には身近な所で人が死んでいる。そのうち、あたしが死ぬ番が回ってくるのかなあ? 沙羅、そもそも殺される夢にどんな意味があるのよ?」
救いを求めるような目で沙羅を見つめる。
「------そうねえ、あたしの知ってる限りでは、今の自分が死んで、新しい自分に生まれ変わるとか、問題が解決していくとかいう解釈が普通みたいだから------」
「ということは、意外と前向きな夢っていうか、心配しなくていいのかなあ?」
一瞬、由理阿の顔が緩む。
「------でもね、自分が殺される夢を見るってことは、自分自身を心理的に攻撃してるってことで、罪悪感の表れと考える向きもあるのよ。独断と偏見で言わせてもらえば、自分の思い出したくない体験を消し去ろうとする、気持ちの表れじゃないかなあと思うんだけど------」
「そ、そんなあ。もしそれが本当なら、消去してしまいたい体験って何なんだろう?」
失望の色が由理阿の顔を横切る。
「由理阿、虫も殺さないような顔してるけど、何かうしろめたいことしてるんじゃないの?何か思い当たる節ない?」
「そ、そんなこと言われても、あたし何もしてないから------」
由理阿は言葉に詰まる。
「------由理阿、不安をかき立てるようなこと言っときながら、こんなこと言うのも変だけど、あんまり心配しないほうがいいって。あんまり役に立たないかもしれないけど、困ったことがあれば、いつでもあたしを呼んで」
沙羅の温かい気持ちが由理阿に伝わってくる。
「ありがとう。じゃ、お言葉に甘えて、困ったときには遠慮なく呼ぶからね」
「ところでさ、由理阿。さっきからちょっと気になってたんだけど、お香か何か焚いた?」
「あっ、そうか。まだ香りが残ってたんだよね。色々あったから、心を落ち着かせるっていうか、リラックスするために何がいいのかなあって、ちょっとネットとかで調べて、アロマセラピーを見つけたってわけ」
「何だ。そういうことか。ところで、このお香って何なの?」
「これは白檀っていって、香木なのよ。リラックス効果があって、ストレスを和らげるんだって。香炉まで買ったんだから」
「ねえ、由理阿、ほんのり甘くっていい香りが漂ってるわ。もうちょっと焚いてくんないかなあ?」
「沙羅が気に入ってくれてうれしいよ。ちょっとこっち来て。」
二人はキッチンへ移動する。
「本当は、こんなやり方はよくないんだろうけどね」
そう言いながら由理阿はガス火の上に炭を置く。
「これ、香炉っていうの。素材も色々あるんだけど、あたしのは京焼」
「紅白梅か。かわいいね」
沙羅の声が弾んでいる。
由理阿は火が点いた炭を香炉の灰に埋め、その上に香木を載せる。
煙が香りとともにくゆっている。
「わあ――っ、すごい! あたしもはまりそう」
沙羅の目が輝いている。
「ところで、由理阿、お腹すいてない? もうすぐ7時よ。あたし、今日お昼にあんまり食べなかったから、もうペコペコ」
「もう沙羅ったら。これからしばらくお香の香りに包まれながらゆったりした時の流れに身を任せようとしてたのに――」
「残念だったね、由理阿。でも、料理はあたしに任せて。今日のような蒸し暑い日にぴったりの丼物の作り方を覚えたところなのよ。冷蔵庫の中の物、好きに使わせてくれるよね?」
「どうぞお好きなように。本当のこと言うと、もう一つ見せたい物があるんだけど、あたしもお腹すいちゃったから、後にするね」
「------覚えてるよ。由理阿が包丁使えないってこと。先の尖った物とか見るだけで怖くてたまんなくなるんだったよね。あたしが料理してる間、あっちに行ってていいよ。終わったら呼ぶから」
沙羅の声が妙に落ち着いていた。
「ありがとう」
沙羅の心遣いがうれしかった。
「ちょっと由理阿、最近自炊してないんじゃないの? 炊飯器ほこり被ってるよ」
「いやっ、その、自炊はしてるんだけど、あたしって、あんまし白いご飯って食べないほうだから------」
由理阿の歯切れの悪い返事を聞きながら、沙羅はさっそく料理に取り掛かる。
さっと洗った米を炊飯器に入れ、白米高速スイッチを押す。
小鍋にオリーブオイルを敷き、種を取った唐辛子とニンニクとねぎを細かく潰して弱火で炒め、焼き色が付いてきたところで醤油を加えてたれを作る。炊き立てのご飯の上に冷えた豆腐・きゅうり・トマトを切って載せ、たれをかけると出来上がりだ。夏ばて防止のぴりっと辛い豆腐丼ってところだ。
パスタを含め麺類好きの由理阿にとっては、久々の白ご飯の食事だ。
「へええ、短時間でも、こんなにふっくら炊き上がるんだ。白米高速ってほとんど使ったことなかったから、気がつかなかった」
沙羅の訪問が久々だったこともあり、夕食後も話が弾んだ。
大学ではしょっちゅう顔を合わすけれど、そんなにゆっくり話はできない。やっぱりうちは違う。
そんなことを思いながら、由理阿がカモミールティーを入れて戻ってくると、テレビを見ていた沙羅は、いつの間にかソファで眠ってしまっていた。
由理阿も食後の片付けの後すぐに床に就いたものの、夜になっても一向に気温が下がらない熱帯夜。いつになっても寝付かれない。
寝返りを打つ度に、すやすやと寝息を立てている沙羅がうらやましかった。
こんなに寝苦しい夜に眠れるなんて、よっぽど疲れていたのかな?
睡眠中に風邪をひかないように、由理阿は夜はできるだけエアコンの使用を控えているが、こうなってはやむを得ない。エアコンのスイッチを入れるついでに、沙羅の安らかな寝顔を見ながらそっとガーゼケットを掛けてやる。
ベッドに戻ってからは、人工の冷風を浴びながら、しばしうつらうつらと浅い眠りの中にいた。
どれくらい時間が経ったのだろう?
由理阿はエアコンの作動音に混じって声が聞こえたような気がした。そのうちみしみしと床がきしむ音もしてきた。空耳だと必死で自分に言い聞かせようにも、一向に足音は止まらない。外部から人が侵入してくることはありえないのに。ドアの鍵もチェーンも掛けてある。
由理阿は、目を閉じてじっとしていると、恐怖が静かにじわじわと体に染み込んでくるような感覚に襲われた。
恐怖が心を満たした瞬間、高校の時同級生から聞いた、怖い話が意識に浮上してきた。深夜ににベッドの回りをうろうろ歩き回る女の霊の目撃談だ。
古びた木造アパートに越して来た夜、床に就いてしばらくすると、机の周りをうろうろと歩き回る足音がする。気のせいだと思いたくても、やがてその足音は自分が寝ているベッドの周りに移ってきた。
怖くて目を閉じてじっとしているしかない。
足音がぴたりと止まった時、様子を覗おうと恐る恐る薄目を開けると、枕元に髪の長い青白い顔をした白い着物姿の女が立ち、自分の顔を上から覗き込んでいた。
全身の血が凍るような感覚に襲われた。
恐怖のあまり頭から布団を被り、ぎゅっと目をつぶる。すると、血がどろどろ流れる映像が瞼の裏に映し出された。はっと反射的に目を開けると、布団の中の闇があるだけ。再び目を閉じると、鮮烈な映像が流れ出す。何度かそんなことを繰り返すうちに、眠りに落ちた。
翌朝、部屋を片付けている時、箪笥の後ろに押入れがあることに気づく。何か秘密が隠されているようで気になり、すぐに箪笥を動かし、押入れを開けてみる。中は空っぽだったが、上段の床と壁に赤い絵の具を撒き散らしたような染みが広がっていた。それは、みるみるうちに光沢を帯びた粘液状に変化していく。