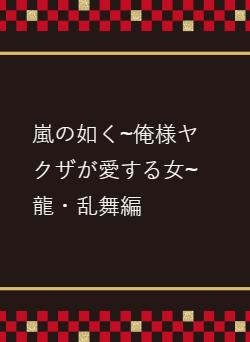コイツが無断で、金庫から『呪いのエンゲージリング』を盗み、花奏の薬指に嵌めたりしなければ・・・
「肩も凝ってれば、揉みますが…」
「余計な心遣いは無用だ…爽爾」
「でも・・・」
爽爾は俺の拒絶に、難色を示した。
「じゃあ~俺はどうすればいいの?」
爽爾の瞳にはウルウルと涙が溢れる。
「どうって・・・」
コイツに八つ当たりしても、花奏の意識が戻るワケでもなくて。
でも、爽爾を見ていると、怒りがこみ上げてくる。
「花奏の力を信じるしかないだろ?」
「それもそうだね」
俺はポンとガクリと落とした爽爾の肩を叩き、慰める。
『紅月』の魂を躰に喰らい、その存在に気づき、ヤツの力を覚醒させた時から…俺は本物の妖となった。
妖狐の純血種の爽爾を心から憎めなかった。
同じ妖だから。
「肩も凝ってれば、揉みますが…」
「余計な心遣いは無用だ…爽爾」
「でも・・・」
爽爾は俺の拒絶に、難色を示した。
「じゃあ~俺はどうすればいいの?」
爽爾の瞳にはウルウルと涙が溢れる。
「どうって・・・」
コイツに八つ当たりしても、花奏の意識が戻るワケでもなくて。
でも、爽爾を見ていると、怒りがこみ上げてくる。
「花奏の力を信じるしかないだろ?」
「それもそうだね」
俺はポンとガクリと落とした爽爾の肩を叩き、慰める。
『紅月』の魂を躰に喰らい、その存在に気づき、ヤツの力を覚醒させた時から…俺は本物の妖となった。
妖狐の純血種の爽爾を心から憎めなかった。
同じ妖だから。