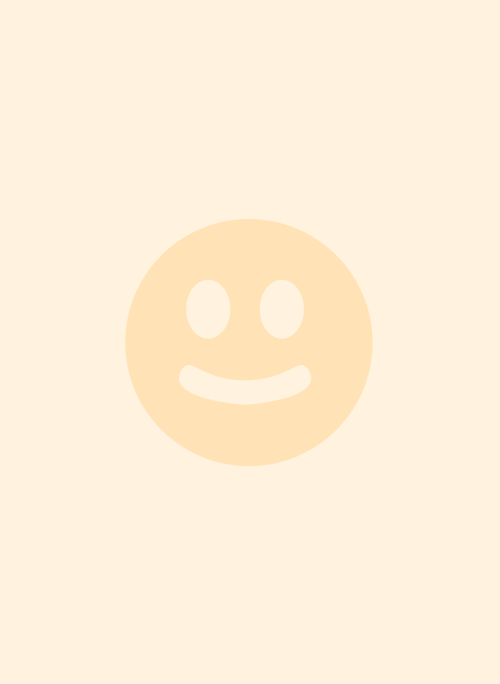一ページの半分が終わった頃に高津が何をしているのかと聞いてきた。
「読書感想文」
「やってなかったの?ショッボー」
「ほっとけ」
「何の本読んだの?」
「チョコレートの町」
「飛鳥井千砂の?」
「そうだな」
高津のほうを向くと、目が「キラキラ」という言葉が似合うくらい輝いている。
「他の作品読んだことある?」
「学校のセンセイ・・・」
「充分充分!」
何がだ。
「それで、チョコレートの町を読んで君は何についてを書こうと思ったのかな?」
「んー・・・故郷の大切さ?」
「惜しい!」
何が惜しいんだ。
「君はあの物語を読んで、自分が将来都会に出て帰ってくるときどう思うと思った?」
「あー・・・あんま帰りたくないかも。親不孝な発言だけど・・・」
「それさ!」
「は?」
「チョコレートの町の主人公は最初、故郷に帰るのに乗り気じゃなかった。これがあの物語と君の共通部分」
「共通部分・・・」
「ただ単に感想を書こうとするから面倒くさいのさ。主人公に共感出来るところを自分ならどうするか。物語の中で起きた出来事が自分の身近でもなかったか。そういうのを比較しながら書いていくといいよ」
確かに、感想を書けといわれても、面白かったです。としか言いようがない。と、毎回思っていた。
「でも、それを5枚で書き終わらないといけないのが大変なんだよな」
「意外とこの書き方だと、五枚なんてあっという間だよ。自分の事書くのは何も見なくても書けるしね」
「なんか簡単に思えてきた」
「でしょ!」
あ、笑顔になれるのか。と、思った。
失礼な話、高津に素直な笑顔を浮かべることが出来るとは思っていなかった。
「失礼いたしやした」
「何が?」
「いや、こっちの話」
「変なの」と、言いながら高津は立ち上がった。
「じゃあ、電車だから帰るわ」
「おう。ありがとな」
「じゃーね」
あ、動いた。そういえば、この間も図書室を出て行くときに歩いていたな。
当たり前のことだが、妙な感動をした。
「読書感想文」
「やってなかったの?ショッボー」
「ほっとけ」
「何の本読んだの?」
「チョコレートの町」
「飛鳥井千砂の?」
「そうだな」
高津のほうを向くと、目が「キラキラ」という言葉が似合うくらい輝いている。
「他の作品読んだことある?」
「学校のセンセイ・・・」
「充分充分!」
何がだ。
「それで、チョコレートの町を読んで君は何についてを書こうと思ったのかな?」
「んー・・・故郷の大切さ?」
「惜しい!」
何が惜しいんだ。
「君はあの物語を読んで、自分が将来都会に出て帰ってくるときどう思うと思った?」
「あー・・・あんま帰りたくないかも。親不孝な発言だけど・・・」
「それさ!」
「は?」
「チョコレートの町の主人公は最初、故郷に帰るのに乗り気じゃなかった。これがあの物語と君の共通部分」
「共通部分・・・」
「ただ単に感想を書こうとするから面倒くさいのさ。主人公に共感出来るところを自分ならどうするか。物語の中で起きた出来事が自分の身近でもなかったか。そういうのを比較しながら書いていくといいよ」
確かに、感想を書けといわれても、面白かったです。としか言いようがない。と、毎回思っていた。
「でも、それを5枚で書き終わらないといけないのが大変なんだよな」
「意外とこの書き方だと、五枚なんてあっという間だよ。自分の事書くのは何も見なくても書けるしね」
「なんか簡単に思えてきた」
「でしょ!」
あ、笑顔になれるのか。と、思った。
失礼な話、高津に素直な笑顔を浮かべることが出来るとは思っていなかった。
「失礼いたしやした」
「何が?」
「いや、こっちの話」
「変なの」と、言いながら高津は立ち上がった。
「じゃあ、電車だから帰るわ」
「おう。ありがとな」
「じゃーね」
あ、動いた。そういえば、この間も図書室を出て行くときに歩いていたな。
当たり前のことだが、妙な感動をした。