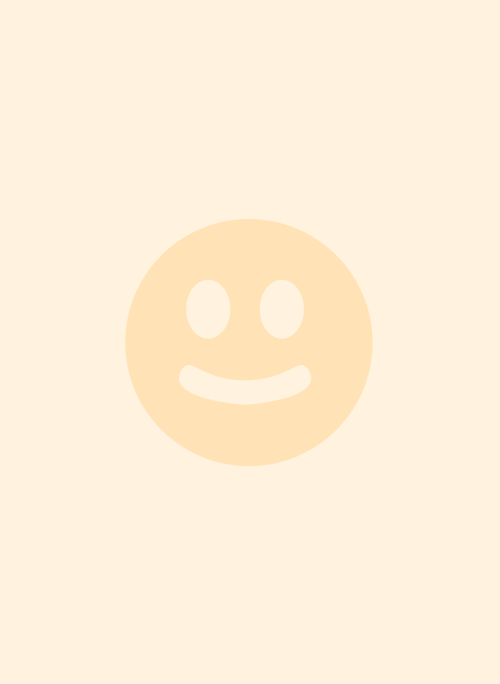着物を着たその人は見た目に反して背筋のシャンをした老婆だった。
「頑張ってるかい千沙。・・・・てっちゃんによし坊?」
「ばあちゃん!」
「「敏子ちゃん!」」
三人で顔を見合う。
「トシコって、うちのばあちゃんのことだったの?」
「本当に三世じゃったか」
「どうりで似ているはずじゃ」
三人で頷きあう。
「ねぇばあちゃん。この二人に告白されたんでしょ?」
「あら。よう知っとるねぇ」
敏子は思い出すように頷いた。
「そう。あれはそろそろ本を読むのに丁度いい季節になる前じゃった。二人がいっぺんに好いとるって言うもんじゃけー。また後日返事をしますって言ったんじゃ」
「あれ?」
敏子とお爺さん二人の会話に噛み合わないところがあった。
「でも、この二人は返事はもらえなかったって言ってたよ」
まさか。と、手を横に振った。
「ちゃんと返事は出しましたよ。ほら、てっちゃんが言い出したじゃないかい。図書室の一番端っこの本に挟んどいてくれって」
「あ。」
思い出したようだ。
しかし普通、そういうことは忘れるのか?
「千沙。とってきてくれるかい?」
「分かった」
高津は一番奥の棚の一番端にある本を持ってきた。
てっちゃんこと眼鏡のお爺さんが中をめくり続けると、確かに封筒がひとつあった。
あれ。このやり方、村上先生もやっていなかったか?
伝統なのか?津高生はいつの時代もやってしまうのか?
そう一人、頭の中で疑問をぶつけていた高津であった。
「ここにあった・・・・・て。敏子ちゃん?」
敏子はその封筒を取り上げると、ぐしゃぐしゃに潰して着物の袖に入れてしまった。
そして、にこりと微笑む。
「昔の事ですよ」
二人は明らかにご不満な様子でお互いを見合っていたが、そんなことはお構いなしに敏子は千沙に本を返す。
「懐かしいもんだね」
「変わらない?」
「いや、いろいろ変わっとるよ。けども、こういう楽しいときの笑顔は変わらないね」
優しい笑顔を見せる。
「楽しいよ」
高津も笑顔で返す。
「それじゃあ私はこのお二人さんと昔話でもしてくるからね」
敏子はお爺さん二人を連れて去って行ってしまった。
「あっという間に行っちゃったね」
委員の子が隣で言う。
「そうだね」
三人が出て行った戸の上の時計に視線が行った。
時間は一時二十三分。
「あ。そろそろ始まる」
そう言うと高津は席を立ちあがった。
「え?どこいくの?」
「ちょっとそこまで」
そう言うと、振り返りもせず図書館を出て行った。
「頑張ってるかい千沙。・・・・てっちゃんによし坊?」
「ばあちゃん!」
「「敏子ちゃん!」」
三人で顔を見合う。
「トシコって、うちのばあちゃんのことだったの?」
「本当に三世じゃったか」
「どうりで似ているはずじゃ」
三人で頷きあう。
「ねぇばあちゃん。この二人に告白されたんでしょ?」
「あら。よう知っとるねぇ」
敏子は思い出すように頷いた。
「そう。あれはそろそろ本を読むのに丁度いい季節になる前じゃった。二人がいっぺんに好いとるって言うもんじゃけー。また後日返事をしますって言ったんじゃ」
「あれ?」
敏子とお爺さん二人の会話に噛み合わないところがあった。
「でも、この二人は返事はもらえなかったって言ってたよ」
まさか。と、手を横に振った。
「ちゃんと返事は出しましたよ。ほら、てっちゃんが言い出したじゃないかい。図書室の一番端っこの本に挟んどいてくれって」
「あ。」
思い出したようだ。
しかし普通、そういうことは忘れるのか?
「千沙。とってきてくれるかい?」
「分かった」
高津は一番奥の棚の一番端にある本を持ってきた。
てっちゃんこと眼鏡のお爺さんが中をめくり続けると、確かに封筒がひとつあった。
あれ。このやり方、村上先生もやっていなかったか?
伝統なのか?津高生はいつの時代もやってしまうのか?
そう一人、頭の中で疑問をぶつけていた高津であった。
「ここにあった・・・・・て。敏子ちゃん?」
敏子はその封筒を取り上げると、ぐしゃぐしゃに潰して着物の袖に入れてしまった。
そして、にこりと微笑む。
「昔の事ですよ」
二人は明らかにご不満な様子でお互いを見合っていたが、そんなことはお構いなしに敏子は千沙に本を返す。
「懐かしいもんだね」
「変わらない?」
「いや、いろいろ変わっとるよ。けども、こういう楽しいときの笑顔は変わらないね」
優しい笑顔を見せる。
「楽しいよ」
高津も笑顔で返す。
「それじゃあ私はこのお二人さんと昔話でもしてくるからね」
敏子はお爺さん二人を連れて去って行ってしまった。
「あっという間に行っちゃったね」
委員の子が隣で言う。
「そうだね」
三人が出て行った戸の上の時計に視線が行った。
時間は一時二十三分。
「あ。そろそろ始まる」
そう言うと高津は席を立ちあがった。
「え?どこいくの?」
「ちょっとそこまで」
そう言うと、振り返りもせず図書館を出て行った。