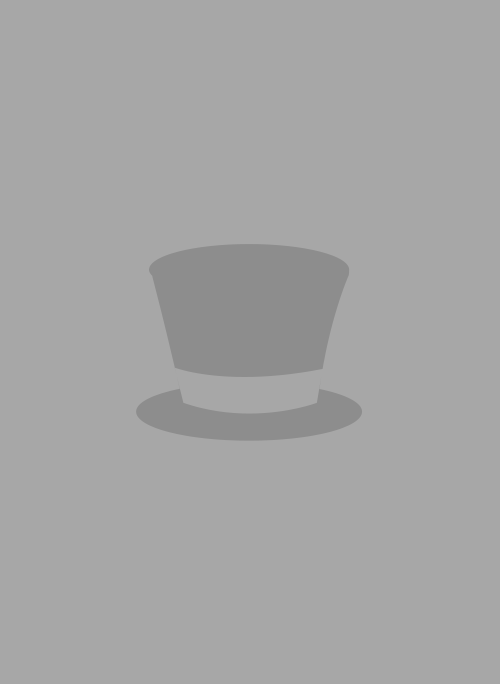「……すっかり暗くなっちゃったね。そろそろ帰らないと」
「……うん」
いつものように、私の肩を叩いて彼は立ち上がった。
私も立ち上がり、清水くんを見る。
足元で子猫が小さく鳴き、その場を去っていった。
「じゃあ……」
改めて顔を見ると、心が痛む。
嫌だ。
別れたくない。
このまま時間が止まってしまえばいい。
それが単なる我が儘に過ぎなくても。
それでもやはり、まだ話していたいと思ってしまう。
「――無理しなくていいと思うけど」
頭から降ってくる、優しい言葉。
止めて。今はそれを言わないで。
「オレだって寂しいし。泣きたいなら、我慢する必要無いんじゃない?」
「で、でも、最後くらい、笑顔でって決めたのに……」
「オレは、君が無理して笑顔作ってる方が嫌だ」
お願いだから。
そんなこと言わないでよ。
「清水くん、私……」
「……うん」
胸が締め付けられ、視界が霞んでくる。
涙が溢れ、頬を伝って落ちていく。
それと同時に、気持ちまで溢れ出てきた。
暗くて顔がよく見えないせいもあったのかもしれない。
私は、泣きながら彼の胸に飛び込んだ。