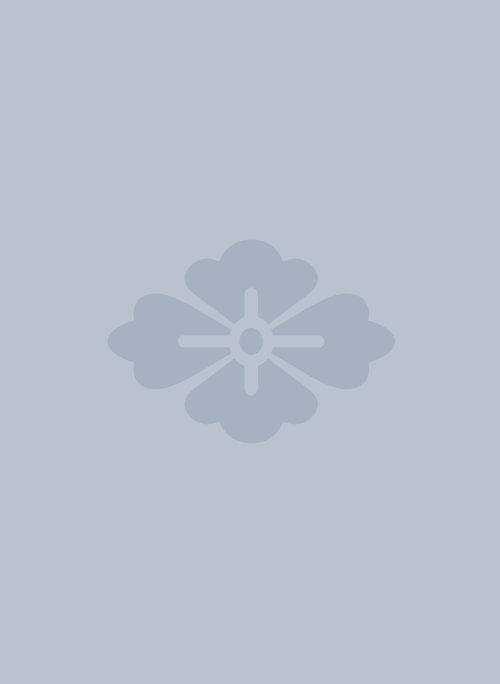まるでそこに存在することが当然のように。
(アダム、か…)
赤く辺りを染める夕焼けの下で笑う彼を見ながら、もう一度その名前を心の中で呟いた。
それはとても幻想的な響きを持っていて。
純粋にぴったりだな、と思う。
隣に座る彼には似合う名前。
その存在を引き立てる名前。
(…だけど…)
だけど、私には絶対に手の届かない名前。
彼に似合うそれは私には眩しすぎる響き。
世界が違うとさえ思ってしまう。
それでも、隣で笑う彼の口元があまりに嬉しそうだったから。
「…花子」
そんな彼に誘われるようについ口を開いた私。
「花子っていうの」
口に出した名前は珍しくもなければ特別なものでもない。
謂うならば"平凡"。
けれどそんな名前がぴったりだと思った。