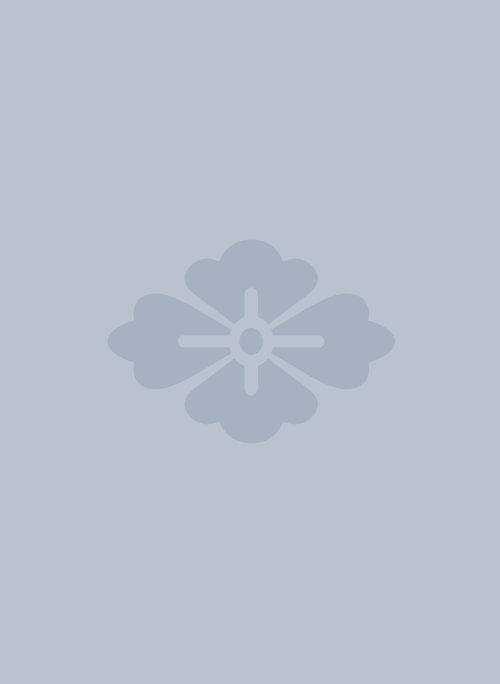呼吸の仕方が、わかるような気がしたんだ。
「…歌がね、上手く歌えなくて。自分の声が大っ嫌いなんだ」
静かな空気に揺れる切羽詰まった声。
吐き出したのは、一人で抱えるには大きくなりすぎた秘密。
それを目の前の少女にぶつけた。
どうしてこんなことを話しているのだろうと、頭の中の冷静な自分が問い掛ける。
相手はまだ小さな子どもだというのに。
しかし、彼女から目を離すことは出来ない。
気付いていた。
彼女の綺麗な瞳に映る自分がどうしようもなく不安そうな顔をしていることに。
見たことのないくらい情けない顔をしていることに。
(たす、けて)
そしてそこに映る俺は、すがるように彼女を真っ直ぐ見つめていた。