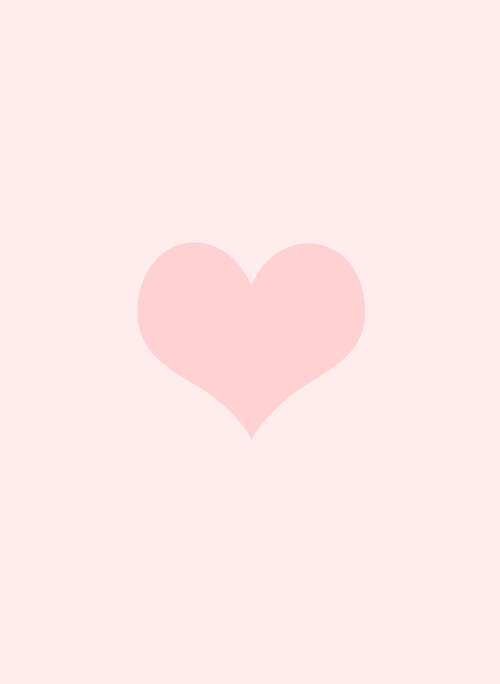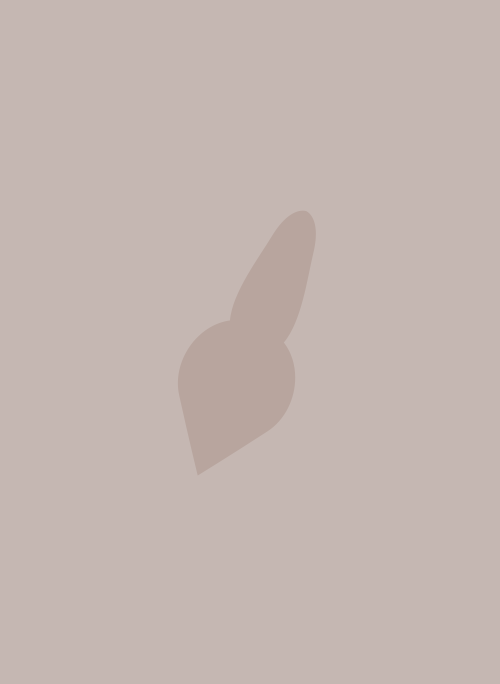それからしばらく経った時だった。
「…うん?」
そう呟いたかと思うと、先生が目を開いた。
視線がバチッとぶつかる。
「水橋…って、お前どうしていきなり飛び出すんだよ!心配したんだぞ!!」
ここまで感情をむき出しにする先生を、私は初めて見た。
「ごめんなさい。でもショックで…」
「とにかく、無事で良かった…」
そう言って安堵のため息をつく先生。
心底嬉しいのだが、私には疑問が1つあった。
「先生、1ついいですか?」
「ん?」
「どうして私の隣で寝ていたんですか?」
「ああ、それはお前があまりにも気持ちよさそうに寝ているから起こさないで待っていたんだけど、結局俺も寝ちゃったんだよ」
そういうことだったのか、と納得する私と複雑な思いの私がいた。
今、目の前にいる人は母の婚約者だというのに、私は一体何を複雑に思う必要があるのだろう。
よほど険しい顔をしていたらしく、先生が訝しげに聞いてきた。
「水橋?」
「いや、なんでもないです」
「それならいいけど。じゃ、そろそろ帰るか」
「はい」
月明かりの下、私達は並んで夜の道を歩いた。
ふと、顔を見上げると黒をバックに銀色の筋が一瞬だけ走ったのが見えた。
「きれい…」
それは涙が出そうなくらいに美しかった。
聖夜に光ったものはきらびやかなイルミネーションでもキャンドルの揺らめく炎でもなく、流れ星と私の涙だった。
「…うん?」
そう呟いたかと思うと、先生が目を開いた。
視線がバチッとぶつかる。
「水橋…って、お前どうしていきなり飛び出すんだよ!心配したんだぞ!!」
ここまで感情をむき出しにする先生を、私は初めて見た。
「ごめんなさい。でもショックで…」
「とにかく、無事で良かった…」
そう言って安堵のため息をつく先生。
心底嬉しいのだが、私には疑問が1つあった。
「先生、1ついいですか?」
「ん?」
「どうして私の隣で寝ていたんですか?」
「ああ、それはお前があまりにも気持ちよさそうに寝ているから起こさないで待っていたんだけど、結局俺も寝ちゃったんだよ」
そういうことだったのか、と納得する私と複雑な思いの私がいた。
今、目の前にいる人は母の婚約者だというのに、私は一体何を複雑に思う必要があるのだろう。
よほど険しい顔をしていたらしく、先生が訝しげに聞いてきた。
「水橋?」
「いや、なんでもないです」
「それならいいけど。じゃ、そろそろ帰るか」
「はい」
月明かりの下、私達は並んで夜の道を歩いた。
ふと、顔を見上げると黒をバックに銀色の筋が一瞬だけ走ったのが見えた。
「きれい…」
それは涙が出そうなくらいに美しかった。
聖夜に光ったものはきらびやかなイルミネーションでもキャンドルの揺らめく炎でもなく、流れ星と私の涙だった。