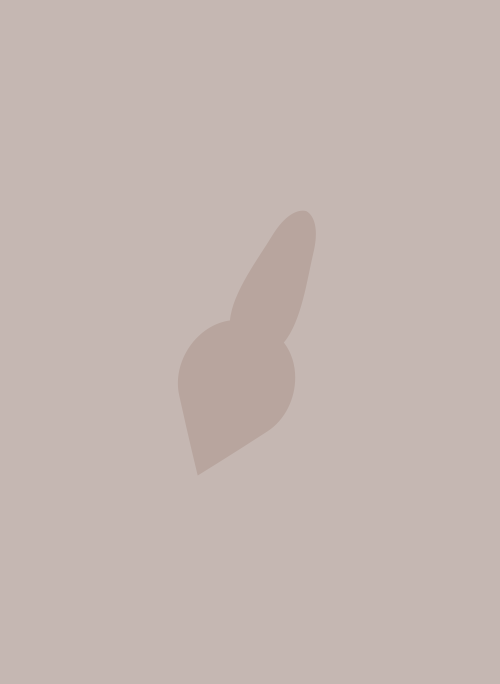「何?」
「わたしを恨めしいと思わないの?」
その目は真剣だった。
「思うわけないじゃない」
本心だった。
ショックだったけど恨めしいだなんて思っていない。
「だってあなたの夫を好きなのよ?わたしがあなただったら、きっと狂ってしまう」
「でも私は、失いたくない」
「え?」
私の言葉に母は顔を上げる。
「大切な母親だから失いたくない。だからこんなことで死ぬとか簡単に言わないで」
私の勢いに、母は驚いた顔をした。
「もしあなたが命を落としたら、母さんはこの苦しみから逃れられるかもしれない。だけど、残された先生や私達はどうなるの?単なる自己満足じゃない。私はこんなことで死なれた方がよっぽど恨めしく思うよ」
「流星…」
「確かに先生が母さんを抱きしめているのを見た時は頭の中が真っ白になるくらいショックだった。でも、母さんがそんなこと言うなんてもっとショックだった」
気付けば、こんなにもキツい言い方をしたのは久々だ。
「私は、いつもの明るくて優しい母さんが好きだから」
ふいに母の目から涙が落ちた。
私まで泣きたくなる。
「だから冗談でも死ぬとか言うのはやめて。人生は1度きりだよ。取り返しなんてつかないんだから。死んだら全部そこで終わっちゃうんだからね」
どこかの安っぽい青春ドラマみたいなセリフだが、この時の私は大まじめだった。
「ごめんね…流星。わたし、母親失格だわ」
「失格じゃないよ。母さん、まだまだこれからでしょ?」
「…ええ。だってまだ29歳だもの」
出来るだけ穏やかに言うと、まだ震えながらもそんな返事が返ってくる。
「嘘ばっかり。もう44歳でしょ」
いつのまにか涙は乾き、私達からは笑いがこぼれていた。
「人生は1度きり。だから取り返しがつかない、か」
母はぽつりと呟く。
「いや、あの、安っぽいセリフ失礼しました」
なんか急に恥ずかしくなる。
「ううん、違うの」
フッと優雅に目を細め、母は笑った。
「あんなに小さくて泣いてばかりだったあなたが…本当に大きくなったわね、流星」
その言葉が照れくさくてフイと目を逸らす。
空を見ると、グレーの巨大な雲は追い風に流され始めていた。
「わたしを恨めしいと思わないの?」
その目は真剣だった。
「思うわけないじゃない」
本心だった。
ショックだったけど恨めしいだなんて思っていない。
「だってあなたの夫を好きなのよ?わたしがあなただったら、きっと狂ってしまう」
「でも私は、失いたくない」
「え?」
私の言葉に母は顔を上げる。
「大切な母親だから失いたくない。だからこんなことで死ぬとか簡単に言わないで」
私の勢いに、母は驚いた顔をした。
「もしあなたが命を落としたら、母さんはこの苦しみから逃れられるかもしれない。だけど、残された先生や私達はどうなるの?単なる自己満足じゃない。私はこんなことで死なれた方がよっぽど恨めしく思うよ」
「流星…」
「確かに先生が母さんを抱きしめているのを見た時は頭の中が真っ白になるくらいショックだった。でも、母さんがそんなこと言うなんてもっとショックだった」
気付けば、こんなにもキツい言い方をしたのは久々だ。
「私は、いつもの明るくて優しい母さんが好きだから」
ふいに母の目から涙が落ちた。
私まで泣きたくなる。
「だから冗談でも死ぬとか言うのはやめて。人生は1度きりだよ。取り返しなんてつかないんだから。死んだら全部そこで終わっちゃうんだからね」
どこかの安っぽい青春ドラマみたいなセリフだが、この時の私は大まじめだった。
「ごめんね…流星。わたし、母親失格だわ」
「失格じゃないよ。母さん、まだまだこれからでしょ?」
「…ええ。だってまだ29歳だもの」
出来るだけ穏やかに言うと、まだ震えながらもそんな返事が返ってくる。
「嘘ばっかり。もう44歳でしょ」
いつのまにか涙は乾き、私達からは笑いがこぼれていた。
「人生は1度きり。だから取り返しがつかない、か」
母はぽつりと呟く。
「いや、あの、安っぽいセリフ失礼しました」
なんか急に恥ずかしくなる。
「ううん、違うの」
フッと優雅に目を細め、母は笑った。
「あんなに小さくて泣いてばかりだったあなたが…本当に大きくなったわね、流星」
その言葉が照れくさくてフイと目を逸らす。
空を見ると、グレーの巨大な雲は追い風に流され始めていた。