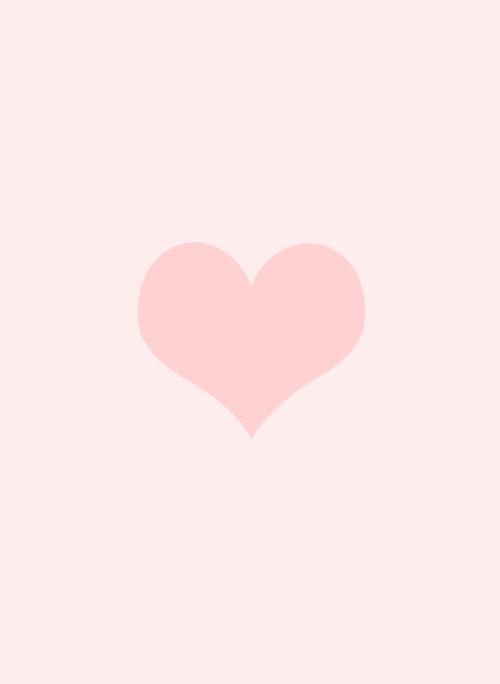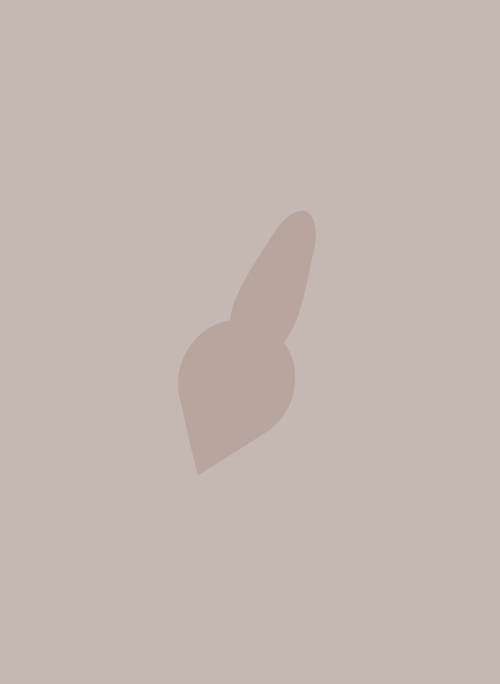パタッ、パタッ。
洗面台に雫が落ちる。
それは蛇口から滴る水ではなく、わたしの涙だ。
視界はすでに靄に覆われてしまったかのように、すべてのものの輪郭がはっきりしていなかった。
苦しい。
この状況をなんとか打開したいのに。
流星を裏切りたくないのに。
皐示さんが好きという気持ちが溢れるだけ。
嫌なわたし。
ガチャ。
誰かがトイレにやって来た。
泣き顔を見られたくなくて、鏡を見る。
そこに映っていたのは今、一番会ってはいけないような気がしていた人だった。
「な…流星」
彼女はわたしに気付くとはっとしたような顔をしたが、悲しみの色が満ちた表情で何も言わずに出ていってしまった。
その態度を見て、わたしは悟った。
きっと、流星は見てしまったのだろう。
皐示さんがわたしを抱きしめているちょうどその瞬間を。
「どんな顔をして会えばいいの…?」
流星にも、皐示さんにも。
わたしの行き場は完全になくなってしまったように感じられた。
1人ぼっちのトイレ。
まるで誰もいない世界にいるみたい。
寂しさと苦しさのあまり、頭がおかしくなってしまいそうだった。
洗面台に雫が落ちる。
それは蛇口から滴る水ではなく、わたしの涙だ。
視界はすでに靄に覆われてしまったかのように、すべてのものの輪郭がはっきりしていなかった。
苦しい。
この状況をなんとか打開したいのに。
流星を裏切りたくないのに。
皐示さんが好きという気持ちが溢れるだけ。
嫌なわたし。
ガチャ。
誰かがトイレにやって来た。
泣き顔を見られたくなくて、鏡を見る。
そこに映っていたのは今、一番会ってはいけないような気がしていた人だった。
「な…流星」
彼女はわたしに気付くとはっとしたような顔をしたが、悲しみの色が満ちた表情で何も言わずに出ていってしまった。
その態度を見て、わたしは悟った。
きっと、流星は見てしまったのだろう。
皐示さんがわたしを抱きしめているちょうどその瞬間を。
「どんな顔をして会えばいいの…?」
流星にも、皐示さんにも。
わたしの行き場は完全になくなってしまったように感じられた。
1人ぼっちのトイレ。
まるで誰もいない世界にいるみたい。
寂しさと苦しさのあまり、頭がおかしくなってしまいそうだった。