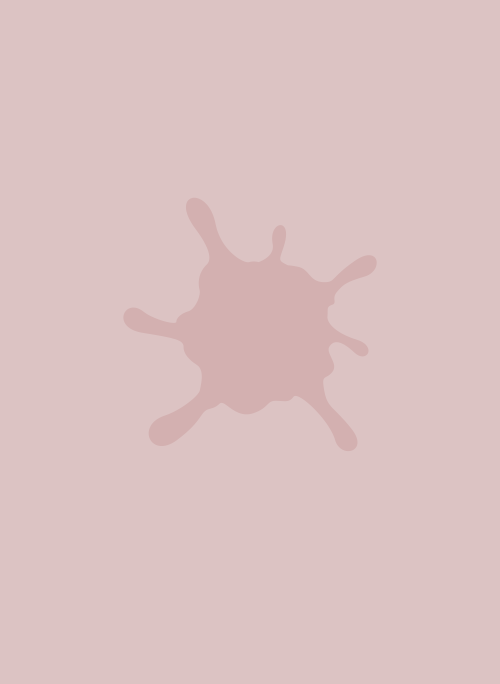「よ、良かったって?」
破裂しそうな心臓を無理やり抑えつけるかのようにして、麻友に聞いて見た。
「そ、それは・・・」
恥じらいと言おうか、そんな表情が伺い知れた。そこで麻友の言葉を遮った。
「いい。何も言わなくていい」
目の前にいるのは老婆だ。けれども麻友だ。しかし、優の知っている麻友ではない。そして、今の麻友に未来は見えなかった。つまり、想いを伝えなかったなら、伝えられないまま終わってしまう。
それだけは嫌だった。
「お、俺・・・麻友が・・・麻友の事が・・・好きだ。大好きだ。世界中の誰よりも好きだ」
叫ぶかのように伝えた。
「麻友も優が大好きなり・・・」
枯れるような声だった。端から見ればおかしな光景だろう。老婆と男子高校生が愛の言葉を交わし合っているのだ。でも、そんなのは気にならない。優はどんな姿になったとしても、麻友が大好きでしかたないし、麻友もそうだ。こんなになっても優への想いは消えない。だからこそ美しかった。それを讃えたかった。
破裂しそうな心臓を無理やり抑えつけるかのようにして、麻友に聞いて見た。
「そ、それは・・・」
恥じらいと言おうか、そんな表情が伺い知れた。そこで麻友の言葉を遮った。
「いい。何も言わなくていい」
目の前にいるのは老婆だ。けれども麻友だ。しかし、優の知っている麻友ではない。そして、今の麻友に未来は見えなかった。つまり、想いを伝えなかったなら、伝えられないまま終わってしまう。
それだけは嫌だった。
「お、俺・・・麻友が・・・麻友の事が・・・好きだ。大好きだ。世界中の誰よりも好きだ」
叫ぶかのように伝えた。
「麻友も優が大好きなり・・・」
枯れるような声だった。端から見ればおかしな光景だろう。老婆と男子高校生が愛の言葉を交わし合っているのだ。でも、そんなのは気にならない。優はどんな姿になったとしても、麻友が大好きでしかたないし、麻友もそうだ。こんなになっても優への想いは消えない。だからこそ美しかった。それを讃えたかった。