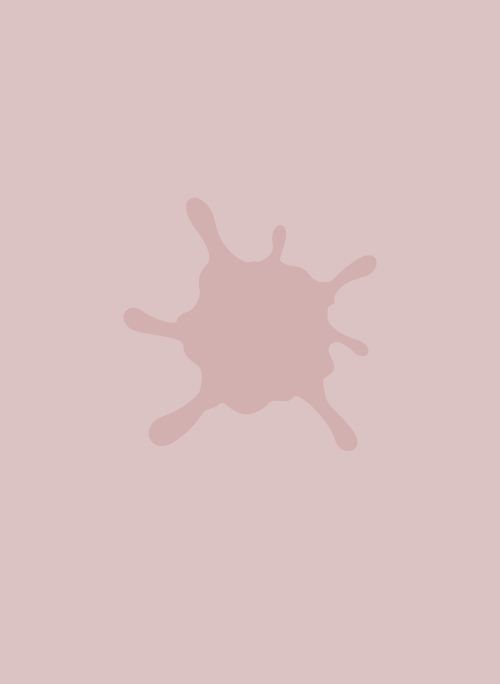怖くなった私は慌てて電話を切り、そしてそこで、目が覚めた。
肩まで布団をかけてベッドに横たわる体は、嫌な汗でじっとりと濡れていた。
今までの恐怖は夢だったのだと分かって、とても安心したのを今でも覚えている。
しかし、ホッとしたのも束の間、私はある重要なことに気づいてしまった。
母親の携帯は、姉が生前使っていたものだったことに。
Hが電話をかけたのはきっと、私の母親ではなく、姉だった。
しかし、Hは姉が死んだのを知っているし、彼のセリフからも姉が死んだことは分かっていたはず。
なら一体なぜ、夢の中のHは死んだ姉に向かって喋り続けたのか。
そして、Hと姉には一体、どんな接点があったのか。
──僕が××××って言ったから死んじゃったの?
Hは姉に、一体何と言ったのだろう。
…否、
そもそもあれは、本当にHだったのだろうか。
電話の向こうの少年は、一切名乗らなかったではないか。