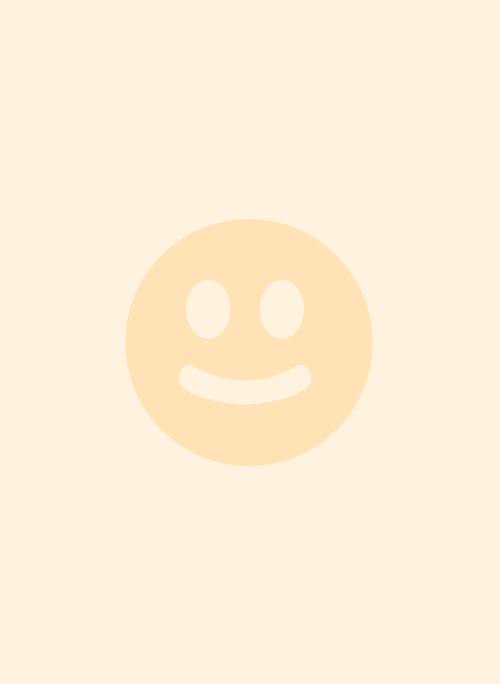「…お前さ」
「ん?」
口の中が気持ち悪くて、ペットボトルのお茶を飲み込む。
「お前はどうなんだよ?」
「どうって…」
「…だからっ!」
イキナリ大きな声を出すから、少しびっくりした。
「好きな奴…とか、いないのかよ?」
「いるよ?」
私の答えがあまりに即答だったからか、三河が目をパチクリさせた。
「何、びっくり?」
「お?おぉ…」
何なの?
だけどそれ以上、
三河がその事を突っ込んでくる事も
他の話題が出る事も無く、
ぎこちない雰囲気は、昼休み終了まで続いた。
ねぇ三河…
この時、もっとあんたに話せば良かった?
そしたら何か変わったのかな?
気づけなくて、ごめん。
あんたが抱えていたその痛みは誰よりも、
私が一番知ってたはずなのに。