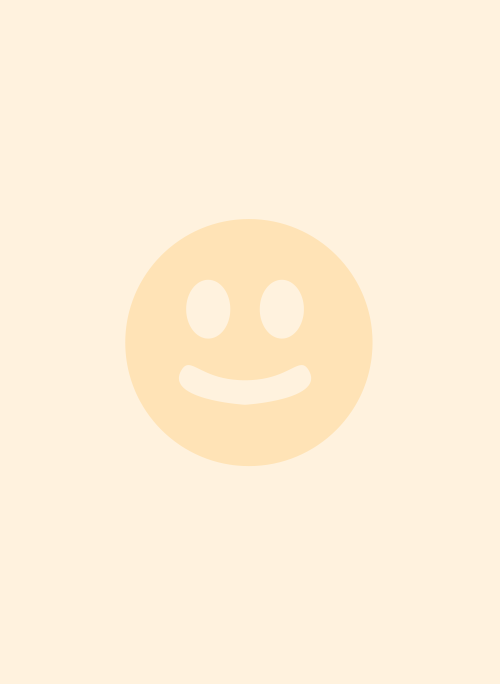「俺はね、明里。」
「いやだ。お前の考えなんて聞きたくない。」
きっとこいつの話を聞いてしまったら、あたしはきっと、頷いてしまう。
またやりたいと、また一緒にやろうと言われてしまえば、こいつを理由にお笑いの世界へ逆戻りしてしまう。
そんなの、ごめんだ。
「ダメだよ。ちゃんと聞いて。」
あたし、こいつの真剣な目、苦手なんだよね。
「俺はさ、なんでも良かったんだ。」
特に、こんな風に絶対にそらさない、意思の強い目。
「…もし誘われた時にお笑いじゃなくて手品をやろうって言われてれば手品をやったと思うし、劇をやろうって言われてれば劇の練習をしたと思う。
面白そうだからやる。最初は、それだけだったんだ。」
「でも、お前、やりたいと思ったって…」
「うん。純粋に、お笑いって楽しいなって思っちゃったんだ。
それにさ、俺が頑張るとなんだかんだ言いつつ明里も一緒に付き合ってくれるだろ?それが、すげー嬉しくて。」
照れたようなハニカミ。
確かに、今まで兄貴であるこいつをバカにはしていたが、ここまで毎日密に関わることはなかったかもしれない。
「俺も一応兄貴である以上、妹には構ってあげたいし、甘えてもらいたいのよ。」