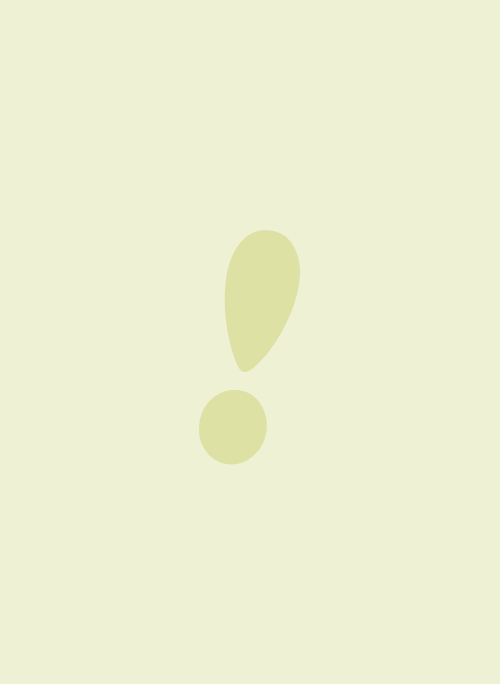「データがないって…」
「君は1980年代後半、若しくは90年代に生まれた。間違いないかい?」
「ええ。1993年11月20日が、私の生まれた日です」
お爺さんはもう一度外に出て戻ってくると、首を横に振った。
「やっぱり、私のような人のデータなんて、残ってないんじゃないんでしょうか?」
「いや、あるはずなんだ。だって、君は2012年の時点で19歳だということだろう?その辺データの回収は随分前に済んでいるんだ」
「だったらどうして…」
頭を抱えるお爺さんはそのまま俯いてしまった。
「あの、聞いてもいいですか?」
顔を上げ、お爺さんは一度瞼を閉じて返事をする。
「私はこうして2012年から2055年までのことを知ったわけですけど、例えば私が戻れたとして、未来を変えるような行動をした場合、そういうのって、違法にならないんですか?」
「それは安心していい。正式な形をとって戻る場合、君がここで見た記憶は消される。心配はいらないよ」
「ああ、そうなんですか」
安心すると同時に、どこかそれも嫌だと思った自分に嫌気がさす。
どの方向に向かっても、常に悩みが付き纏い、開放とは程遠い現実へ投げ出されるばかりだ。