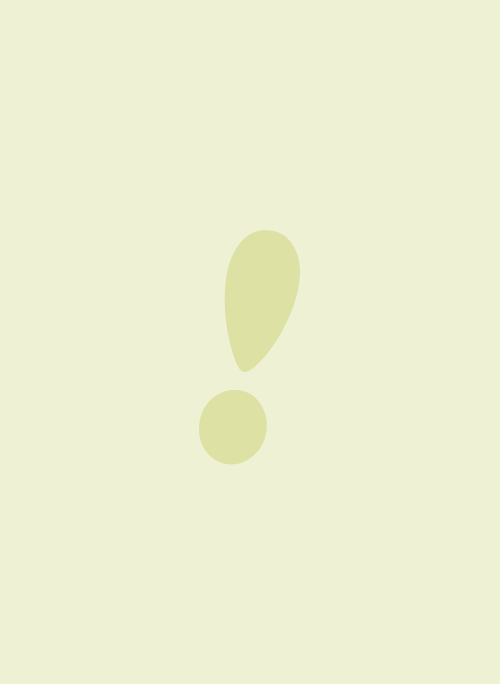「いえ、本当にいないんです。私の両親は私が幼い時に二人とも事故で亡くなって。おばあちゃんや、親戚たちも私を煙たがって施設に入れたくらいなんです。友達だって、そう呼べる人も、碌にいませんでした。好きな人にも振られて、どちかと言えば、2012年に必要ない人間ナンバー1だったかも」
情けない。
今の自分がどれほど哀れな笑みを浮かべていることか。
「そんなことはない」
力強く発せられたお爺さんの声で、無理に上げていた口角が緩んだ。
「現に君は今ここにいる。どんな理由であれ、君を必要としている人がいるんだ。尤も、私もその一人なんだけどね」
「…お爺さんが?」
「自分の手で傷つけてしまった人の傷を完治させることがどれ程困難なことかわかっている。それが、不可能に限りなく近いということも。けれど、その傷を少しでも癒したい、浅くしたい。そう願って、そのためだけに生きてきた。こんな老いぼれにでも出来ることはまだあるはずだと信じてね。そして、今日、私は君に出逢った。自己満足に過ぎないことはわかっている。君に許しを得たいわけじゃないんだ。ただ、手伝わせてくれないだろうか?君が、過去に戻る手伝いを、どうか」
そう言うとお爺さんは跪き、床に白い髪を着けるように低く頭を下げた。