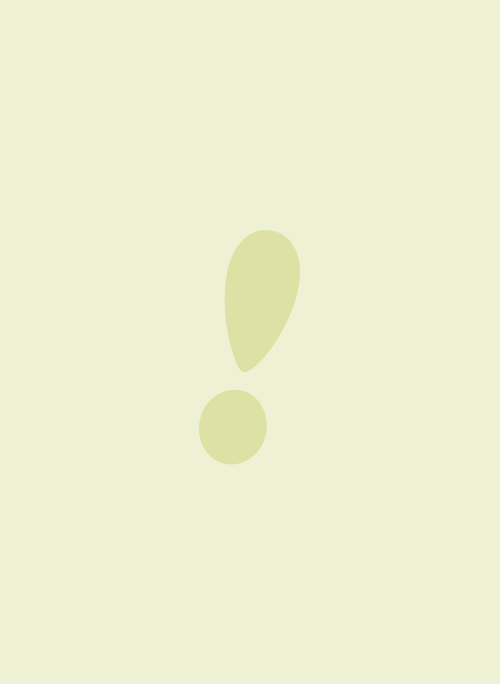それから私はまた梓を守るため、片時も離れようとしなかった。
勿論それはただの口実で、本当は傍にいたかっただけだったのだが。
高校を卒業していく梓の制服のボタンを、どうか誰にも奪われませんように。
そんな心配をするほど梓に人気があったわけではないが、私は先輩だらけの中、卒業式の日も、校門前で梓を待っていた。
けれどその日、同級生に囲まれていた梓を見た時、制服のボタンがひとつなくなっていることに気づいた。
気づかないふりをして、言いたい台詞を呑み込んで、そうして恰も今気づいたかのように驚いて見せた。
「よかったね、貰ってくれる人がいて」
そんな風に強がって笑う私は、生まれつきの強情なのかもしれない。
「っていうか、ごめんね、ずっと私、居て」
長い沈黙は破られないまま。梓の横顔に、私は何を期待していたのだろうか。
大学生になると大学に着いて行くわけにもいかず、私は何もない平凡で、退屈な高校生活を淡々と送っていた。
施設に帰っても、施設を出てしまった梓は、もうそこにいない。
守ってあげるから。
気付けば、そんな口実も通用しない歳になっていた。