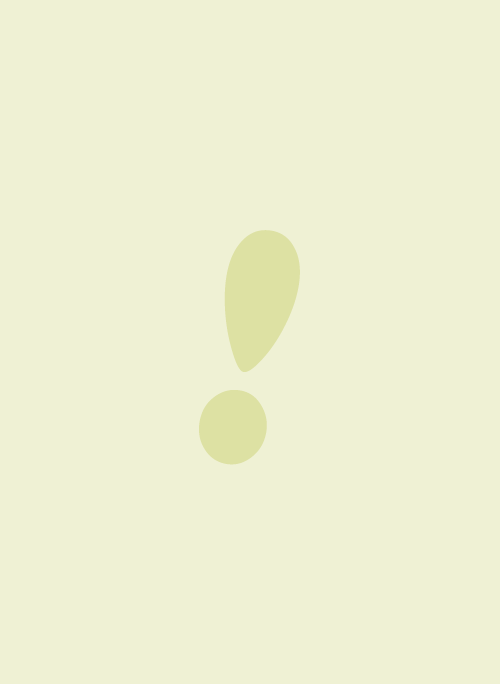私は中学へ入学し、梓は3年生へと進級した。
大人に向かう一歩踏み出すと同時に、私は大きな戸惑いを得た。
すべてが逆戻りしたようだった。
思春期という疎ましい時期に入ると、梓は口を効いてくれなくなった。
虐められたことも隠して、校門前で待つ私から逃げるように一人で下校する事が当たり前だった。
私の誓いが、こんなにも脆い物っだったのかと思い知らされるようだった。
それが、ただの独りよがりであったことに、初めて気づいたのだ。
自分を必要とする人がいなくなってしまう。
そんな不安に襲われた。
中央廊下で見かけた梓は、友達であろう男の子達と何か話していた。
よかった、梓はちゃんと友達が出来たんだ。
思わず綻んでいると視線が合致する。
しかし梓が微笑むことはない。
もはやそれは幻覚だったのかもしれないというほど短い瞬間だった。
チャイムが鳴る。
騒々しく教室に戻る生徒の渦に混じり、その姿を見失った。
「衣奈ー!次体育だよー!」
友人の声に元気よく返事をした。
「あ、うん先行っててー!」
誰もいなくなった廊下の真ん中で、私は頬に手をかざした。
その存在に気づいた瞬間、堪えていたものが溢れ出すように次々と頬を伝った。
そうして私は漸く気づく。
ああ、私はこの人の事が好きなのだと。