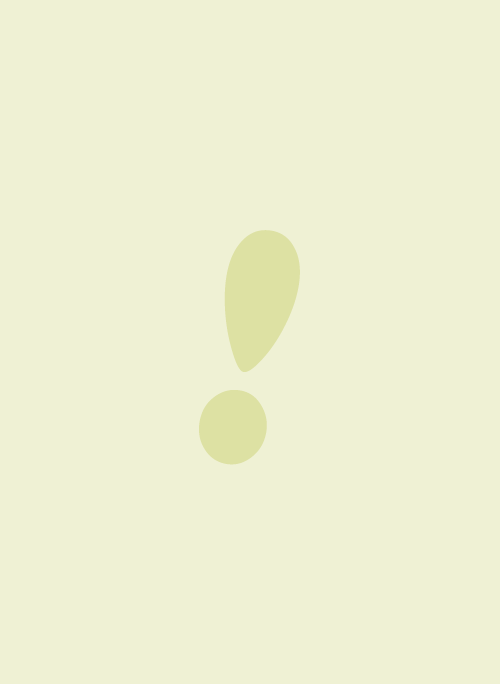私はその手を咄嗟に掴み、握りしめた。
少し離れた大人たちに、幼馴染に、気づかれないように。
私がいるよ。
恥ずかしくて、口にすることはなかったが、梓はそうすると堪えていた涙を頬に伝わせた。
施設に来たときは、触れることすら許してくれなかった。
しかしその時、梓は私の手を強く、何か言いたげに握り返した。
そして私はそれを小さな手一杯に受け止めたくて、また握り返す。
木枯らしの吹く帰り道、まだ温もりを忘れられない私の右手だけがぽかぽかとしていた気がする。
どうして人は死ぬの?
施設の玄関で、突拍子もなく幼い子が施設の先生に訪ねていた。
「人はいつか死ぬんだよ」
先生の説明は最もで、もちろんそれを説明されなくても私たちはそれを知っている。
だけど、その最もな説明に納得するにはまだ若すぎるわけで。
死への恐怖、未知の死後への恐怖。
それが先走り不安になることを、大人たちは忘れてしまったのだろうか。
振り返った視界に映った梓の面持ちを見て、私はすかさず先生の説明を遮った。
「私は死なない」
そうねと私を宥めるような声で言った先生が誰であったのかなどもう、忘れてしまった。
「私は絶対死なないから!」
顔を合わせた梓は驚いた様子でこちらを見ていた。
想像も出来ない程遠い未来。
どんなことがあっても、いつでも必ず、私は梓を守るよ。
そう誓うように、私は梓を見つめた。