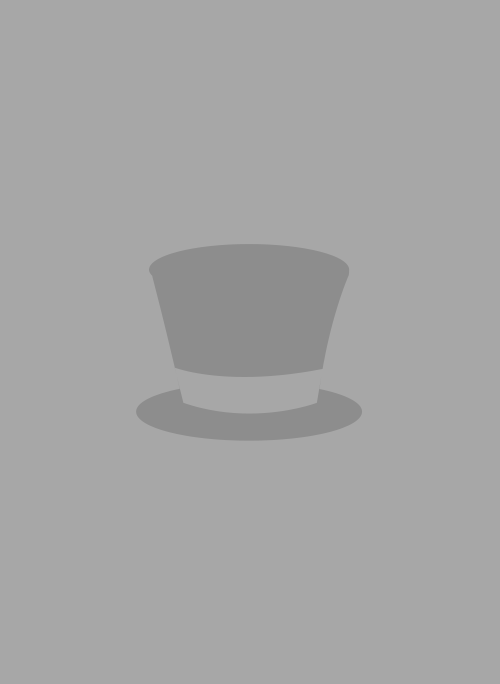圭くんに子ども扱いをされることを今まで極端に嫌っていた。
子供だからって馬鹿にされたら、やけになって言い返したり、突っかかったりした。
だけど、たかが四歳しか変わらないのにと思っていたその年齢の差は、思ったよりも大きい。
それを、圭くんと付き合っていく中で、ひしひしと感じていた。
どんなにがんばったところで、年齢差なんて埋まらない。
偶にクラスメイトの中には、自分が高校生であることを武器にしている子もいるけど、あたしにはそんなにいいようには考えられないし。
何より、それをどう武器にしていいのかもわからない。
使い道を全く知らないあたしにとっては、何の意味も持たない事実で――…
堂々と、同じ学校で圭くんと肩を並べられるあの人たちのことが、あたしにはとてもうらやましく思えた。
そんなことを思っていると、自分の頭の上にポンと温かいぬくもりを置かれた。
それが、圭くんの手だとすぐにわかったあたしは顔を上げて、圭くんを見つめる。
運転中の圭くんは、前を向いたままだったけど、その表情はうれしそうにあたしには見えた。
「馬鹿だな、お前。そんなこと気にしてたのか?」
「そんなことって、あたしには!」
「『重要なこと』ってか? それこそ、俺からしたら馬鹿らしいよ。お前が高校生だってことは、俺は嫌って言うほど知ってるっての。それを承知で、俺はお前と付き合ってんだぞ?」
「でも…、圭くんの周りには綺麗な大人の女性がたくさんいて……」
「お前よりも俺の方が心配」
「・・・・・?」