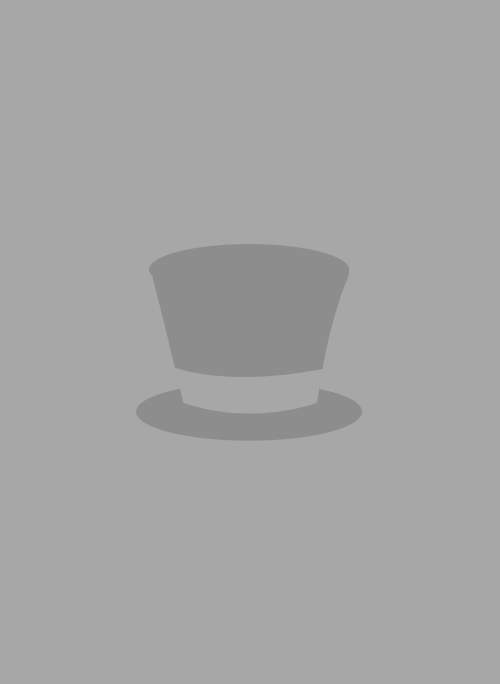「あの人、本当に圭くんに彼女がいるってわかってたのかな?」
回りくどく言っても、伝わらないかもしれないから、あたしは直球で圭くんに聞くと、圭くんは「言ったんだから、当たり前だろ?」って、あっさりと肯定する。
あっさりと、それも圭くんにそう言われると、あたしはそれ以上何も言うことはできなくて――…
でも、なんとなくあの時に見せたあの人の表情や行動が、あたしに不安な気持ちを残す。
告白して断られても、あの人の中での圭くんへの想いは消えていない。
それだけは確実に言える。
―――もしかしたら、彼女は信じていなかったのかもしれない。
圭くんに彼女がいると言われて断られても。
それは断るための方便であって、本当はいないと思っていたのかも――…
―――だってね…。
あたしもそれほど詳しくは知らないけど、圭くんってあたしと付き合う前までは、女性とは褒められたお付き合いをしてこなかったみたいだし――…
あっ!
もしかして、あの女性だけじゃなく、研究室にいた男の人たちも驚いていたのは、そういう圭くんの過去のことを知ってたから………。
特定の彼女を作ったことに驚いていたとか――…
そこまで考え付いたところで、無性にムカついてきた。
そりゃさ、過去は今更どうすることもできないし、そんな圭くんの過去を知ってて付き合ってるから、今更そのことで圭くんを責める気にはならない。
でも…。
でもだよ?
そんな圭くんの過去のいい加減な付き合いのせいで、どうせ、あたしとも長続きしないだろうと思われてたら――…
「超、ムカつく」
「ぁあ!?」
つい、あまりのムカつきで声に出してしまっていた。
そして、その声はもちろんすぐ横に座っていた圭くんの耳にもばっちりと入ってしまったわけで――…
「ムカつくって、何がだよ」
ジロリと横目で睨まれた。