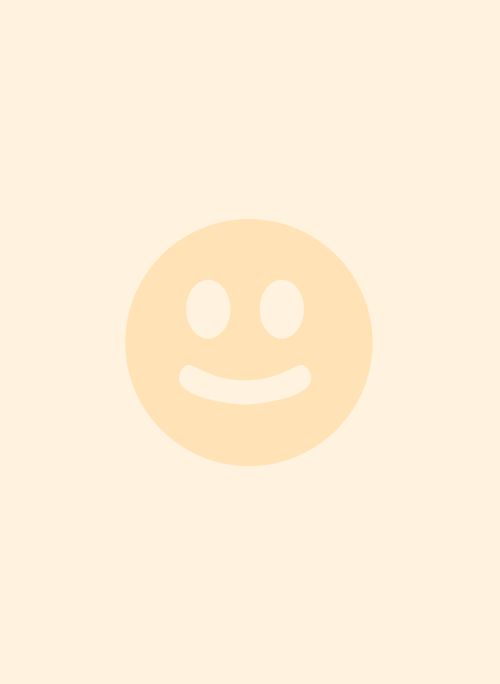その夜。
いつものように剣道着を纏い、愛刀の『死門逝風(しもんゆきかぜ)』片手に歩いていた俺は、工事現場へと入り込む。
鉄骨剥き出し、セメント袋は山積みになり、足場を組んであるようなビルの建設現場。
静寂に包まれたこの場に足を踏み入れた理由は他でもない。
ここなら存分に仕合えるだろうから。
「そうだろう?娘」
俺は振り返る。
…白い制服、長い黒髪。
凛とした気配を纏った女子が、黒き宝石の如き瞳でこちらを見据えていた。
いつものように剣道着を纏い、愛刀の『死門逝風(しもんゆきかぜ)』片手に歩いていた俺は、工事現場へと入り込む。
鉄骨剥き出し、セメント袋は山積みになり、足場を組んであるようなビルの建設現場。
静寂に包まれたこの場に足を踏み入れた理由は他でもない。
ここなら存分に仕合えるだろうから。
「そうだろう?娘」
俺は振り返る。
…白い制服、長い黒髪。
凛とした気配を纏った女子が、黒き宝石の如き瞳でこちらを見据えていた。