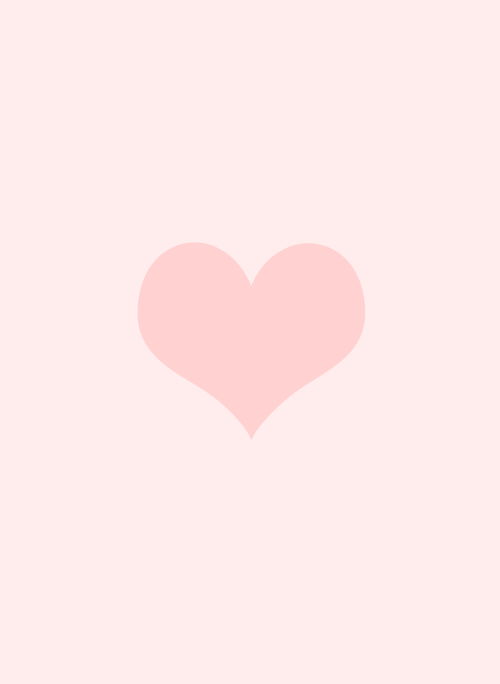千は当然、帝が何に対して気を悪くしているのか気づいていたが、あえて触れずに話を続ける。
「ねぇ、毬?
私、先日のお礼をしたいと思ってここに呼んだのよ」
「――お礼?」
「そう」
千は自信たっぷりの笑みをその口元に浮かべる。
「龍星と、結婚したいと思わない?」
――え、と、帝と毬は目を丸くした。
龍星は得意の無表情で冷静さを保っているので、その心の内はほかの人には伝わらない。
「どう?」
毬は相変わらず顔を見せないので、千は改めて問う。
「毬の気持ちがないなら、この話はすすめることはできないわね」
と、ひとりごちても見せる。
「結婚――したい、です」
毬は、小さな声で、でもはっきりとそう言った。
「あら、いい子」
千の口調はまるで、弟子を褒める師匠のようだ。
「それなら、この機に乗じるのが一番よ。
お父様も、右大臣家がごたごたしている今、目立つことがしたいでしょうし、『私』や家を救ってくれた龍星にも頭があがらないはずよ。
だから、右大臣の喪があけるのを待ってすぐに裳着と所顕し(ところあらわし)を行うことを提案するわ。
――帝のお名前で」
「ねぇ、毬?
私、先日のお礼をしたいと思ってここに呼んだのよ」
「――お礼?」
「そう」
千は自信たっぷりの笑みをその口元に浮かべる。
「龍星と、結婚したいと思わない?」
――え、と、帝と毬は目を丸くした。
龍星は得意の無表情で冷静さを保っているので、その心の内はほかの人には伝わらない。
「どう?」
毬は相変わらず顔を見せないので、千は改めて問う。
「毬の気持ちがないなら、この話はすすめることはできないわね」
と、ひとりごちても見せる。
「結婚――したい、です」
毬は、小さな声で、でもはっきりとそう言った。
「あら、いい子」
千の口調はまるで、弟子を褒める師匠のようだ。
「それなら、この機に乗じるのが一番よ。
お父様も、右大臣家がごたごたしている今、目立つことがしたいでしょうし、『私』や家を救ってくれた龍星にも頭があがらないはずよ。
だから、右大臣の喪があけるのを待ってすぐに裳着と所顕し(ところあらわし)を行うことを提案するわ。
――帝のお名前で」