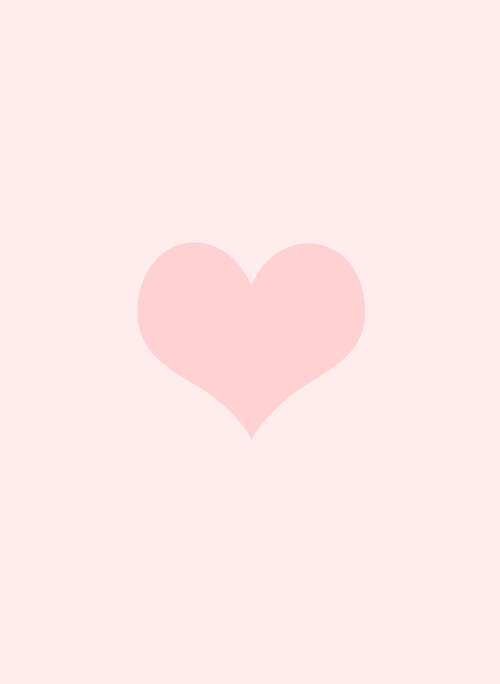翌日、二人は弘徽殿へと向かった。
「龍星を出仕させるためには、毬を呼ぶほか手だてがないのか」
帝は開口一番、不機嫌にそう言った。
千はおなかがかなり出てきたものの、すこぶる元気そうでそれを聞いてころころと笑う。
「あら、いいではありませんか。
この二人、とてもお似合いですわ。
以前よりも雰囲気も変わって、すっかり夫婦といった感じもしますもの」
千は遠慮なく、意味ありげな視線を龍星に送る。
龍星は涼しい顔で聞き流すが、隣に居る毬が途端に真っ赤になって狼狽えるのだから、二人の間に【何か】があったことは隠しようもなかった。
「――あ、あのね、お姉さま」
「いいのよ、毬。
何も言わないで。
私、余計なこと想像しちゃいそうだから」
毬はついにいたたまれなくなって、龍星の背中の方に隠れてしまった。
「あらあら、すっかり懐いてしまって。
でも、からかうためだけに来てもらったわけではないのよ。
先日は、本当に申し訳なかったわ。
傷の調子はどうかしら?」
千はさらりと話題を変えるが、毬は動揺が収まらずに二の句がつけない。
「見るからに元気そうではないか」
代わりに答えたのは、益々面白くなさそうにふてくされていた帝だった。
「龍星を出仕させるためには、毬を呼ぶほか手だてがないのか」
帝は開口一番、不機嫌にそう言った。
千はおなかがかなり出てきたものの、すこぶる元気そうでそれを聞いてころころと笑う。
「あら、いいではありませんか。
この二人、とてもお似合いですわ。
以前よりも雰囲気も変わって、すっかり夫婦といった感じもしますもの」
千は遠慮なく、意味ありげな視線を龍星に送る。
龍星は涼しい顔で聞き流すが、隣に居る毬が途端に真っ赤になって狼狽えるのだから、二人の間に【何か】があったことは隠しようもなかった。
「――あ、あのね、お姉さま」
「いいのよ、毬。
何も言わないで。
私、余計なこと想像しちゃいそうだから」
毬はついにいたたまれなくなって、龍星の背中の方に隠れてしまった。
「あらあら、すっかり懐いてしまって。
でも、からかうためだけに来てもらったわけではないのよ。
先日は、本当に申し訳なかったわ。
傷の調子はどうかしら?」
千はさらりと話題を変えるが、毬は動揺が収まらずに二の句がつけない。
「見るからに元気そうではないか」
代わりに答えたのは、益々面白くなさそうにふてくされていた帝だった。