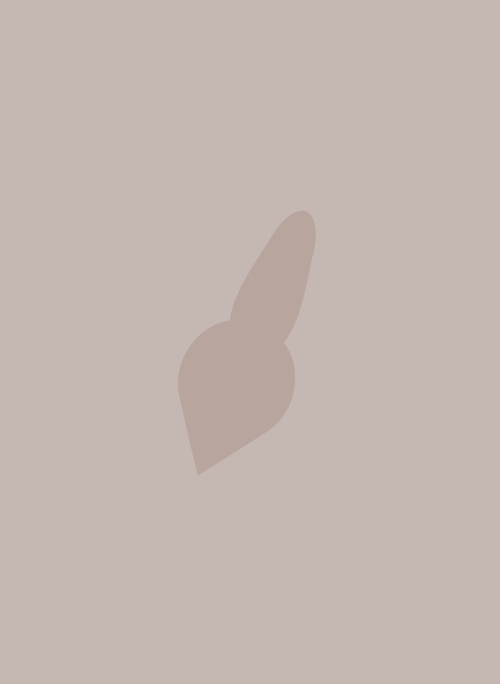「ねぇ、何処か行こうよ」
甘えるように勇作に纏わり付いてリサは言った。まだ子供のような所のある彼女にとってずっと部屋の中にいるのは息が詰まるらしい。ウィークデイは勇作について会社に行っているのだが、誰にも気づかれないように息を潜めているため、出掛けたことにはならないようだ。
勇作はその仕事で神経を磨り減らし、休日だからと言ってとても出掛ける気にはなれなかった。だが、リサが甘えるようにして片時も彼から離れようとしないので、とうとう根負けしてしまった。
「近くなら良いよ」
ゆったりと身体を沈ませていた椅子から起き上がると勇作はリサの頭に手を置いた。
「近くって、どこ?」
「シネコンなんてどうだい?」
勇作はそう言うと私鉄の駅名を告げた。
「何を見るの?」
リサは目を輝かせている。行く先は何処でも良いようだ。彼女にとっては勇作と出かけることが大事なのだろう。
「行ってから決めても良いんじゃない?」
勇作は本棚代わりにしているカラーボックスの上からヘルメットを一つ取った。リサの分はない。他の人には見えないのだし、何より彼女は死んでいる。安全に気を配らなくても良いのだ。
「そうだね、じゃあ早く行こう」
リサは嬉しそうに玄関の扉を擦り抜けていく。こういうとき幽霊は便利だと勇作は思った。
鉄製の外階段を下り、自転車置き場に向かう。数台の自転車やバイクの中から百二十五CCのスクーターに二人は跨がった。リサはスクーターに乗る必要はないのだが、こういうときは必ず勇作の後ろのシートに座った。
セルスターターを回し、スロットルを開く。単気筒のエンジンの軽い断続音が響く。
「落ちるなよ」
勇作は首を後ろに向けて言った。
「大丈夫、しっかり捉まっているから」
リサは勇作の胴に回した両腕に力を込めた。
本来、幽霊には実体がないのだから彼女の力を感じることはないのだが、勇作にはリサがしっかりと捉まっていることを感じていた。
エンジンの心地よい音が高まり、二人(正確には人間一人と幽霊一体)を乗せたスクーターは走り出した。
甘えるように勇作に纏わり付いてリサは言った。まだ子供のような所のある彼女にとってずっと部屋の中にいるのは息が詰まるらしい。ウィークデイは勇作について会社に行っているのだが、誰にも気づかれないように息を潜めているため、出掛けたことにはならないようだ。
勇作はその仕事で神経を磨り減らし、休日だからと言ってとても出掛ける気にはなれなかった。だが、リサが甘えるようにして片時も彼から離れようとしないので、とうとう根負けしてしまった。
「近くなら良いよ」
ゆったりと身体を沈ませていた椅子から起き上がると勇作はリサの頭に手を置いた。
「近くって、どこ?」
「シネコンなんてどうだい?」
勇作はそう言うと私鉄の駅名を告げた。
「何を見るの?」
リサは目を輝かせている。行く先は何処でも良いようだ。彼女にとっては勇作と出かけることが大事なのだろう。
「行ってから決めても良いんじゃない?」
勇作は本棚代わりにしているカラーボックスの上からヘルメットを一つ取った。リサの分はない。他の人には見えないのだし、何より彼女は死んでいる。安全に気を配らなくても良いのだ。
「そうだね、じゃあ早く行こう」
リサは嬉しそうに玄関の扉を擦り抜けていく。こういうとき幽霊は便利だと勇作は思った。
鉄製の外階段を下り、自転車置き場に向かう。数台の自転車やバイクの中から百二十五CCのスクーターに二人は跨がった。リサはスクーターに乗る必要はないのだが、こういうときは必ず勇作の後ろのシートに座った。
セルスターターを回し、スロットルを開く。単気筒のエンジンの軽い断続音が響く。
「落ちるなよ」
勇作は首を後ろに向けて言った。
「大丈夫、しっかり捉まっているから」
リサは勇作の胴に回した両腕に力を込めた。
本来、幽霊には実体がないのだから彼女の力を感じることはないのだが、勇作にはリサがしっかりと捉まっていることを感じていた。
エンジンの心地よい音が高まり、二人(正確には人間一人と幽霊一体)を乗せたスクーターは走り出した。