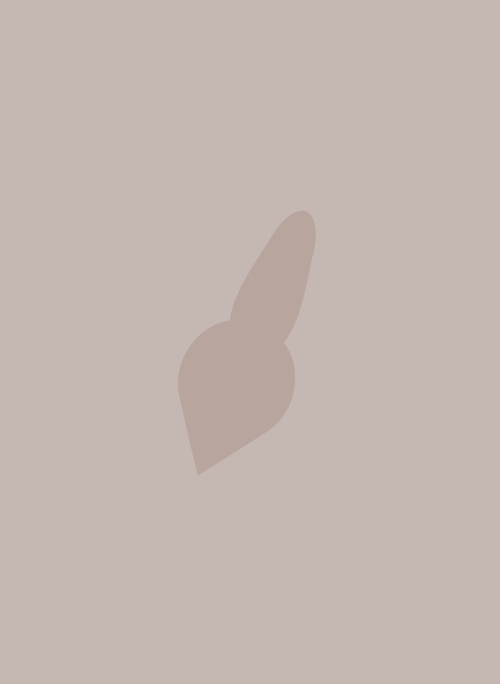リサと暮らし始めて一週間が過ぎた。
彼女は勇作が何処行くにも一緒に行動していた。勇作が仕事に行くのも、日常のちょっとした買い物に行くにも、必ずついてきた。幸い彼女は勇作以外の人には殆ど見えないため、彼にとって特に支障はなかったが…。
リサはとても寂しがり屋なんだ。勇作はそう理解した。実際彼女は年齢よりも幼く見えた。まだ親に反抗しない年齢のようだった。生きていた頃はきっと大事に育てられていたのだろう。口では大人びたことをいっているが、無垢で壊れやすい危うさを持っているようだった。
(この子は僕が傍に居ないと駄目なのかもしれない)
小さなテーブルに両肘をついてCDプレーヤーから流れてくる音楽を心地よさそうに聴いているリサを見て勇作はそんなことを考えていた。
流れてくる曲は皆、十数年前の曲だった。勇作がまだ学生だった頃に流行っていた曲でリサが知らないようなものばかりだった。それでも彼女は勇作の好きなものは出来る限り自分のものにしようとしていた。そんな彼女の健気さを勇作は妹を見るような視線で眺めていた。
そう、勇作はいつの間にかこのリサという少女に好意を抱き始めていた。
実際、何の変化もなく、退屈な日々の繰り返しの中に心地よい変化を与えてくれた。リサが勇作を頼りにしているように、勇作もまた、リサを必要とし始めていた。リサがいることが日常の一部になり始めていた。こんな暮らしが続いていくことも悪くはない。勇作はそう思うようになっていた。
また、リサが勇作以外の人には見えないということが彼を更に心地よくさせていた。他の人間に見えないのだから、勇作以外にリサに好意を抱くものは居ないはずだった。それはリサが勇作の元から去ることはないということでもあった。
以前、勇作にも女性と交際していた頃があった。だが、それはいつも長続きはしなかった。勇作自身、女性の扱いに不器用であったし、そんな勇作に過去の女性達はいつしか距離を置くようになっていた。
その心配がリサにはないのだ。
リサが幽霊であることは勇作を安心させることでもあったが、同時に一つの悲しさを彼は感じていた。
どれほどリサを愛おしく感じるようになっても、彼女に触れることが叶わない。
その事実だった。
彼女は勇作が何処行くにも一緒に行動していた。勇作が仕事に行くのも、日常のちょっとした買い物に行くにも、必ずついてきた。幸い彼女は勇作以外の人には殆ど見えないため、彼にとって特に支障はなかったが…。
リサはとても寂しがり屋なんだ。勇作はそう理解した。実際彼女は年齢よりも幼く見えた。まだ親に反抗しない年齢のようだった。生きていた頃はきっと大事に育てられていたのだろう。口では大人びたことをいっているが、無垢で壊れやすい危うさを持っているようだった。
(この子は僕が傍に居ないと駄目なのかもしれない)
小さなテーブルに両肘をついてCDプレーヤーから流れてくる音楽を心地よさそうに聴いているリサを見て勇作はそんなことを考えていた。
流れてくる曲は皆、十数年前の曲だった。勇作がまだ学生だった頃に流行っていた曲でリサが知らないようなものばかりだった。それでも彼女は勇作の好きなものは出来る限り自分のものにしようとしていた。そんな彼女の健気さを勇作は妹を見るような視線で眺めていた。
そう、勇作はいつの間にかこのリサという少女に好意を抱き始めていた。
実際、何の変化もなく、退屈な日々の繰り返しの中に心地よい変化を与えてくれた。リサが勇作を頼りにしているように、勇作もまた、リサを必要とし始めていた。リサがいることが日常の一部になり始めていた。こんな暮らしが続いていくことも悪くはない。勇作はそう思うようになっていた。
また、リサが勇作以外の人には見えないということが彼を更に心地よくさせていた。他の人間に見えないのだから、勇作以外にリサに好意を抱くものは居ないはずだった。それはリサが勇作の元から去ることはないということでもあった。
以前、勇作にも女性と交際していた頃があった。だが、それはいつも長続きはしなかった。勇作自身、女性の扱いに不器用であったし、そんな勇作に過去の女性達はいつしか距離を置くようになっていた。
その心配がリサにはないのだ。
リサが幽霊であることは勇作を安心させることでもあったが、同時に一つの悲しさを彼は感じていた。
どれほどリサを愛おしく感じるようになっても、彼女に触れることが叶わない。
その事実だった。