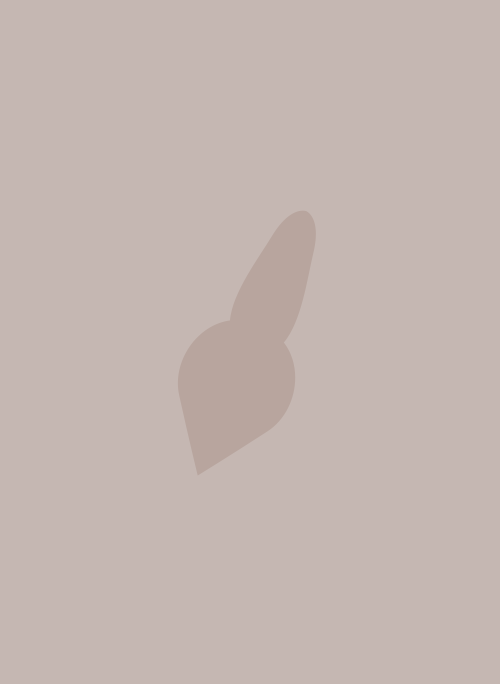「本当に、助けてくださって、ありがとうございました。」
私は、おぶわれながらも、頭を小さく下げた。
「いえいえ。そんなことお気になさらないで。むしろ、助けられて本当によかった。」
「渡部さんが、通りかかって、声をかけてくれなかったら……何度考えても恐ろしいです。」
「本当に、ひどい奴が世の中にいるものですよね。俺は、ああゆう人間が一番許せないんです。」
今まで、自分のことを「僕」と言っていたのに、急に「俺」に変わったところにドキッとしてしまった。
気持ちがあらぶってつい、口走ってしまったのだろうか。でも、そうした本音を聞けたことは、本当の彼を垣間見れた気がして、嬉しかった。
「そういう人たちを、取り締まるために、渡部さんは、警察官になられたんですか?」
私は、少々立ち入っている気がして気が引けたが、尋ねた。
「いやぁ、僕はそんないい人間じゃないですよ。そうありたいとは思いますけど、なかなか難しいですし、そんな立派な理由でなったわけではないですよ。」
そういって、白い息をたなびかせた。
「んー、パトカーに乗ってみたかったからかな?なーんてね!」
ハハハ、とまた心地よい笑い声をころころと響かせた。
「とっても素敵ですね。それに、渡部さんは本当にしっかり職務をこなされていると私は思います。あの町の人に、感謝され、頼られてると、思います…。」
消え入りそうな声で、私はそういった。
体がとても熱かった。
この熱が彼の背中を伝っていってしまうことを恐れ、また更に熱くなった。
「なんで、そう思うんです?」
「それは……」
とだけいって、私は口をとっさにつぐんだ。
だって、私は、毎日あなたを見てるから。
仕事に行くとき、帰るとき、ランチに出たとき。いつでもあなたがいないかと、あなたの姿を探してしまう。そして、見つけた時のあなたは、いつも真剣な表情で、仕事をしているか、近隣の人らしき人々と穏やかな笑顔を浮かべて話しているから……
なんて、言えるわけない。そんな、ストーカーみたいなこと。
さらに真っ赤になって、私は彼の背中に顔をうずめた。
「ありがとうございます。」
彼は静かにそういった。
その穏やかな響きを、私は、満足げにゆったりと味わった。
幸せの味をじっくりと味わった気がした。
彼の地面を踏みしめる足音が心地よく耳に響き、歩くたびに揺れる振動が心地よくって、そのまま眠りへの扉をそっと開けてしまっていた。