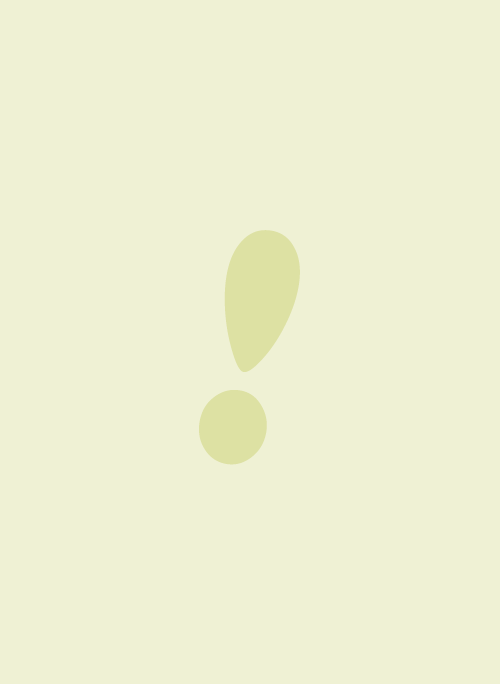赤色灯の数も少なくなったのと、徹に促されて私はあちき君の家に戻った。
リビングのあちき君のベッドに千穂子が寝ていた。
文也は私が出て行く前と同じ体制で居た。
あちき君はコタツに座っていた。
私はリビングの隅に置かれた文也達の服を見た。
血と油と、汚れにまみれていた。
悔しさが再び込み上げて来た。
その朝、みんな一言も喋らなかった。
本当は学校を休もうと思った。
そしたら、あちき君が優しく言った。
『みんな大丈夫だから、文弥は学校に行ってきな。みんな何処にも行かないから。な……。』
文也も私を見て頷いた。
私はゆっくり学校に向かった。
足に鉛がついて、後ろ髪を思い切り引っ張られたみたいな感じを憎々しく思いながら駅に向かった。
リビングのあちき君のベッドに千穂子が寝ていた。
文也は私が出て行く前と同じ体制で居た。
あちき君はコタツに座っていた。
私はリビングの隅に置かれた文也達の服を見た。
血と油と、汚れにまみれていた。
悔しさが再び込み上げて来た。
その朝、みんな一言も喋らなかった。
本当は学校を休もうと思った。
そしたら、あちき君が優しく言った。
『みんな大丈夫だから、文弥は学校に行ってきな。みんな何処にも行かないから。な……。』
文也も私を見て頷いた。
私はゆっくり学校に向かった。
足に鉛がついて、後ろ髪を思い切り引っ張られたみたいな感じを憎々しく思いながら駅に向かった。