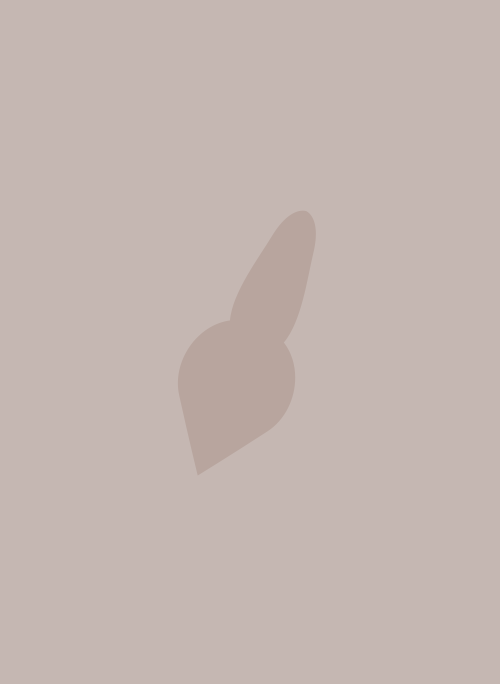誰もいない校庭を小島と恵はゆっくりと歩いていた。遠くから校内放送の音が聞こえてくる。その音が途切れた時、校舎内からざわめきが聞こえてきた。恐らく昨夜のことをこれから生徒達に説明されるのだろうと二人は思った。
今日は珍しく日差しが強い。容赦なく二人に降りかかる。小島は堪りかねてネクタイを緩める、恵もハンカチで拭きだしてくる額の汗を拭っている。
「嬢ちゃんはどう感じた?あの子達の言ってこと」
「少なくとも、余り真面目な生徒達ではないみたいですね。親や学校の目を盗んで遊んでいるようですから」
そう言ったとき、恵は突然、小島の行く手を遮るように立ちはだかり両手を腰にあてて鋭い目付きで小島を睨みつけた。
「小島さん、その『嬢ちゃん』っていうのはやめてくれませんか?」
小島は呆気にとられて恵を見つめた。
「私だって、もう三十近いんですから」
恵の声が段々小さくなる。
小島は溜息をついてそれに応える。
「そりゃあなぁ、嬢ちゃんは今は俺と階級は一緒だが、すぐに上になってしまう、そして県警に行っちまう」
小島は恵の鋭い視線をそらし、彼女の脇をすり抜ける時に上を見て言い切った。
「でも、俺にとっては『嬢ちゃん』は『嬢ちゃん』なんだ」
小島は恵の肩を叩く、恵は溜息をついて彼に続いた。
遠くでマイクを通した校長の声が聞こえてきた。
今日は珍しく日差しが強い。容赦なく二人に降りかかる。小島は堪りかねてネクタイを緩める、恵もハンカチで拭きだしてくる額の汗を拭っている。
「嬢ちゃんはどう感じた?あの子達の言ってこと」
「少なくとも、余り真面目な生徒達ではないみたいですね。親や学校の目を盗んで遊んでいるようですから」
そう言ったとき、恵は突然、小島の行く手を遮るように立ちはだかり両手を腰にあてて鋭い目付きで小島を睨みつけた。
「小島さん、その『嬢ちゃん』っていうのはやめてくれませんか?」
小島は呆気にとられて恵を見つめた。
「私だって、もう三十近いんですから」
恵の声が段々小さくなる。
小島は溜息をついてそれに応える。
「そりゃあなぁ、嬢ちゃんは今は俺と階級は一緒だが、すぐに上になってしまう、そして県警に行っちまう」
小島は恵の鋭い視線をそらし、彼女の脇をすり抜ける時に上を見て言い切った。
「でも、俺にとっては『嬢ちゃん』は『嬢ちゃん』なんだ」
小島は恵の肩を叩く、恵は溜息をついて彼に続いた。
遠くでマイクを通した校長の声が聞こえてきた。