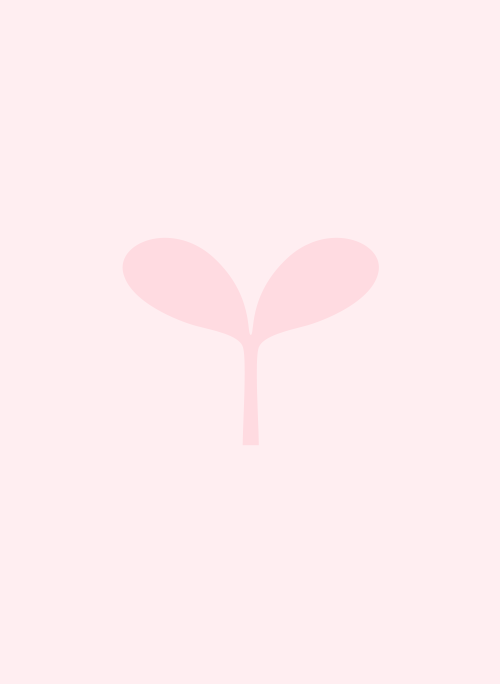「ユンさまが――」
思いもよらぬ名前が耳に届き、マイアは足を止めた。
偶然にも柱に隠れるように佇むマイアの姿は、きっと彼女らの視線には入っていないのであろう。マイアが立ち止まるのと同時くらいに、ひとりの少女が堪えきれず涙をぽろぽろとこぼし始めた。周りにいた少女らは、顔を覆って泣き始めた少女を宥めるように、肩に手を置き心配そうな表情で、「大丈夫」とだけ言った。
人好きのするユンは、城中の少女らから熱い視線を注がれることも少なくはない。マイアには内緒にしているのであろうが、言い寄られてすまなさそうに断りを伝えるユンを見かけたこともある。
マイアは、柱にもたれかけながら、深く息を吐き出した。
泣いているということは、受け入れられなかったのだろう。ユンのことだから、相手が傷つくような拒絶は決してしない。けれど、それが逆に相手を傷つけるのだ。
マイアの胸がどきどきと鼓動を打つ。
心臓をぎゅっと握られたような苦しさの中に、優越感からくる胸の高鳴りも自覚していた。