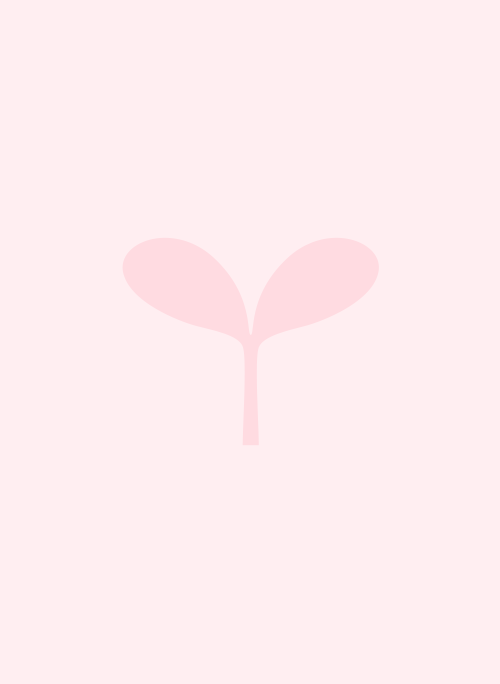だが、この日は違った。
妖精の囁きではなく、人間の話し声だ。
なんとなく視線を庭園のほうに巡らせてみれば、同じ仕着せに身を包んだ女中が、箒を持ったまま数人で固まって話をしていた。よほど真剣な話をしているのか、よく晴れた空には不釣り合いなほど暗い表情をしている者もいれば、涙をこらえているかのような苦痛に満ちた表情の少女もいる。
この渡り廊下で人を見かけるのは珍しかったが、こうして女中が固まって談笑したり、会話に花を咲かせていたりする光景は何も珍しいものでもなかった。おそらく庭園の清掃にあたっている者たちだろう。
(……失恋でもしたのかしら)
彼女たちからにじみ出ている沈鬱とした雰囲気に、マイアはそう思った。
自分とそれほど歳の変わらない少女らが集まって、しかも今にも泣きだしそうな苦い表情を見れば、一番に思いつくのが若い悩みだった。
以前ステイルに恋をしていた頃は、あの少女のように暗く塞ぎこんだり泣くのを堪えたり、辛いと思うような気持ちに苛まれた。
そんなことを思いだし、ほんの少しの苦さと、すでに過去として自分が乗り越えたことを強く実感して安堵するふたつの思いを抱えながら、彼女らの集まっている場所に近づいたときだった。