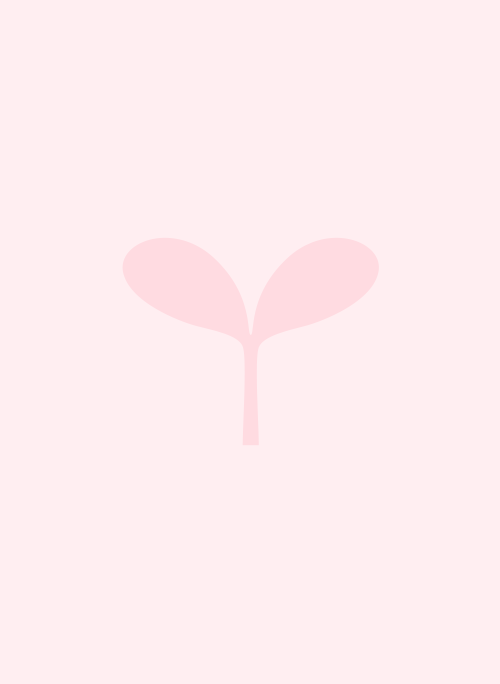そんな二か月を過ごしたある日。
いつものように、マイアはマリーおばさんたちの部屋で時を過ごしていた。城中で働く女中のひとりが、マイアに言伝を持って現れた。フィーネ様がお呼びです、とだけ残して去っていく背中を見て、マイアはなぜか言葉に言い表せないような不安を覚えた。
フィーネがマイアを呼びつけるのは、これが初めてではないのに。むしろ、よくある出来事だった。
それなのに――。
マイアは、賑やかな雰囲気に包まれた部屋の中でたった一人、静かに視線を窓に映した。
不安など、どこにも見当たらないような、雲ひとつない晴れた昼だった。
フィーネの自室に続く、一階の長い廊下をマイアはひとり歩いていた。
華やかな花々に彩られた庭園がマイアの左手側に広がる。窓のない廊下には、等間隔にある柱が庭園から差し込む強い陽光で薄暗い廊下に長い影を作っていた。人気もなく、城の中で一番好きな場所だった。柱に妖精が隠れていて、マイアが通り過ぎる瞬間に小さな顔を出すのだと言われれば、夢見る年頃が終わったマイアでも本気で信じてしまえるほど、ここの場所は綺麗である。唯一聞こえるのは、風が草花を揺らす音のみだ。もしくは妖精たちが囁きあう声――。