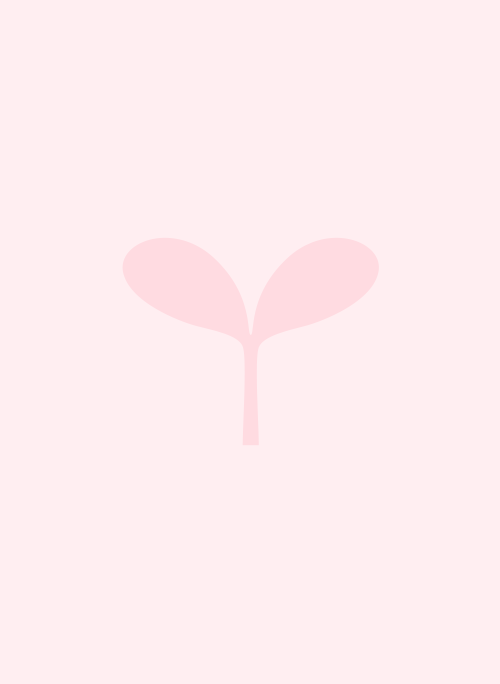本当は、起きているのよ、と言いたい。
今日はどんなお仕事をしてきたの、と訊きたい。
もうずっとユンの声を聞いていない。
けれど、たった二時間程度しか眠れないユンの邪魔をしたくはなかった。マイアが話しかけることで、一分、二分――十分と、それだけ時間が減っていくのを知っていたからだ。ただでさえ過酷な状況で働いているというのに、これ以上ユンの睡眠を削ってしまえば、今度はユンが倒れてしまう。
そう考えると、どうしても目が開けられなかった。
ユンが部屋から出て行ったあと、しばらくは眠れない。知らず涙が頬を伝う夜もある。けれど、不満だと声に出してはいけない。会えるだけ――ユンがマイアの部屋に来てくれるだけでも、十分に恵まれているのだ。
わかってはいても、やはりマイアは寂しかった。
だからこそ、起きている時間はマリーおばさんたちのいる部屋に入り浸っていた。少しでも気を紛らわせるために。なるべく独りの時間を作らないよう、賑やかで笑顔の溢れる部屋で、一日中過ごした。