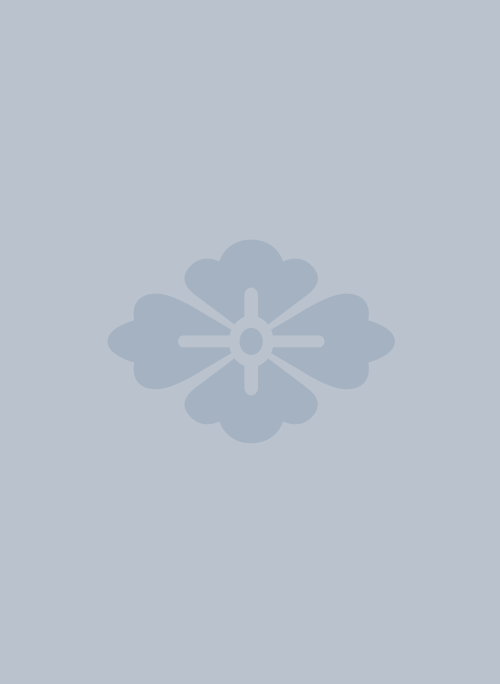「…よろしいのですか?ご当主。」
イヤミったらしくそう聞いたのは久佐波。
「その言い方はやめてくれ。」
「ですが…」
にへらと笑って手を振った恭二に、久佐波は眉を顰めた。
「お前の言いたいことは分かっているつもりだよ。」
「ならば戻すべきではなかったのでは?奏楽様の安全を考えるのならあそこは何が何でも説得するべきです。」
「許可を得ようとしているならね。」
「はい?」
恭二は立ち上がり、廊にでた。
そして、星の出ている空を見上げた。
「あの子は『戻らせてください』とお願いしてきたわけでも『戻りたいです』とも、どちらとも私の答えを気にするものではなかった。」
「それは確かに…」
「あの時…もし、『戻らせてください』と言ってきたなら鎖をつけてでもここから出さないつもりだったが…いやいや、さすがは姉さんの子。『戻ります』と来られては…可愛い姪の巣立ちを邪魔する理由なんてないよ。…寂しいがね。それに、生半可な覚悟ではないのだろう。なんて言ったってこの日の本一、優秀な私の姪だからね!!」
ふふん、と胸をはる恭二に、久佐波は、冷ややかな視線を向けた。
「…鎖をつけるとは…とんだ発想ですね…いえ、ですが気にしないでください。たとえご当主がそうであっても軽蔑などは表に出しせんよ?なぜなら私が仕えるご当主ですからね。」
「突っ込むところはそこか、久佐波…それにお前、さりげなく私を軽蔑しているだろう」
「いえ、表には出しません。」
「心の中では思っているということか。」
「なるほど、ですから奏楽さまの浪士組戻りを許可なさったのですね。」
イヤミったらしくそう聞いたのは久佐波。
「その言い方はやめてくれ。」
「ですが…」
にへらと笑って手を振った恭二に、久佐波は眉を顰めた。
「お前の言いたいことは分かっているつもりだよ。」
「ならば戻すべきではなかったのでは?奏楽様の安全を考えるのならあそこは何が何でも説得するべきです。」
「許可を得ようとしているならね。」
「はい?」
恭二は立ち上がり、廊にでた。
そして、星の出ている空を見上げた。
「あの子は『戻らせてください』とお願いしてきたわけでも『戻りたいです』とも、どちらとも私の答えを気にするものではなかった。」
「それは確かに…」
「あの時…もし、『戻らせてください』と言ってきたなら鎖をつけてでもここから出さないつもりだったが…いやいや、さすがは姉さんの子。『戻ります』と来られては…可愛い姪の巣立ちを邪魔する理由なんてないよ。…寂しいがね。それに、生半可な覚悟ではないのだろう。なんて言ったってこの日の本一、優秀な私の姪だからね!!」
ふふん、と胸をはる恭二に、久佐波は、冷ややかな視線を向けた。
「…鎖をつけるとは…とんだ発想ですね…いえ、ですが気にしないでください。たとえご当主がそうであっても軽蔑などは表に出しせんよ?なぜなら私が仕えるご当主ですからね。」
「突っ込むところはそこか、久佐波…それにお前、さりげなく私を軽蔑しているだろう」
「いえ、表には出しません。」
「心の中では思っているということか。」
「なるほど、ですから奏楽さまの浪士組戻りを許可なさったのですね。」