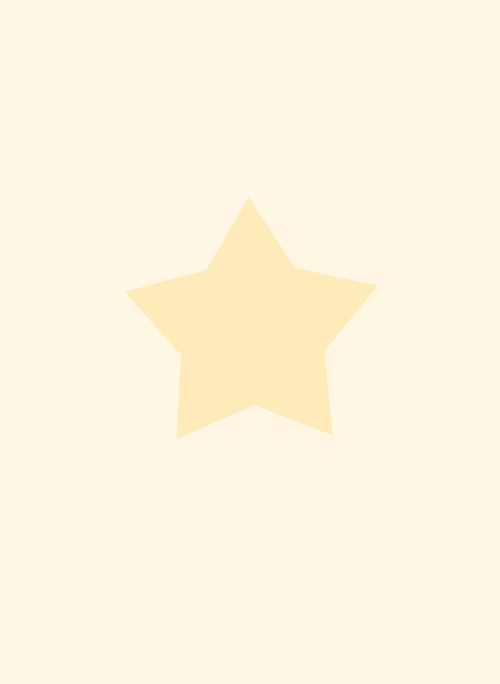「ちょっと、ちょっと」
キリはあわてて赤いマントを引っぱった。
「ラグナードこそ、やめておいたほうがいいよ」
頭に血が上っている男たちを観察して、キリはささやいた。
「あの人たち、ただのごろつきじゃなくて、たぶんプロの傭兵だよ?」
箱入りのおぼっちゃまにしか見えない白銀の騎士に対し、男たちは身につけた鋼と皮の無骨な鎧こそ粗末なものの、どの男も筋骨隆々でたくましい体つきをしており、その鎧や身に刻まれた無数の傷が、歴戦の強者であることを物語っている。
そして、全員が手に剣をぶら下げていた。
「そんなことは見ればわかる」
ラグナードは口の端をつり上げて笑い、留め金を外してマントを脱ぎ捨てた。
「わかってるなら、ケンカするなんてばかだよ。相手は五人もいるんだし」
「バカはおまえとあいつらだ。プロだと言うなら、金で雇われて戦争をする傭兵とこの俺と、どちらが戦いに慣れているかくらいわかるだろう」
一瞬キリは、ラグナードが魔法の援護を期待しているのだろうかとも思ったが、その言葉からは本気で五人の荒くれ者たちより自分が優位だと信じて疑っていないことが伝わってきた。
「持っていろ」
と言って、さらにラグナードが自らの剣までキリに押しつけてきたので、キリは頭を抱えそうになった。
「ケンカで剣を抜かないとは、高尚な騎士道精神か何かか?」
一方の男たちは一様にあざけって、ずらずらと剣を抜きはなった。
「悪ィが、俺たちは『生まれが卑しい』んでね」
男の一人がラグナードのセリフを根に持った様子で引用し、
「遠慮なくこいつを使わせてもらう」
掲げられた剣呑(けんのん)な鋼のぎらつきを目にして、宿屋の主がふるえあがる。
「流血ざたは困りやすぜ!」
「うるせえ、引っこんでろ」
と店主を押さえつけたのは、傭兵たちの仲間ではなく、こんなおもしろい酒の肴はないとばかりに周囲で盛り上がる他の客だった。
「違うな」
鋼鉄の刃を向けられても眉一つ動かさずに、ラグナードは男たちと向き合って立っていた。
「はあ? 何がだ?」
「剣を使わないのは騎士道精神などではない、と言ったんだ」
美しい口もとに強気な笑みを作ったまま、素手の若者は平然と語った。
「おまえたちのような者を斬っては、下賤の血で俺の剣が汚れる」
その一言が、開始の合図となった。
あんまりの言いように堪忍袋の緒が切れ、
肉厚の剣を振りかざして、最初にカップをぶつけられた男が躍りかかる。
キリは目を見張った。
キリはあわてて赤いマントを引っぱった。
「ラグナードこそ、やめておいたほうがいいよ」
頭に血が上っている男たちを観察して、キリはささやいた。
「あの人たち、ただのごろつきじゃなくて、たぶんプロの傭兵だよ?」
箱入りのおぼっちゃまにしか見えない白銀の騎士に対し、男たちは身につけた鋼と皮の無骨な鎧こそ粗末なものの、どの男も筋骨隆々でたくましい体つきをしており、その鎧や身に刻まれた無数の傷が、歴戦の強者であることを物語っている。
そして、全員が手に剣をぶら下げていた。
「そんなことは見ればわかる」
ラグナードは口の端をつり上げて笑い、留め金を外してマントを脱ぎ捨てた。
「わかってるなら、ケンカするなんてばかだよ。相手は五人もいるんだし」
「バカはおまえとあいつらだ。プロだと言うなら、金で雇われて戦争をする傭兵とこの俺と、どちらが戦いに慣れているかくらいわかるだろう」
一瞬キリは、ラグナードが魔法の援護を期待しているのだろうかとも思ったが、その言葉からは本気で五人の荒くれ者たちより自分が優位だと信じて疑っていないことが伝わってきた。
「持っていろ」
と言って、さらにラグナードが自らの剣までキリに押しつけてきたので、キリは頭を抱えそうになった。
「ケンカで剣を抜かないとは、高尚な騎士道精神か何かか?」
一方の男たちは一様にあざけって、ずらずらと剣を抜きはなった。
「悪ィが、俺たちは『生まれが卑しい』んでね」
男の一人がラグナードのセリフを根に持った様子で引用し、
「遠慮なくこいつを使わせてもらう」
掲げられた剣呑(けんのん)な鋼のぎらつきを目にして、宿屋の主がふるえあがる。
「流血ざたは困りやすぜ!」
「うるせえ、引っこんでろ」
と店主を押さえつけたのは、傭兵たちの仲間ではなく、こんなおもしろい酒の肴はないとばかりに周囲で盛り上がる他の客だった。
「違うな」
鋼鉄の刃を向けられても眉一つ動かさずに、ラグナードは男たちと向き合って立っていた。
「はあ? 何がだ?」
「剣を使わないのは騎士道精神などではない、と言ったんだ」
美しい口もとに強気な笑みを作ったまま、素手の若者は平然と語った。
「おまえたちのような者を斬っては、下賤の血で俺の剣が汚れる」
その一言が、開始の合図となった。
あんまりの言いように堪忍袋の緒が切れ、
肉厚の剣を振りかざして、最初にカップをぶつけられた男が躍りかかる。
キリは目を見張った。