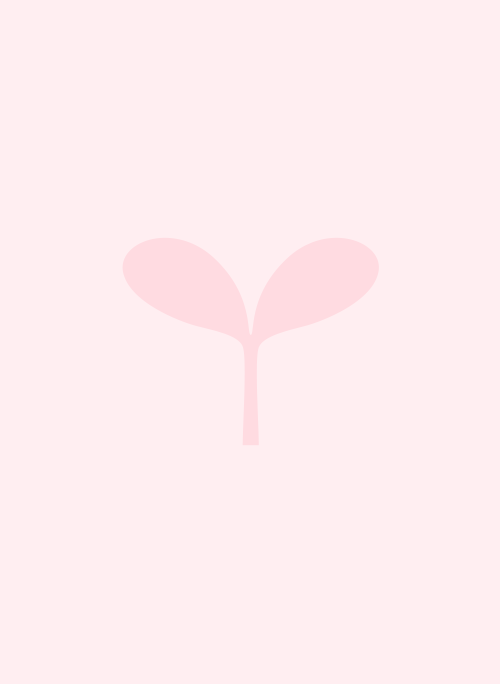「そこの主人が言った言葉が通じなかったようだから、もう一度この俺が言ってやる」
ラグナードは流暢(りゅうちょう)に地方言語を操って、男たちに冷笑を向けて言った。
「まるで盛りのついたオス犬だな」
「なんだと!?」
「これだから生まれの卑しい者は、行動も下品で困る。
ここは売春宿か? 女に飢えているなら他の店に行け。
貴様らのようなクズは他の客の──というか、俺の酒のじゃまだ。俺の視界からただちに消えうせろ」
男たちを映す紫色の瞳は、虫けらかゴミでも見るかのような見下しきった侮蔑の色をたたえていた。
「──と、この主人は言ったんだ。ばかな頭でも今度は理解できたか?」
そうしめくくって、
きれいな顔を冷ややかな嘲笑(ちょうしょう)でいろどったまま、ラグナードはふたたび優雅に杯をかたむけた。
そこまでは言っていない! と、主張したかったが言葉にならずにパクパクと口を動かして、蒼白になった店の主人は脂汗の浮いた頭をぶんぶか横に振った。
「このやろう──」
いっせいに、男たちが立ち上がった。
「どこの貴族のボンボンか知らねえが──ご立派な騎士様よォ、覚悟はできてるだろうなァ」
昨日からのキリとの会話でも、相手を怒らせるような発言を幾度となくくり返しているラグナードだが、
普段に輪をかけて悪意たっぷりの今回のセリフは、完全にけんかを売った内容だった。
「覚悟だと?」
ラグナードは優雅に杯を持ったまませせら笑った。
「貴様らこそ、けんかをする気なら相手をよく見て選んだほうがいい。国ではこの鎧と狼の紋章を見て、俺に歯向かおうという者など一人もいなかったぞ?」
美青年は肩から下がったマントの装飾用の垂れ布を示し、そこにあしらわれた炎と狼を象った模様を見せた。
「やめておけ、ケガをすることになる」
「ケガだとよ」
男の一人が肩ごしに仲間をふり返って言い、こめかみに青筋をうかせたまま、男たちがどっと笑った。
「誰のケガの心配だ?」
「どこの国から出てきたのか知らねえが、世間知らずの坊やにはおしおきが必要だな」
どの男も、目がまったく笑っていなかった。
ラグナードが首を振って、コトリと杯をテーブルに置き立ち上がった。
「やれやれ、忠告してやったのに、親切がわからんとはな」
徹頭徹尾(てっとうてつび)上から目線の態度は、誰の目にも親切には見えず、彼の言う忠告とやらは挑発としか思えなかった。
血の気の多い客が集まった酒場にはたちまち、「いいぞ」「やれ!」という双方への野次が飛び交い、仲裁しようという者は皆無だった。
「お客さんがた、面倒ごとは……」
困り果てた店の主人が泣きそうになり、
ことの発端の娘はとっとと店の奥に逃げこんで、その場から姿を消してしまっていた。
ラグナードは流暢(りゅうちょう)に地方言語を操って、男たちに冷笑を向けて言った。
「まるで盛りのついたオス犬だな」
「なんだと!?」
「これだから生まれの卑しい者は、行動も下品で困る。
ここは売春宿か? 女に飢えているなら他の店に行け。
貴様らのようなクズは他の客の──というか、俺の酒のじゃまだ。俺の視界からただちに消えうせろ」
男たちを映す紫色の瞳は、虫けらかゴミでも見るかのような見下しきった侮蔑の色をたたえていた。
「──と、この主人は言ったんだ。ばかな頭でも今度は理解できたか?」
そうしめくくって、
きれいな顔を冷ややかな嘲笑(ちょうしょう)でいろどったまま、ラグナードはふたたび優雅に杯をかたむけた。
そこまでは言っていない! と、主張したかったが言葉にならずにパクパクと口を動かして、蒼白になった店の主人は脂汗の浮いた頭をぶんぶか横に振った。
「このやろう──」
いっせいに、男たちが立ち上がった。
「どこの貴族のボンボンか知らねえが──ご立派な騎士様よォ、覚悟はできてるだろうなァ」
昨日からのキリとの会話でも、相手を怒らせるような発言を幾度となくくり返しているラグナードだが、
普段に輪をかけて悪意たっぷりの今回のセリフは、完全にけんかを売った内容だった。
「覚悟だと?」
ラグナードは優雅に杯を持ったまませせら笑った。
「貴様らこそ、けんかをする気なら相手をよく見て選んだほうがいい。国ではこの鎧と狼の紋章を見て、俺に歯向かおうという者など一人もいなかったぞ?」
美青年は肩から下がったマントの装飾用の垂れ布を示し、そこにあしらわれた炎と狼を象った模様を見せた。
「やめておけ、ケガをすることになる」
「ケガだとよ」
男の一人が肩ごしに仲間をふり返って言い、こめかみに青筋をうかせたまま、男たちがどっと笑った。
「誰のケガの心配だ?」
「どこの国から出てきたのか知らねえが、世間知らずの坊やにはおしおきが必要だな」
どの男も、目がまったく笑っていなかった。
ラグナードが首を振って、コトリと杯をテーブルに置き立ち上がった。
「やれやれ、忠告してやったのに、親切がわからんとはな」
徹頭徹尾(てっとうてつび)上から目線の態度は、誰の目にも親切には見えず、彼の言う忠告とやらは挑発としか思えなかった。
血の気の多い客が集まった酒場にはたちまち、「いいぞ」「やれ!」という双方への野次が飛び交い、仲裁しようという者は皆無だった。
「お客さんがた、面倒ごとは……」
困り果てた店の主人が泣きそうになり、
ことの発端の娘はとっとと店の奥に逃げこんで、その場から姿を消してしまっていた。