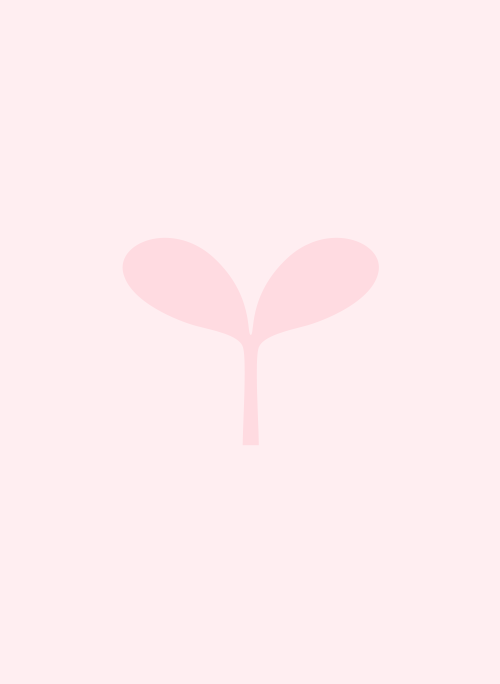慣れないスパイスの風味のために、おいしいのかまずいのかよくわからない異国の地の料理を二人でたいらげて、
「明日の作戦を立てておくぞ」
食後に追加で頼んだ果実酒の杯をかたむけながら、ラグナードは言った。
「作戦も何も」
キリはミルクとはちみつたっぷりの食後のお茶を一口飲んで、肩をすくめた。
ベルムの樹皮を丸めたスティックが入っていて、かき混ぜるとスパイシーな香りが甘いお茶と良く合っておいしい。
「パイロープに着いたら、実質わたしが一人で怪物を何とかすることになるんでしょ」
彼女はやや憂鬱(ゆううつ)な気分になる。
どんな怪物なのかわからないものと対峙することになるのでは、心の準備もできない。
「誰がお前を一人で怪物に立ち向かわせると言った」
ラグナードは思いもよらない言葉を耳にしたという様子で、鼻を鳴らした。
「お前は霧を晴らすことに専念しろ。その間は、俺が怪物の相手をして注意を引きつけておく」
「えっ、ラグナードが?」
自らイスを引くのも拒む自称王子様のことだから、てっきり何もせずに高みの見物でも決めこむ気だとばかり思っていたキリは驚いて、
──不安になった。
「ええー? 大丈夫かな。死んじゃったりしない?」
「心配するな」
ラグナードは微笑んだ。
「これでも戦場では前線で戦っている。子供の頃から訓練も受けてきたし、戦いの経験はそれなりに豊富なつもりだ」
自信たっぷりにそう語る重武装の騎士様を、キリは穴が開くほどながめた。
格好だけは勇ましいが、いかにも温室育ちの小ぎれいな見た目の美青年は、他のテーブルの屈強な荒くれ者たちと比べても実に頼りなかった。
どちらかと言えばラグナードは色白で虚弱そうで、本人は戦場に出て戦ってきたつもりでも、端から見れば周囲の人間から大切に守られてきたという印象だ。
キリの目にはとてもとても、三百人の兵団がもどってこなかった場所に行って、未知の怪物相手に何か役に立つようには見えない。
「ほんとにほんとに大丈夫? 勝手に死んでもらったら困るよ? ラグナードが死んじゃったら、ヴェズルングの杖をくれる人がいなくなっちゃうんだから」
もっとも、ラグナードの命よりも彼女の心配事は目下、ご褒美の杖のことだった。
「旅の方?」
このとき、給仕をしていた娘がケノーランドの地方言語で声をかけてきて、二人は話を中断した。
「珍しい白い肌ね。異大陸の人?」
そう言う宿屋の娘は日に焼けた小麦色の肌をしていて、それは周囲の多くの客たちも同様だった。
砂漠の照り返しが強いケノーランドでは、色の黒い肌が一般的だ。
「どこから来たのかしら? 私の言葉、わかる?」
「ゴンドワナから来たの」
キリが、リンガー・ノブリスでそう答えた。
「明日の作戦を立てておくぞ」
食後に追加で頼んだ果実酒の杯をかたむけながら、ラグナードは言った。
「作戦も何も」
キリはミルクとはちみつたっぷりの食後のお茶を一口飲んで、肩をすくめた。
ベルムの樹皮を丸めたスティックが入っていて、かき混ぜるとスパイシーな香りが甘いお茶と良く合っておいしい。
「パイロープに着いたら、実質わたしが一人で怪物を何とかすることになるんでしょ」
彼女はやや憂鬱(ゆううつ)な気分になる。
どんな怪物なのかわからないものと対峙することになるのでは、心の準備もできない。
「誰がお前を一人で怪物に立ち向かわせると言った」
ラグナードは思いもよらない言葉を耳にしたという様子で、鼻を鳴らした。
「お前は霧を晴らすことに専念しろ。その間は、俺が怪物の相手をして注意を引きつけておく」
「えっ、ラグナードが?」
自らイスを引くのも拒む自称王子様のことだから、てっきり何もせずに高みの見物でも決めこむ気だとばかり思っていたキリは驚いて、
──不安になった。
「ええー? 大丈夫かな。死んじゃったりしない?」
「心配するな」
ラグナードは微笑んだ。
「これでも戦場では前線で戦っている。子供の頃から訓練も受けてきたし、戦いの経験はそれなりに豊富なつもりだ」
自信たっぷりにそう語る重武装の騎士様を、キリは穴が開くほどながめた。
格好だけは勇ましいが、いかにも温室育ちの小ぎれいな見た目の美青年は、他のテーブルの屈強な荒くれ者たちと比べても実に頼りなかった。
どちらかと言えばラグナードは色白で虚弱そうで、本人は戦場に出て戦ってきたつもりでも、端から見れば周囲の人間から大切に守られてきたという印象だ。
キリの目にはとてもとても、三百人の兵団がもどってこなかった場所に行って、未知の怪物相手に何か役に立つようには見えない。
「ほんとにほんとに大丈夫? 勝手に死んでもらったら困るよ? ラグナードが死んじゃったら、ヴェズルングの杖をくれる人がいなくなっちゃうんだから」
もっとも、ラグナードの命よりも彼女の心配事は目下、ご褒美の杖のことだった。
「旅の方?」
このとき、給仕をしていた娘がケノーランドの地方言語で声をかけてきて、二人は話を中断した。
「珍しい白い肌ね。異大陸の人?」
そう言う宿屋の娘は日に焼けた小麦色の肌をしていて、それは周囲の多くの客たちも同様だった。
砂漠の照り返しが強いケノーランドでは、色の黒い肌が一般的だ。
「どこから来たのかしら? 私の言葉、わかる?」
「ゴンドワナから来たの」
キリが、リンガー・ノブリスでそう答えた。