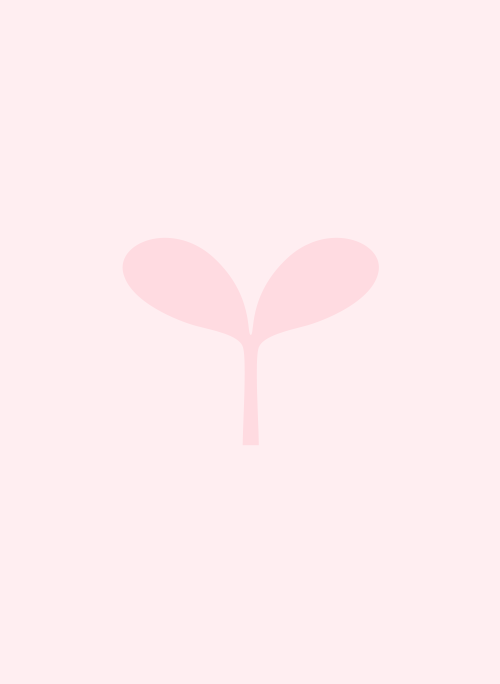ラグナードは目を見開いた。
「魔法の刻印みたいに見えるけど……ちょっと違うような……」
キリはもどかしそうに、うーんとうなった。
「何かに似てるんだけど……なんだっけ……?」
「お前──この刻印が見えるのか?」
ラグナードはかすれた声で言った。
「見える?」
キリはきょとんとした。
「そりゃもう、はっきりと。
そんなに大きな模様なら、見えるに決まってるよー。イレズミみたいな複雑なマークが……」
「あるらしいな。俺は見たことがないが」
「……はい?」
不思議そうな表情になるキリの前で、ラグナードは腰の後ろから小さなナイフを引き抜いて、みがきぬかれた鋼の輝きを左頬のそばに持っていった。
「こういうことだ」
言いながら、彼は酒場の中を照らすランプの灯りを反射してキラキラと輝く刃の角度を調節し、ナイフに映りこんだ己の左頬がキリにも見えるようにする。
「あれっ」と声を上げて、キリは目をまん丸にした。
「なんにも映ってない?」
刃物の中の鏡像には、色白の青年の頬が映っているだけだった。
しかし視線を実像の頬にもどせば、キリには出会った時から今も変わらずハッキリと、そこに刻まれた漆黒の紋様が見えている。
顔の左半分を覆いつくして刻みこまれた複雑な模様は、
何かの形を象った絵のようにも、
知らない太古の文字のようにも見える。
「こいつは鏡には映らないんだ」
と、ラグナードは言った。
「自分の顔を直に見ることはできないから、俺自身は見たことがない。ついでに言うと──」
ラグナードはナイフをしまって、周囲で盛り上がる他の客や、給仕にいそがしくかけまわる店の人間たちに視線を向けた。
「普通の人間には誰も、こいつは見えていないはずだ」
「えっ」
びっくりして、キリは周囲の人間たちを見回した。
「見えていれば、普通はお前のようにジロジロと俺の顔に目をやるものだろう」
昨夜からのキリの視線の意味を自意識過剰にかんちがいしていたと気づかされて、ラグナードは不機嫌に吐き捨てた。
「これは魔法の刻印だ」と、ラグナードは言った。
「この刻印を普通に見ることができるなど、お前が異常なんだ」
「魔法の刻印……?」
キリはエメラルドの瞳でまじまじとラグナードの頬にある不思議な模様を見つめた。
ありとあらゆる魔法の記号や紋章を思い浮かべてみたが、彼女の知るどんな魔法の刻印にも、目の前の模様と一致するものはなかった。
「うーん……強いて言えば、呪いの刻印に少しだけ似てるような……?」
夜の闇を墨に溶かして描いたような色はどこか不吉な、禍々しさのようなものを放っている。
「呪いだと? ばかを言うな」
ラグナードは不快そうに顔をしかめた。
「魔法の刻印みたいに見えるけど……ちょっと違うような……」
キリはもどかしそうに、うーんとうなった。
「何かに似てるんだけど……なんだっけ……?」
「お前──この刻印が見えるのか?」
ラグナードはかすれた声で言った。
「見える?」
キリはきょとんとした。
「そりゃもう、はっきりと。
そんなに大きな模様なら、見えるに決まってるよー。イレズミみたいな複雑なマークが……」
「あるらしいな。俺は見たことがないが」
「……はい?」
不思議そうな表情になるキリの前で、ラグナードは腰の後ろから小さなナイフを引き抜いて、みがきぬかれた鋼の輝きを左頬のそばに持っていった。
「こういうことだ」
言いながら、彼は酒場の中を照らすランプの灯りを反射してキラキラと輝く刃の角度を調節し、ナイフに映りこんだ己の左頬がキリにも見えるようにする。
「あれっ」と声を上げて、キリは目をまん丸にした。
「なんにも映ってない?」
刃物の中の鏡像には、色白の青年の頬が映っているだけだった。
しかし視線を実像の頬にもどせば、キリには出会った時から今も変わらずハッキリと、そこに刻まれた漆黒の紋様が見えている。
顔の左半分を覆いつくして刻みこまれた複雑な模様は、
何かの形を象った絵のようにも、
知らない太古の文字のようにも見える。
「こいつは鏡には映らないんだ」
と、ラグナードは言った。
「自分の顔を直に見ることはできないから、俺自身は見たことがない。ついでに言うと──」
ラグナードはナイフをしまって、周囲で盛り上がる他の客や、給仕にいそがしくかけまわる店の人間たちに視線を向けた。
「普通の人間には誰も、こいつは見えていないはずだ」
「えっ」
びっくりして、キリは周囲の人間たちを見回した。
「見えていれば、普通はお前のようにジロジロと俺の顔に目をやるものだろう」
昨夜からのキリの視線の意味を自意識過剰にかんちがいしていたと気づかされて、ラグナードは不機嫌に吐き捨てた。
「これは魔法の刻印だ」と、ラグナードは言った。
「この刻印を普通に見ることができるなど、お前が異常なんだ」
「魔法の刻印……?」
キリはエメラルドの瞳でまじまじとラグナードの頬にある不思議な模様を見つめた。
ありとあらゆる魔法の記号や紋章を思い浮かべてみたが、彼女の知るどんな魔法の刻印にも、目の前の模様と一致するものはなかった。
「うーん……強いて言えば、呪いの刻印に少しだけ似てるような……?」
夜の闇を墨に溶かして描いたような色はどこか不吉な、禍々しさのようなものを放っている。
「呪いだと? ばかを言うな」
ラグナードは不快そうに顔をしかめた。