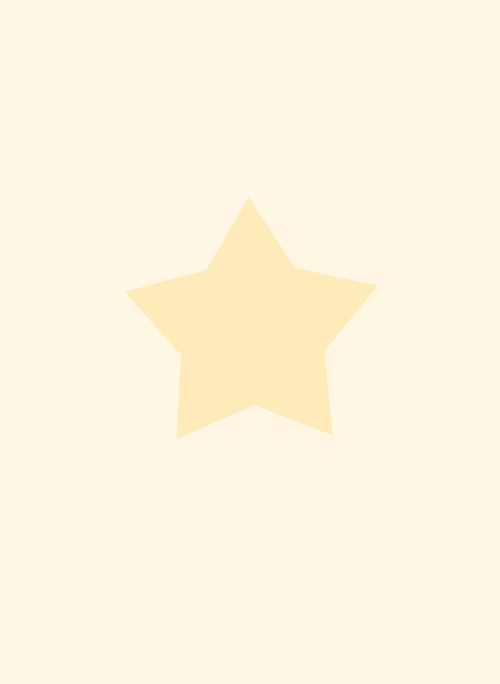エバーニアに行くもう一つのルートが、軽鉱石を使った天空船だ。
大いなる回廊の内部上空は真空で、旅の最大の障害となる霧がまったく発生しない。
このため、太陽や月の通り道である天空回廊をさけて、無数の星々にぶつからないようにさえ気をつければ、もっとも安全に移動できる場所であり、
そして直線距離を移動できる最短の経路でもある。
内部上空は人が一番に目をつけ、
昔から真空中を移動するための密閉された「天空船」を作って移動に利用してきた最大の航路だった。
とは言っても、世界の反対側まで飛ぶとなれば天空船を使っても一週間から十日はかかる。
ラグナードはこの杖が戦闘騎並の性能を持っているとは言っていたが、地表に沿ってたった二日で飛べるとは驚異的な速さだ。
「そういえば疲れると言ってたが、まさか途中で魔力が尽きて墜落したりしないだろうな」
ラグナードは心配になって訊(き)いた。
「あーそれは大丈夫。魔法核が出回ってるせいでそういうイメージがあるかもしれないけど、セレマ(魔力)ってのは、尽きたりするものじゃないから」
明日には着くと聞いて、キリは安堵しながら言った。
「ずーっと魔法使ってると、体がダルくなって疲れて眠たくなって、だから魔法が使えなくなるだけ。
でも、この杖は寝てる間も魔法を使わせ続けるから──操縦担当者が別に乗ってるなら、わたしが落っこちたり死んだりしなければ墜落しないよ」
ラグナードはぎょっとした。
「──って、死ぬのか!?」
キリはおかしそうに声を立てて笑った。
「飛行騎杖に乗って疲れて死んだ魔法使いの話は聞かないよー。
つまり、操縦者が他にいれば、魔法を使いっぱなしで休息もとれるから大丈夫ってこと。
……疲れるけどね」
そう言って、キリはほわほわあくびをした。
最初は感動したキリだったが、これだけ上空だと逆に見るものがあまりなくて早くも退屈していた。
「でも、操縦者のラグナードまで居眠りしたり、今わたしを殺したりしたら落ちるよ」
「肝に銘じておこう」
「じゃ、わたしは寝てるから、第一大陸に着いたら起こしてね」
「待て!」
嫌な予感がして、ラグナードはいそいで背後の少女に声をかけた。
「念のため、ヒモか何かで手すりに体をくくりつけてから寝ろ」
騎杖の狭いへこみの中で小動物のように丸くなって眠りこけるキリを、ラグナードが足でどついて起こしたのは、
豊かな第三大陸ローレンシアを過ぎ、西の空の上へと昇って消えてゆく夕日が、眼下に広がる荒涼たる砂の大地を紅に染め上げた日暮れだった。
大いなる回廊の内部上空は真空で、旅の最大の障害となる霧がまったく発生しない。
このため、太陽や月の通り道である天空回廊をさけて、無数の星々にぶつからないようにさえ気をつければ、もっとも安全に移動できる場所であり、
そして直線距離を移動できる最短の経路でもある。
内部上空は人が一番に目をつけ、
昔から真空中を移動するための密閉された「天空船」を作って移動に利用してきた最大の航路だった。
とは言っても、世界の反対側まで飛ぶとなれば天空船を使っても一週間から十日はかかる。
ラグナードはこの杖が戦闘騎並の性能を持っているとは言っていたが、地表に沿ってたった二日で飛べるとは驚異的な速さだ。
「そういえば疲れると言ってたが、まさか途中で魔力が尽きて墜落したりしないだろうな」
ラグナードは心配になって訊(き)いた。
「あーそれは大丈夫。魔法核が出回ってるせいでそういうイメージがあるかもしれないけど、セレマ(魔力)ってのは、尽きたりするものじゃないから」
明日には着くと聞いて、キリは安堵しながら言った。
「ずーっと魔法使ってると、体がダルくなって疲れて眠たくなって、だから魔法が使えなくなるだけ。
でも、この杖は寝てる間も魔法を使わせ続けるから──操縦担当者が別に乗ってるなら、わたしが落っこちたり死んだりしなければ墜落しないよ」
ラグナードはぎょっとした。
「──って、死ぬのか!?」
キリはおかしそうに声を立てて笑った。
「飛行騎杖に乗って疲れて死んだ魔法使いの話は聞かないよー。
つまり、操縦者が他にいれば、魔法を使いっぱなしで休息もとれるから大丈夫ってこと。
……疲れるけどね」
そう言って、キリはほわほわあくびをした。
最初は感動したキリだったが、これだけ上空だと逆に見るものがあまりなくて早くも退屈していた。
「でも、操縦者のラグナードまで居眠りしたり、今わたしを殺したりしたら落ちるよ」
「肝に銘じておこう」
「じゃ、わたしは寝てるから、第一大陸に着いたら起こしてね」
「待て!」
嫌な予感がして、ラグナードはいそいで背後の少女に声をかけた。
「念のため、ヒモか何かで手すりに体をくくりつけてから寝ろ」
騎杖の狭いへこみの中で小動物のように丸くなって眠りこけるキリを、ラグナードが足でどついて起こしたのは、
豊かな第三大陸ローレンシアを過ぎ、西の空の上へと昇って消えてゆく夕日が、眼下に広がる荒涼たる砂の大地を紅に染め上げた日暮れだった。