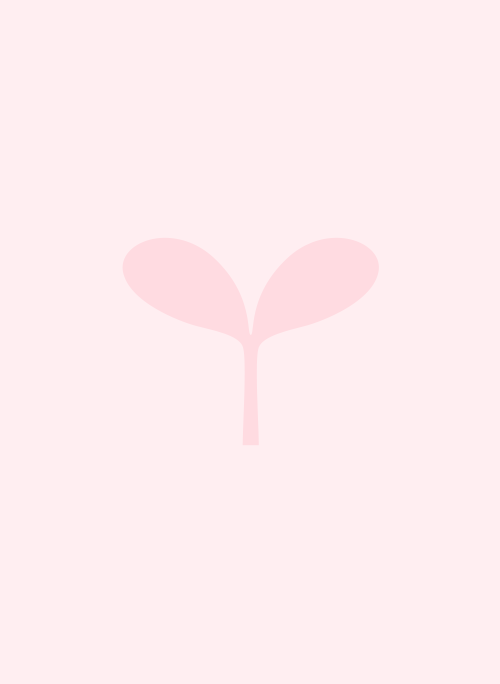「飲み物って……」
慣れた手つきでカップの中にミルクやはちみつを加え、熱せられた暖炉の縁にそれらの入った陶器のカップを置くキリを、ラグナードは信じられない気分で見つめた。
「まさか、卵か? 卵なのか?」
「卵だよ」
暖炉の熱で温められ始めた卵をスプーンでかき混ぜながら、キリがこくんとうなずいた。
「あれ? 飲まないの? おいしいよ」
「……俺はいい」
卵が食べ物ではなく飲み物として出てくるとは、とんでもない家に迷い込んだとラグナードは思った。
それとも魔法使いの間では、客人をもてなす時にはこれが普通なのだろうか。
そんなことを考えかけて、いやいやばかな、と否定する。
ここに来るまでに何人か魔法使いを訪ね歩いたが、こんな飲み物を勧めてきた者は誰もいなかった。
この娘がおかしいのだ。
押し黙ったまま、少女のピンク色の髪をにらみつけて彼はそう結論づけた。
キリは不思議そうな顔をして、温まってとろりとした卵入りのカップを暖炉から下ろし、テーブルの上に戻した。
はちみつとミルク、卵が混ざった甘い香りが部屋の中に漂った。
ラグナードの胸に驚愕が広がる。
温められたその飲み物は、最初の印象とずいぶん違って見え、菓子かケーキのような甘い香りは、ヒカリダケしか食べていない空きっ腹にはこたえた。
不覚にもおいしそうだと思ってしまったところに、
「おいしいよ?」
笑顔でもう一度繰り返されて、
「……気が変わった。俺も一杯もらおうか」
そっぽを向いてラグナードはそう言った。
うれしそうな顔をして、キリが「どうぞ」と自分が用意した飲み物をラグナードの空のカップと入れ替えた。
あらためて自分の分を用意し始めた少女をながめつつ、目の前に置かれたその飲み物を口に運び──
おそるおそるカップに口をつけて一口含み、彼は軽く感動を覚えた。
優しい甘さは疲れ切った体に染みこむようで、実にうまかった。
「なるほど、溶かしたプディングのようなものだな」
つぶやいたラグナードを見て、キリがほほえんだ。
「どっちかと言うと、固める前のプディングかな」
慣れた手つきでカップの中にミルクやはちみつを加え、熱せられた暖炉の縁にそれらの入った陶器のカップを置くキリを、ラグナードは信じられない気分で見つめた。
「まさか、卵か? 卵なのか?」
「卵だよ」
暖炉の熱で温められ始めた卵をスプーンでかき混ぜながら、キリがこくんとうなずいた。
「あれ? 飲まないの? おいしいよ」
「……俺はいい」
卵が食べ物ではなく飲み物として出てくるとは、とんでもない家に迷い込んだとラグナードは思った。
それとも魔法使いの間では、客人をもてなす時にはこれが普通なのだろうか。
そんなことを考えかけて、いやいやばかな、と否定する。
ここに来るまでに何人か魔法使いを訪ね歩いたが、こんな飲み物を勧めてきた者は誰もいなかった。
この娘がおかしいのだ。
押し黙ったまま、少女のピンク色の髪をにらみつけて彼はそう結論づけた。
キリは不思議そうな顔をして、温まってとろりとした卵入りのカップを暖炉から下ろし、テーブルの上に戻した。
はちみつとミルク、卵が混ざった甘い香りが部屋の中に漂った。
ラグナードの胸に驚愕が広がる。
温められたその飲み物は、最初の印象とずいぶん違って見え、菓子かケーキのような甘い香りは、ヒカリダケしか食べていない空きっ腹にはこたえた。
不覚にもおいしそうだと思ってしまったところに、
「おいしいよ?」
笑顔でもう一度繰り返されて、
「……気が変わった。俺も一杯もらおうか」
そっぽを向いてラグナードはそう言った。
うれしそうな顔をして、キリが「どうぞ」と自分が用意した飲み物をラグナードの空のカップと入れ替えた。
あらためて自分の分を用意し始めた少女をながめつつ、目の前に置かれたその飲み物を口に運び──
おそるおそるカップに口をつけて一口含み、彼は軽く感動を覚えた。
優しい甘さは疲れ切った体に染みこむようで、実にうまかった。
「なるほど、溶かしたプディングのようなものだな」
つぶやいたラグナードを見て、キリがほほえんだ。
「どっちかと言うと、固める前のプディングかな」