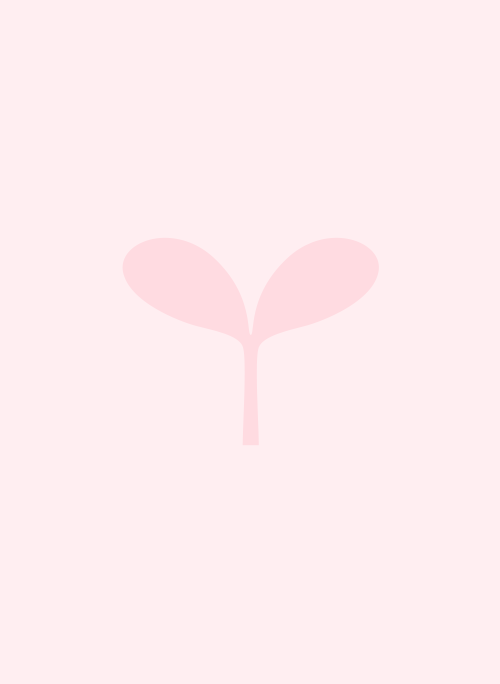「なに?」
と、アルシャラは眉をはね上げて、
目の前の魔法使いの魂胆に気づいた。
「それであんた、俺様をけしかけようってのか」
「まあな。
常に旅ばかりしていて居場所のはっきりしない魔法使いに杖を持ち逃げされるのは困る。
下手をすればヴェズルングの杖は永遠に行方知れずになっちまうからな」
ル・ルーはすんなりと認めて、にやにやした笑いをうかべた。
「俺が教国の命令で、ガルナティスの内情を探るなんて退屈な任務についてる理由の半分は、ヴェズルングの杖だからな」
「理由の半分ねえ」
と言って、アルシャラもまた端正な顔ににやにやした笑みを作った。
「もう半分の理由ってのは何なんだ?」
「ガルナティス王国そのものに対する興味さ」
ル・ルーはうっそうとしげる初夏の森を見回した。
頭上にういた魔法の光源は周囲を真昼のごとく照らしているが、
視界の端には、光が届かず夜の森の闇にしずんだ木々が見えている。
「ガルナティス王国は、異常な国だ」
と、ル・ルーは言った。
「俺はな、魔法使いであることに誇りを持っているし、魔法使いの力というものを誇りに思っている。
かつて魔法使いの国が世界を支配したのは、当然のことだと思ってる。
その神聖エスメラルダが、ただの人間の国に滅ぼされたという歴史を知ったときは、どうしても納得できなかった。
今も──納得していない」
「そいつは……魔法使いであれば誰もが一度は感じる、人間側の勝利に対するヒガミみたいなもんだろ」
「かもな。
だが、ガルナティスはエスメラルダを滅ぼしただけじゃない。
争いが絶えないこの血の大陸にあって、千年間もこれだけの国土を維持したまま栄えつづけた国は一つもない。
ガルナティス王国以外に、一つもないんだ」
ル・ルーの話を聞いて、
アルシャラは「そう言えばそうだな」とつぶやいた。
「人間が勝てるはずのない魔法の国に勝利し、まるで『滅びることを許されないかのように』繁栄し続けるこの国はなんだ?
なぜ、『もともと神聖エスメラルダの貴族だった』ヴェズルングは、ガルナティスの反乱に協力したんだ?
この国には、なにか秘密がある。
歴史の表では語られることのない秘密がな」
木々の奥に広がる闇を見つめて、ル・ルーはしのびやかに笑いをもらした。
「偵察任務の合間に王家のことを調べてみたら、奇妙なことがわかったよ。
過去、ガルナティスで即位した王のうち、国を滅ぼしてもおかしくなかった暴君や愚君は、『一人残らず』早世していた。
それこそ──誰かに暗殺でもされたかのようにな」
「ああ、そんなうわさを聞いたことがあるな」
アルシャラも、暗い森の木々の向こうに視線を投げる。
「王家に伝わる怪談の一つだ」
アルシャラはそう言って、
こうこうと輝く明かりにはっきりと照らし出されたル・ルーの顔をながめた。
「まあ、俺様もヴェズルングの杖を他のやつに渡すつもりはねえけどな。
あんたが杖を手に入れたら、あんたを食って殺すついでにいただこうかと思ってたんだが──居場所がわからねえレイヴンが持って行っちまうのは、ちょいと困るねェ」
「俺の魔法を食うつもりなのか。なまいきな」
ル・ルーはおかしそうに笑った。
「毒のシムノンにこてんぱんにやられたやつが。
言葉どおり、百年早い」
「さっきの話だと、あんただってシムノンには勝てなかったんだろ」
「十年前の話だ」
ル・ルーはすました顔でそう返して、「おまえはわかってないようだけどな」と続けた。
「シムノンの毒の属性というのはな、ただ人を殺すという用途のみに限定するならば、俺やおまえや、ミレイ猊下に匹敵する攻撃力を誇るんだ。
俺や猊下の魔法のようにこうして明かりを作ったり、おまえの炎のように暖を取ったりなんていう使い道すらもない、完全な殺人用途の属性という意味では、より凶悪と言っていい」
「なるほどね。エスメラルダの賢者様よりは、『暗殺者や密偵』なんかにぴったりの属性ってわけだ」
「そういうことだな」
「ところで──」
アルシャラは、
かたわらに置かれていた自分の杖を拾い上げて片目をつぶった。
「おい」
「ああ」
「ル・ルー、あんた──つけられたな」
ふふ、と木の根に座ったままル・ルーが笑った。
「仕方あるまい。
おまえの杖と違って、飛行騎杖での移動は目立つんだ」
「『森の虫の声を止める』なんざ、相手もマヌケな密偵みてえだけどな」
そう言って、
アルシャラは『先刻からずっと虫の音ひとつなく静まりかえったまま』の森に、ぐるりと視線をめぐらせた。
「さて、どうしたものかな?」
ル・ルーがにやにや笑い、
「こうしてバッチリ顔をさらした状態で、
俺の本名も、
俺がエスメラルダの任務でガルナティスに潜りこんでいることも、
ついでに俺がガルナティス王国にいる個人的な目的まで話してしまったわけだ」
「あんた、それ全部わざとだろ」
アルシャラもにたついた。
「まあ、月並みだが──」
と言って、
楽団の指揮者がタクトをふるように、ル・ルーが片手をついっと上げる。
「どこの誰だか知らないが、このまま返すわけにはゆかないな」
瞬間、
二人の近くの木の後ろから人影が飛び出し、
一瞬で森の闇の奥へと身をひるがえして消えた。
「あーらら、逃げちゃったぞ」
とアルシャラ。
「逃がしてやるさ」
とル・ルー。
「俺が呪文を唱え終えるまでな」
雷光を操る魔法使いの口が、
ぶきみな言葉の羅列をつむぎ始める──。
と、アルシャラは眉をはね上げて、
目の前の魔法使いの魂胆に気づいた。
「それであんた、俺様をけしかけようってのか」
「まあな。
常に旅ばかりしていて居場所のはっきりしない魔法使いに杖を持ち逃げされるのは困る。
下手をすればヴェズルングの杖は永遠に行方知れずになっちまうからな」
ル・ルーはすんなりと認めて、にやにやした笑いをうかべた。
「俺が教国の命令で、ガルナティスの内情を探るなんて退屈な任務についてる理由の半分は、ヴェズルングの杖だからな」
「理由の半分ねえ」
と言って、アルシャラもまた端正な顔ににやにやした笑みを作った。
「もう半分の理由ってのは何なんだ?」
「ガルナティス王国そのものに対する興味さ」
ル・ルーはうっそうとしげる初夏の森を見回した。
頭上にういた魔法の光源は周囲を真昼のごとく照らしているが、
視界の端には、光が届かず夜の森の闇にしずんだ木々が見えている。
「ガルナティス王国は、異常な国だ」
と、ル・ルーは言った。
「俺はな、魔法使いであることに誇りを持っているし、魔法使いの力というものを誇りに思っている。
かつて魔法使いの国が世界を支配したのは、当然のことだと思ってる。
その神聖エスメラルダが、ただの人間の国に滅ぼされたという歴史を知ったときは、どうしても納得できなかった。
今も──納得していない」
「そいつは……魔法使いであれば誰もが一度は感じる、人間側の勝利に対するヒガミみたいなもんだろ」
「かもな。
だが、ガルナティスはエスメラルダを滅ぼしただけじゃない。
争いが絶えないこの血の大陸にあって、千年間もこれだけの国土を維持したまま栄えつづけた国は一つもない。
ガルナティス王国以外に、一つもないんだ」
ル・ルーの話を聞いて、
アルシャラは「そう言えばそうだな」とつぶやいた。
「人間が勝てるはずのない魔法の国に勝利し、まるで『滅びることを許されないかのように』繁栄し続けるこの国はなんだ?
なぜ、『もともと神聖エスメラルダの貴族だった』ヴェズルングは、ガルナティスの反乱に協力したんだ?
この国には、なにか秘密がある。
歴史の表では語られることのない秘密がな」
木々の奥に広がる闇を見つめて、ル・ルーはしのびやかに笑いをもらした。
「偵察任務の合間に王家のことを調べてみたら、奇妙なことがわかったよ。
過去、ガルナティスで即位した王のうち、国を滅ぼしてもおかしくなかった暴君や愚君は、『一人残らず』早世していた。
それこそ──誰かに暗殺でもされたかのようにな」
「ああ、そんなうわさを聞いたことがあるな」
アルシャラも、暗い森の木々の向こうに視線を投げる。
「王家に伝わる怪談の一つだ」
アルシャラはそう言って、
こうこうと輝く明かりにはっきりと照らし出されたル・ルーの顔をながめた。
「まあ、俺様もヴェズルングの杖を他のやつに渡すつもりはねえけどな。
あんたが杖を手に入れたら、あんたを食って殺すついでにいただこうかと思ってたんだが──居場所がわからねえレイヴンが持って行っちまうのは、ちょいと困るねェ」
「俺の魔法を食うつもりなのか。なまいきな」
ル・ルーはおかしそうに笑った。
「毒のシムノンにこてんぱんにやられたやつが。
言葉どおり、百年早い」
「さっきの話だと、あんただってシムノンには勝てなかったんだろ」
「十年前の話だ」
ル・ルーはすました顔でそう返して、「おまえはわかってないようだけどな」と続けた。
「シムノンの毒の属性というのはな、ただ人を殺すという用途のみに限定するならば、俺やおまえや、ミレイ猊下に匹敵する攻撃力を誇るんだ。
俺や猊下の魔法のようにこうして明かりを作ったり、おまえの炎のように暖を取ったりなんていう使い道すらもない、完全な殺人用途の属性という意味では、より凶悪と言っていい」
「なるほどね。エスメラルダの賢者様よりは、『暗殺者や密偵』なんかにぴったりの属性ってわけだ」
「そういうことだな」
「ところで──」
アルシャラは、
かたわらに置かれていた自分の杖を拾い上げて片目をつぶった。
「おい」
「ああ」
「ル・ルー、あんた──つけられたな」
ふふ、と木の根に座ったままル・ルーが笑った。
「仕方あるまい。
おまえの杖と違って、飛行騎杖での移動は目立つんだ」
「『森の虫の声を止める』なんざ、相手もマヌケな密偵みてえだけどな」
そう言って、
アルシャラは『先刻からずっと虫の音ひとつなく静まりかえったまま』の森に、ぐるりと視線をめぐらせた。
「さて、どうしたものかな?」
ル・ルーがにやにや笑い、
「こうしてバッチリ顔をさらした状態で、
俺の本名も、
俺がエスメラルダの任務でガルナティスに潜りこんでいることも、
ついでに俺がガルナティス王国にいる個人的な目的まで話してしまったわけだ」
「あんた、それ全部わざとだろ」
アルシャラもにたついた。
「まあ、月並みだが──」
と言って、
楽団の指揮者がタクトをふるように、ル・ルーが片手をついっと上げる。
「どこの誰だか知らないが、このまま返すわけにはゆかないな」
瞬間、
二人の近くの木の後ろから人影が飛び出し、
一瞬で森の闇の奥へと身をひるがえして消えた。
「あーらら、逃げちゃったぞ」
とアルシャラ。
「逃がしてやるさ」
とル・ルー。
「俺が呪文を唱え終えるまでな」
雷光を操る魔法使いの口が、
ぶきみな言葉の羅列をつむぎ始める──。