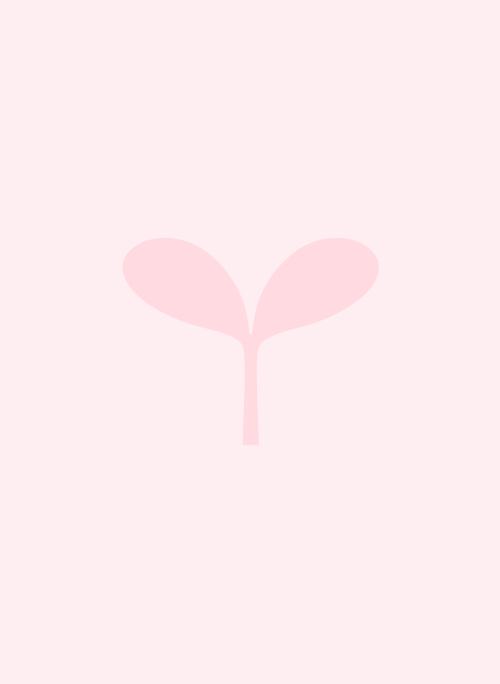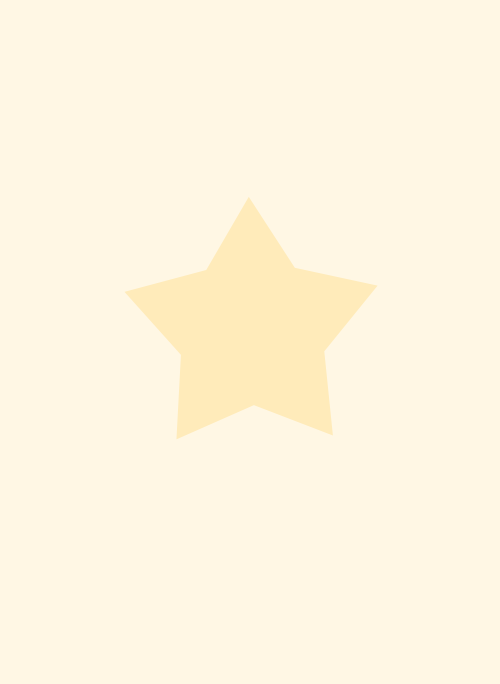出会った夜にラグナードが、
『俺のこの容姿は王族とはほど遠い』
とリンガー・レクスで口にしていたことや、
幼いころ彼は体が弱くてお姫様として育てられていたと語ったことや、
彼の外見からは、どこか虚弱でひ弱そうな温室育ちの印象を受けたことを、キリは思い出した。
「病弱な体質は、ガルナティスの王位を継承する者にとってはそれだけで汚点なんだ。
姫として育てられていたなど──」
はっ、とラグナードは短く息をはき出して乾いた声で笑って、「いい笑いの種だ」と言った。
キリは衝撃を受けながら「汚点……」と、ラグナードが口にした言葉をくり返した。
「女だろうが、男だろうが関係ない。
ガルナティスでは民衆も、諸侯も、
焔狼王の築いた国を継ぐ烈火のごとき強い王を望む。
そして──」
ラグナードは、
自虐的で悲痛な笑いをはりつかせたまま、瞑目した。
「今の陛下は──姉上は──ガルナティス国王として完璧だ。完璧すぎる」
キリはそうかと思った。
国王と謁見したときのラグナードとイルムガンドルのやりとりの謎がとけた。
赤毛の者を皇太子にすればいいと言ったラグナードには、
この王家に生まれた者ゆえの、己の外見と病弱な過去に対する強烈なコンプレックスがあったのだ。
新たな王が立てば、誰もが先王と比較する。
完璧すぎる王の次に玉座に着く者には、大きな重圧がのしかかるのである。
確かに、
イルムガンドルの深紅の髪と、
鋼鉄のような眼光には、
女王とは言え、いかにもこの肖像画の青年を思わせる、焔狼の一族の風格がみなぎっていた。
「でも──」とキリは納得がゆかずに口を開いた。
「見た目や体質なんて、生まれつきなんだからしかたないよ。
王様にふさわしいかどうかに、そんなことまで求められるなんて……変なの」
キリはなんだかせつなくなって、
すみれ色の綺麗な瞳や、
やさしい色合いのプラチナブロンドや、
はかなげな白い肌を見つめた。
女の子なら誰でも見とれるような美しいこの姿も、彼自身は嫌いで、
この国の王子様に生まれてしまったせいで自分を好きになれないのだということが、キリにはとても悲しかった。
「わたしは素敵だと思うけどなあ。
ラグナードの髪や瞳の色、好きだよ?」
ラグナードは思わずキリの顔を見て、
彼を見上げる大きなエメラルドの瞳と目が合って、どきりとして──
フン、と鼻を鳴らして目をそらした。
「それでなぐさめているつもりか?」
不覚にも心臓がさわいだことをごまかすように、
ラグナードはあしざまにあざわらった。
「しょせん、お前のような庶民には理解できないだろう」
あんまりな反応が返ってきて、ぶー、とキリがふくれた。
「だいたい、いくら赤い髪の王様の子孫だからって、そんなに赤毛ばっかり生まれるわけがないよ。
お后様には、金髪や、黒髪や、茶色い髪の人だっていたわけでしょ?」
キリは、ブラウンの髪をしたラグナードの母親を脳裏に描いて、
少し気むずかしそうな顔をした絵の中の王様に視線をもどした。
「千年の間には、ラグナードみたいな髪の人もほかにもいたんじゃないの?」
普通は、生まれてくる子供は両親に似るものだから、
赤毛の片親にばかり似た子供がずっと生まれ続けるなどあり得ないことである。
しかし、「いない」と、ラグナードは断言した。
「記録に残っているこの国の王族の髪はすべて赤だ」
ラグナードはあり得ない事実を告げてから、
ふと──王家に伝わる奇妙なうわさを思い出した。
「もっとも、記録に残っていないだけかもしれないが」
ガルナティスの王家には
存在しない回廊の話とはまた別の、怪談とも呼べる不気味な言い伝えが一つあった。
「この王家で金髪や黒髪に生まれた者は皆、歴史から消されてきたのかもしれないな」
「え?」
「だとすれば、俺も……」
そう言って、
長いまつげをふせ、ラグナードは黙った。
「まるで呪いのようだな」
と、黙っていたジークフリートも不穏当な言葉を口にした。
「はにゃ? 呪い?」
「たとえばこの初代国王に魔法で『そういう』呪いをかければ、伴侶の髪の色がどうであれ、子々孫々まで生まれてくる王族の子供をすべて赤毛にすることもたやすいが……」
「赤毛にする呪いって──」
キリは目をまたたいた。
滑稽(こっけい)すぎる呪いに思えた。
「──そんなことして、なんの意味があるの?」
「無意味だな。いやがらせにもならん」
ジークフリートが肩をすくめる──代わりに羽を動かした。
「フェンリスヴォルフ一世の髪の色に無礼なことを言うな」と、ラグナードが顔をしかめた。
「呪いかあ……」
キリは口の中でつぶやいた。
それにしても、赤い髪の人間ばかり生まれる王家など、
呪いがかかっているとでも考えなければ、なんとも変な話である。
国民が千年間も赤い髪を信奉して、ラグナードのようにそのせいで苦しむ子孫がいるというのは、
ある意味、この初代国王が遺した呪いとも言える気はしたが。
赤い髪の王様の絵をしげしげと見上げて、
「そう言えばこの王様って、なんだかラグナードに似てるみたい?」
と、キリは言った。
『俺のこの容姿は王族とはほど遠い』
とリンガー・レクスで口にしていたことや、
幼いころ彼は体が弱くてお姫様として育てられていたと語ったことや、
彼の外見からは、どこか虚弱でひ弱そうな温室育ちの印象を受けたことを、キリは思い出した。
「病弱な体質は、ガルナティスの王位を継承する者にとってはそれだけで汚点なんだ。
姫として育てられていたなど──」
はっ、とラグナードは短く息をはき出して乾いた声で笑って、「いい笑いの種だ」と言った。
キリは衝撃を受けながら「汚点……」と、ラグナードが口にした言葉をくり返した。
「女だろうが、男だろうが関係ない。
ガルナティスでは民衆も、諸侯も、
焔狼王の築いた国を継ぐ烈火のごとき強い王を望む。
そして──」
ラグナードは、
自虐的で悲痛な笑いをはりつかせたまま、瞑目した。
「今の陛下は──姉上は──ガルナティス国王として完璧だ。完璧すぎる」
キリはそうかと思った。
国王と謁見したときのラグナードとイルムガンドルのやりとりの謎がとけた。
赤毛の者を皇太子にすればいいと言ったラグナードには、
この王家に生まれた者ゆえの、己の外見と病弱な過去に対する強烈なコンプレックスがあったのだ。
新たな王が立てば、誰もが先王と比較する。
完璧すぎる王の次に玉座に着く者には、大きな重圧がのしかかるのである。
確かに、
イルムガンドルの深紅の髪と、
鋼鉄のような眼光には、
女王とは言え、いかにもこの肖像画の青年を思わせる、焔狼の一族の風格がみなぎっていた。
「でも──」とキリは納得がゆかずに口を開いた。
「見た目や体質なんて、生まれつきなんだからしかたないよ。
王様にふさわしいかどうかに、そんなことまで求められるなんて……変なの」
キリはなんだかせつなくなって、
すみれ色の綺麗な瞳や、
やさしい色合いのプラチナブロンドや、
はかなげな白い肌を見つめた。
女の子なら誰でも見とれるような美しいこの姿も、彼自身は嫌いで、
この国の王子様に生まれてしまったせいで自分を好きになれないのだということが、キリにはとても悲しかった。
「わたしは素敵だと思うけどなあ。
ラグナードの髪や瞳の色、好きだよ?」
ラグナードは思わずキリの顔を見て、
彼を見上げる大きなエメラルドの瞳と目が合って、どきりとして──
フン、と鼻を鳴らして目をそらした。
「それでなぐさめているつもりか?」
不覚にも心臓がさわいだことをごまかすように、
ラグナードはあしざまにあざわらった。
「しょせん、お前のような庶民には理解できないだろう」
あんまりな反応が返ってきて、ぶー、とキリがふくれた。
「だいたい、いくら赤い髪の王様の子孫だからって、そんなに赤毛ばっかり生まれるわけがないよ。
お后様には、金髪や、黒髪や、茶色い髪の人だっていたわけでしょ?」
キリは、ブラウンの髪をしたラグナードの母親を脳裏に描いて、
少し気むずかしそうな顔をした絵の中の王様に視線をもどした。
「千年の間には、ラグナードみたいな髪の人もほかにもいたんじゃないの?」
普通は、生まれてくる子供は両親に似るものだから、
赤毛の片親にばかり似た子供がずっと生まれ続けるなどあり得ないことである。
しかし、「いない」と、ラグナードは断言した。
「記録に残っているこの国の王族の髪はすべて赤だ」
ラグナードはあり得ない事実を告げてから、
ふと──王家に伝わる奇妙なうわさを思い出した。
「もっとも、記録に残っていないだけかもしれないが」
ガルナティスの王家には
存在しない回廊の話とはまた別の、怪談とも呼べる不気味な言い伝えが一つあった。
「この王家で金髪や黒髪に生まれた者は皆、歴史から消されてきたのかもしれないな」
「え?」
「だとすれば、俺も……」
そう言って、
長いまつげをふせ、ラグナードは黙った。
「まるで呪いのようだな」
と、黙っていたジークフリートも不穏当な言葉を口にした。
「はにゃ? 呪い?」
「たとえばこの初代国王に魔法で『そういう』呪いをかければ、伴侶の髪の色がどうであれ、子々孫々まで生まれてくる王族の子供をすべて赤毛にすることもたやすいが……」
「赤毛にする呪いって──」
キリは目をまたたいた。
滑稽(こっけい)すぎる呪いに思えた。
「──そんなことして、なんの意味があるの?」
「無意味だな。いやがらせにもならん」
ジークフリートが肩をすくめる──代わりに羽を動かした。
「フェンリスヴォルフ一世の髪の色に無礼なことを言うな」と、ラグナードが顔をしかめた。
「呪いかあ……」
キリは口の中でつぶやいた。
それにしても、赤い髪の人間ばかり生まれる王家など、
呪いがかかっているとでも考えなければ、なんとも変な話である。
国民が千年間も赤い髪を信奉して、ラグナードのようにそのせいで苦しむ子孫がいるというのは、
ある意味、この初代国王が遺した呪いとも言える気はしたが。
赤い髪の王様の絵をしげしげと見上げて、
「そう言えばこの王様って、なんだかラグナードに似てるみたい?」
と、キリは言った。