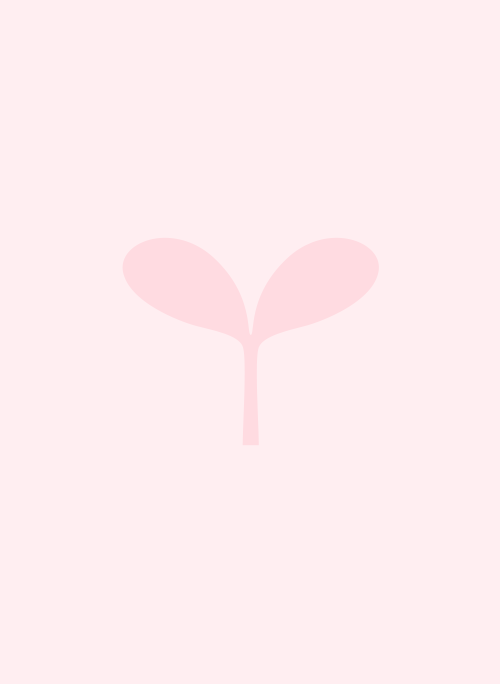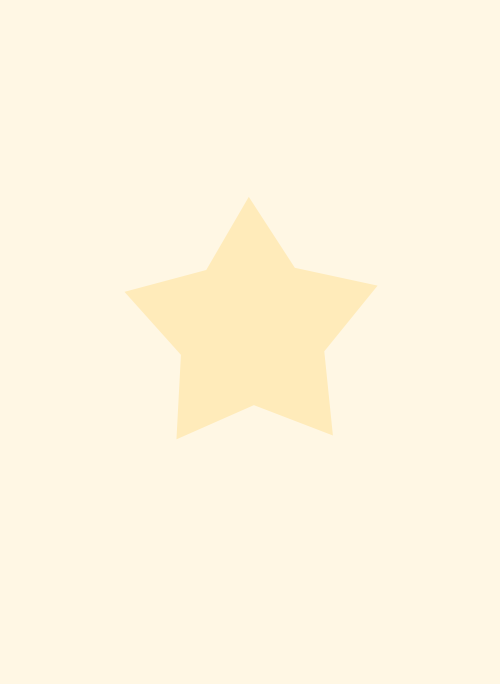この二十年の間、
エスメラルダでは毎年大ごもりの晩のたび、魔法使いが一人ずつ消えるという奇怪な事件が続いていた。
彼らがどんな末路をたどったのか、
その犯人が、何の目的に彼らを使ったのか、
堕落の極みともいうべき凄絶(せいぜつ)な部屋の中には、一目瞭然にその答えを指し示す無惨な物体が大量に存在した。
エスメラルダを震撼(しんかん)させる、世紀の大スキャンダルであった。
エスメラルダは【至極のシムノン】の二つ名と枢機卿の地位を彼から永遠に剥奪し、
【毒のシムノン】をエスメラルダの大罪人として、生死問わずのおたずね者にして追っ手を差し向けた。
けれども、
骨の髄(ずい)まで腐っていても、皮肉にも相手はエスメラルダの枢機卿の座までのぼりつめた大賢者。
さらに悪いことに、
あたかも自らの属性であるかのように、子供を操って霧の魔法を自在に使う彼を、
捕縛はおろか殺すことのできる魔法使いはエスメラルダにすら皆無だった。
奇しくも、エスメラルダにとってシムノンは、千年前の霧のヴェズルングとまったく同様の敵となったのだ。
こうして、
世界を点々としながら追っ手を振り切り続けてまんまとシムノンは逃げおおせ、
そしてついに、その夜は訪れる。
旅人一人立ち入らぬ、ゴンドワナ大陸の大森林の奥地で──。
あの夜が来るまでの子供時代の記憶は、彼女にとって思い出したくもないものだった。
どこかから、他のたくさんの子供と一緒にさらわれてきた。
幼い彼女が、唯一理解できたのはそれだけで、
わけがわからぬままに、
空を飛ぶ杖に乗せられ、空に浮かぶ町に連れて来られた。
のちに、月白のミレイという名だということを知ったが、彼女をさらってきたのはまっ白な魔法使いで、
それでもその魔法使いは優しい人だった。
ミレイのもとにいた間は、まだ幸せだったのだ。
エリゼ・ド・シムノン。
その物語に登場するような腰の曲がった白髪の老人の魔法使いにひきとられてから、彼女はそれをいやというほど思い知った。
魔法使いの弟子にしてやるという甘い言葉は大ウソで、
このおそろしい老人にひきとられてからの一年間、
育ち盛りの子供であったにもかかわらず、彼女は奴隷のようにろくに食事も与えられず、
ありとあらゆる雑用を押しつけられ、
小さな失敗を一つでもやらかそうものならば鞭で打たれ、
そして雑用以外の時間には、妙な魔法をかけられて、
自らの意志で体を動かすこともしゃべることもさせてもらえなかった。
老人はまるでなにかにとりつかれてでもいるように、
いつも飢えた獣のようなギラギラとした異様な光を、おちくぼんだ両目にみなぎらせていた。
エスメラルダでは毎年大ごもりの晩のたび、魔法使いが一人ずつ消えるという奇怪な事件が続いていた。
彼らがどんな末路をたどったのか、
その犯人が、何の目的に彼らを使ったのか、
堕落の極みともいうべき凄絶(せいぜつ)な部屋の中には、一目瞭然にその答えを指し示す無惨な物体が大量に存在した。
エスメラルダを震撼(しんかん)させる、世紀の大スキャンダルであった。
エスメラルダは【至極のシムノン】の二つ名と枢機卿の地位を彼から永遠に剥奪し、
【毒のシムノン】をエスメラルダの大罪人として、生死問わずのおたずね者にして追っ手を差し向けた。
けれども、
骨の髄(ずい)まで腐っていても、皮肉にも相手はエスメラルダの枢機卿の座までのぼりつめた大賢者。
さらに悪いことに、
あたかも自らの属性であるかのように、子供を操って霧の魔法を自在に使う彼を、
捕縛はおろか殺すことのできる魔法使いはエスメラルダにすら皆無だった。
奇しくも、エスメラルダにとってシムノンは、千年前の霧のヴェズルングとまったく同様の敵となったのだ。
こうして、
世界を点々としながら追っ手を振り切り続けてまんまとシムノンは逃げおおせ、
そしてついに、その夜は訪れる。
旅人一人立ち入らぬ、ゴンドワナ大陸の大森林の奥地で──。
あの夜が来るまでの子供時代の記憶は、彼女にとって思い出したくもないものだった。
どこかから、他のたくさんの子供と一緒にさらわれてきた。
幼い彼女が、唯一理解できたのはそれだけで、
わけがわからぬままに、
空を飛ぶ杖に乗せられ、空に浮かぶ町に連れて来られた。
のちに、月白のミレイという名だということを知ったが、彼女をさらってきたのはまっ白な魔法使いで、
それでもその魔法使いは優しい人だった。
ミレイのもとにいた間は、まだ幸せだったのだ。
エリゼ・ド・シムノン。
その物語に登場するような腰の曲がった白髪の老人の魔法使いにひきとられてから、彼女はそれをいやというほど思い知った。
魔法使いの弟子にしてやるという甘い言葉は大ウソで、
このおそろしい老人にひきとられてからの一年間、
育ち盛りの子供であったにもかかわらず、彼女は奴隷のようにろくに食事も与えられず、
ありとあらゆる雑用を押しつけられ、
小さな失敗を一つでもやらかそうものならば鞭で打たれ、
そして雑用以外の時間には、妙な魔法をかけられて、
自らの意志で体を動かすこともしゃべることもさせてもらえなかった。
老人はまるでなにかにとりつかれてでもいるように、
いつも飢えた獣のようなギラギラとした異様な光を、おちくぼんだ両目にみなぎらせていた。