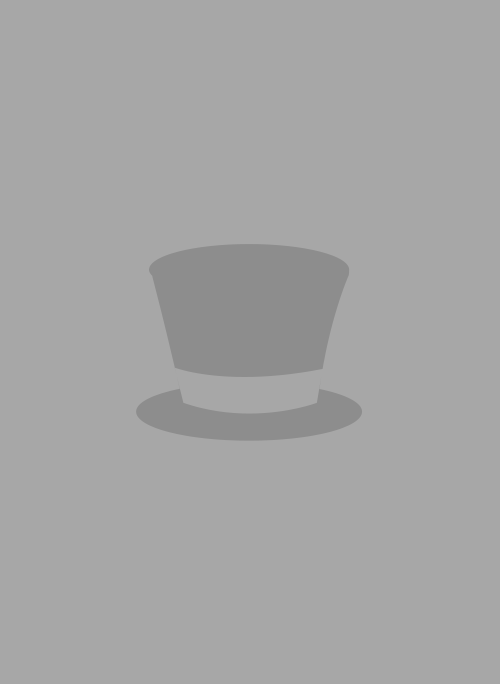それでも――――私は、
気付くと視界がぼんやりと滲んでいた。
目に盛り上がってくる思いの雨は止めることが出来ず、セルマはそのまま家を飛び出した。
「セルマ! どこにいくの?」
何かを恐れるような叫びも無視して、走った。
森は生まれた時からの棲みか。
庭といっても差し支えない。
何も考えないで走っていても、足はいつもの場所へと自らを運んだ。
草花の為にあるような、少しだけ開けたこの場所。
何かあるといつもここへ来ては、太陽の光を浴びた。
傾きかけた今では、もう月光のが近いかもしれない。
セルマは丸いその場の中心で、がっくりと膝を下ろした。