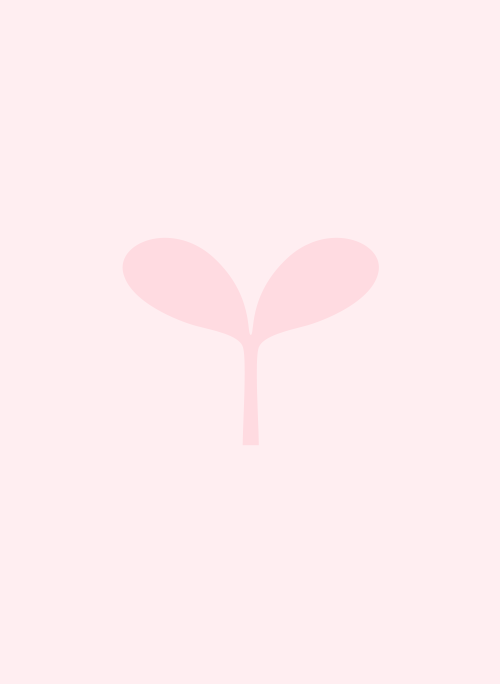偶然見つけたバイクは、いい仕事をしてくれた。確かに十番地までは、バイクで走らせても三十分近くかかるほど遠い。それに、ガイの言うとおり、ガソリンも残り僅かだ。水すら満足に得られないこの辺りで、ガソリンが手に入るなんてことは不可能である。ガソリンがなくなれば、きっと今まで仏を見るような目でバイクを見ていた連中も、しれっとした顔で解体し、瓦礫の山に積むのだろう。そうなれば、足は自分らの持つ二本の足のみになる。そうして、あのバイクのことを、それは大切に、子供のように扱ってきたことなど忘れて過ごし始めるのだろう。
もし、災厄が訪れていなければ、バイクが使えなくなったとしても、さほど真剣に考えはしなかっただろう。壊れたら次を求めればいい。彼らが喜んでいるのは、ガソリンがなくなり、いずれは解体されてしまうだろうバイクの寿命を縮めなくてすんだことに喜んでいるのではない。水場が近くなり、自分らの苦労が減ることに喜びの声をあげているのだ。なぜかはわからないが、俺はそのことに無性に苛々した。物を大切にするほうでも、進んで人助けをするような殊勝な人間でもない。そんな俺が、何に腹を立てているのか、自分自身でもよくわからず、わからないことが余計に俺を苛々させていた。
「でも三番地か……。素直にわけてくれればいいけどな」
ガイが防塵マスクの奥で呟き、俺も「そうだな」と曖昧な返事をすると、そのまま三番地の方角へと視線を送る。
災厄の日以降、土地以上に人々が荒れた。咎める法もなければそれを執行する人間もいない。盗みや殺人を犯したところで、裁く者がいなければ、こうも簡単に人間は堕ちてしまうのだ。もちろん、まっとうな人間がこの辺りでも多いのはよく知っている。けれど、三番地という場所は、荒れた者が多く集う場所でもあった。自分が生き延びるために、平気で盗みも人殺しも行えるのだ。