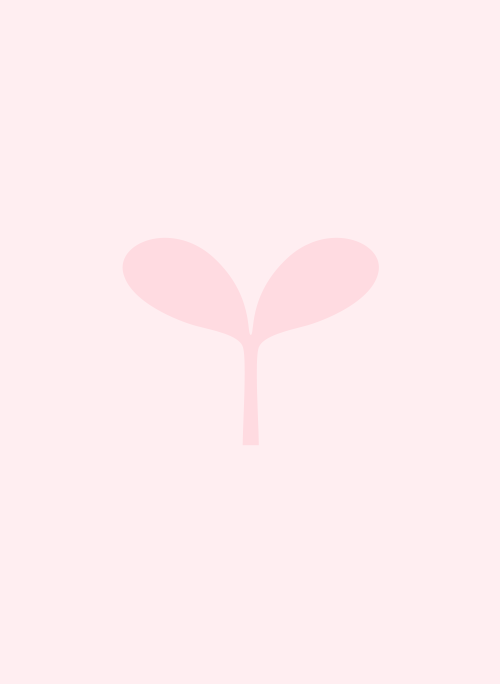周りの話によれば、荒地になるまで数日の間があったという。
その間目を覚まさなかった自分にも驚くが、その間は絵地獄そのものだったらしい。倒壊した家々からは炎が立ち上り、火の粉が舞う。海は荒れ、逃げ惑う人々をいとも簡単に飲み込んだ。それは子供の頃に砂場で蟻地獄に砂をかけて遊んだ残酷さにも似ている。自然とは、時にむごい仕打ちを俺らに与える。
けれど、俺らは生きている。ならば、生きなくてはいけない。どんな状況であっても、生きようと努力しなくてはならない。こんな状況になるまで、生きていくことに「努力する」なんて考えたこともなかった。起きて食事を摂り、好きな時間に眠り好きな時間に用を足す。当たり前のようで、今はとても難しい。
「よお、アキラ。使えそうなものはあったか?」
目から口元までをしっかりと覆う防塵マスクをつけたまま、俺は振り返らずに手振りを付けて肩をすくめてみせた。
倒壊した家やビル、それらの破片があちらこちらに散らばり、俺らはその中から使えそうなものを探して生活している。今にも風に吹かれてしまいそうなテントの背後には、集めてきたガラクタが山のように積んであった。俺に声をかけた男は、山になったガラクタから使えそうなものを探しているのだろう。がちゃがちゃと忙しなく落ち着きのない音をたてている。