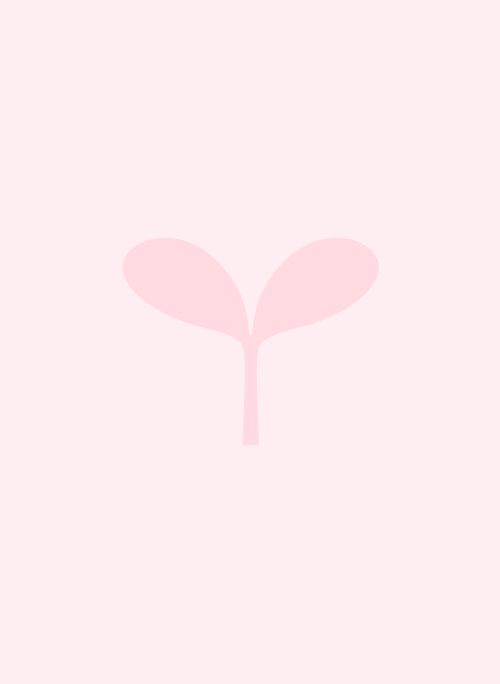「明日からはまた十番地の水を汲みに行くしかないな。アキラもこんなんだし、しばらくは俺が行くか」
不満そうに舌打ちをし、振り返ったガイは意外にも清々しい笑顔を浮かべていた。白い歯を見せ、再び前を向いた。
「悪いな」
「悪いと思うならあまりみんなに心配かけさせるようなことするなよ。あいつらも俺も今はみんな家族みたいなもんだろう」
「そうだな……」
傷が疼いた。その痛みは、俺への罰かもしれない。今まで彼らの中から安心感を探そうともしなかった。自分から歩み寄ろうとしなければ、そんなものが見つかるはずもないというのに。
彼らが俺を心配してくれたように、俺もまた彼らを大切にしていきたいと、今なら素直に思えた。
瞼が落ちそうに重い。気がつけば空がすでに白み始めている。もう夜明けだ。二番地のみんなは俺が帰るのを今も待っているのだろう。ガイの話によれば、ここ最近は俺が出かけてから戻ってくるまで、誰ひとり眠らないということだから。まずは謝ろう。そして彼らになにかしてやりたい。今の身体では何もできやしないが、治ったら、きっと。
その前に、ユリにお礼を言いに、またあの池に行こう。
今度は一人ではなくガイも連れて。
ガイの背中で、俺は静かな睡魔に誘われて、ゆっくりと目を閉じ意識を手放した。