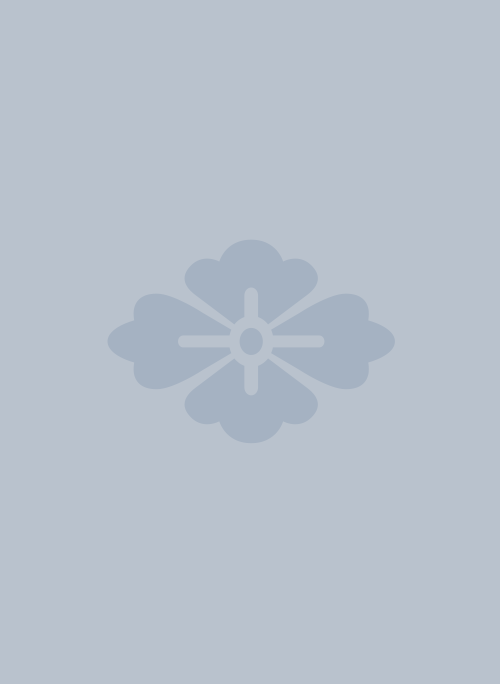さて、"素振り"も終わった所で本番いくか。
足元に転がる樫原だったモノを踏みつけ、俺はマンションに入った。
管理人は俺を見てギョッとする。
樫原の返り血と、血塗れの鉄バットを見ればそれはもう不審者確定。
「開けろ、無理矢理抉じ開けられられてぇのか」
管理人は激しく首を振った。
怯えた顔でエントランスの鍵を開ける。
「おい、406号室の鍵も寄越せ」
「そ、それは…」
「殺されてぇのか」
「わ、わかりました!わかりましたから、殺さないで下さい!!」
鍵を受け取り、階段から奴の元へ向かう。
引きずっている鉄バットの音が響くが、誰とも鉢合わせせずに四階に辿り着けた。
406号室…インターホンを押すと、男の声が聞こえた。
「はい」
「Da adesso punire il」(今からお前を処刑する)
「…!Il diavolo d'Italia …!?」(イタリアの悪魔だと…!?)
すぐにそのインターホンは切られ、奴がこちらに走ってくる足音が聴こえた。
ドアに手を触れさせる前に、鍵を開けて蹴破るようにして入った。
すぐ目の前には、奴が上半身裸で立っている。
「Non Kill Me Please…!!」(殺さないでくれ…!!)
「Perché?」(何故だ?)
「Vuoi essere un essere umano!」(人間になりたいんだ!)
「………………」
この強欲悪魔が…血の臭いが既にお前に染み付いているんだよ。
「È povero diavolo…」(哀れな悪魔だ…)
「A…Aiuto…!」(た…助け…!)
高らかに、俺はバットを振るった。
足元に転がる樫原だったモノを踏みつけ、俺はマンションに入った。
管理人は俺を見てギョッとする。
樫原の返り血と、血塗れの鉄バットを見ればそれはもう不審者確定。
「開けろ、無理矢理抉じ開けられられてぇのか」
管理人は激しく首を振った。
怯えた顔でエントランスの鍵を開ける。
「おい、406号室の鍵も寄越せ」
「そ、それは…」
「殺されてぇのか」
「わ、わかりました!わかりましたから、殺さないで下さい!!」
鍵を受け取り、階段から奴の元へ向かう。
引きずっている鉄バットの音が響くが、誰とも鉢合わせせずに四階に辿り着けた。
406号室…インターホンを押すと、男の声が聞こえた。
「はい」
「Da adesso punire il」(今からお前を処刑する)
「…!Il diavolo d'Italia …!?」(イタリアの悪魔だと…!?)
すぐにそのインターホンは切られ、奴がこちらに走ってくる足音が聴こえた。
ドアに手を触れさせる前に、鍵を開けて蹴破るようにして入った。
すぐ目の前には、奴が上半身裸で立っている。
「Non Kill Me Please…!!」(殺さないでくれ…!!)
「Perché?」(何故だ?)
「Vuoi essere un essere umano!」(人間になりたいんだ!)
「………………」
この強欲悪魔が…血の臭いが既にお前に染み付いているんだよ。
「È povero diavolo…」(哀れな悪魔だ…)
「A…Aiuto…!」(た…助け…!)
高らかに、俺はバットを振るった。