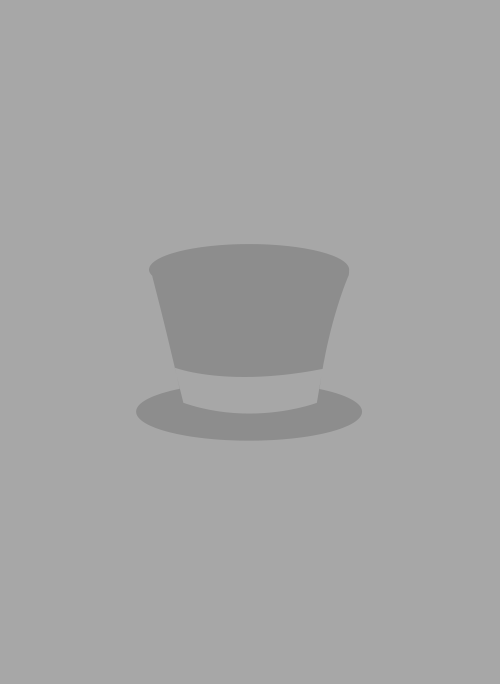「で? 一体どうしたの?」
家に入ってからも3人の様子は全く変わらない。
誰からも話そうとせず、部屋はとても重苦しい空気が漂っている。
全く話そうともしない大也の様子を見かねて、みゆきは率先して会話の打破を試みる。
深青だけが、みゆきの顔を見て力なく答える。
「みゆきちゃんにも話したほうがいいのかな………」
自分がいかに蚊帳の外かというのを思い知らされた気がしてみゆきはむなしくなる。
自分の家でもないのになぜかみんなにお茶の用意までして、話の本筋は自分には関係がない。
まるで自分が尽くしているだけの単なる暇人のようではないか。
でも、それでも気になるために引き下がれない自分にもちょっと悲しい気がする。
「私だけ仲間はずれはないんじゃない! ちょっと、気、悪いよ」
「ごめん。そう意味じゃないんだ。ただ、巻き込んじゃっていいのかな、と思って」
あからさまに気分を害したようなみゆきの態度に深青はたじろぐ。
そして、弁解しながら大也の方を見る。
「大丈夫。俺のことを言ってるんだろ。こいつは大体のことは知ってるから」
大也の答えになんとなく言おうとしていることがみゆきにもわかってくる。
「もしかして、変なものが見えるとかの関係?」
恐る恐る話すみゆきに大也が苦笑する。
「ああ………。」
みゆきには全く理解できない話を今からしようとしているのかと思うととても寂しい気持ちになる。
このことは自分しか知らない、大也との2人だけの秘密だと自分では思っていたのに、それを知る人ができる。
それも、そのことをおそらく自分よりも理解している人が。
そのことにみゆきの心の中ではさざ波が立っていたが、みゆきは微塵も見せず取り繕う。
「そっか。大丈夫だよ。私はちゃんと知っているから」
その言葉をどんな思いで言ったのか、深青たちは知る由もなかった。